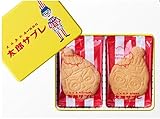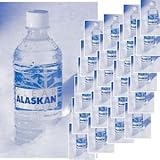2017.06.08.【赤祖父俊一。米アラスカ大学名誉教授。】。米国が「パリ協定」から離脱した。私=赤祖父俊一=の率直な意見は、「これでやっと地球温暖化、気候変動の問題を学問として研究できるかもしれない」ということである。
多くの読者は「いまさら何をバカな」と思われるであろう。地球温暖化は現在、確かに進行している。それなのに米国はなぜ、「パリ協定」から離脱したのかと疑問を持つのは当然である。しかし、これを機会になぜこの問題が、「パリ協定」という世界中の多くの国を挙げての協定にまで発展してしまったのかを冷静に考えてみる必要がある。
地球温暖化を含めた気候変動には、自然変動(人間がコントロールできない)と、人間の活動(炭酸ガス放出)によって起きる人的変動がある。地球は過去からの多くの気候変動を繰り返してきたが、これは自然変動であり、当然、現在でも起きている。
多くの読者は「いまさら何をバカな」と思われるであろう。地球温暖化は現在、確かに進行している。それなのに米国はなぜ、「パリ協定」から離脱したのかと疑問を持つのは当然である。しかし、これを機会になぜこの問題が、「パリ協定」という世界中の多くの国を挙げての協定にまで発展してしまったのかを冷静に考えてみる必要がある。
地球温暖化を含めた気候変動には、自然変動(人間がコントロールできない)と、人間の活動(炭酸ガス放出)によって起きる人的変動がある。地球は過去からの多くの気候変動を繰り返してきたが、これは自然変動であり、当然、現在でも起きている。
●人的変動とばかりは言えぬ温暖化
それなのに、なぜ現在、温暖化を一方的に人的変動と決めてしまったのか。実際には、現在進行している温暖化については、自然変動と人的変動を正確に確定して区別できないのである。
現在、気候変動問題で大活躍している人たち(報道も含めて)に、この区別について質問しても、「世界の気候学の権威からなる『気候変動に関する政府間パネル』(IPCC)が人的変動であるとしているから」という答えが返ってくるだけだ。
しかし、実際には気候学の権威の話でも「計算が合う、または計算で合わせられる」程度のことでしかないようだ。それにもかかわらずIPCCと報道は、この未熟な学問を政治的大問題にしてしまった。
地球温暖化の影響例として必ず引き合いに出されるのが「北極海の海氷の減少」である。北極点で気温が零度程度になるのは、1年でわずか1カ月ほどである。この現象について、アラスカ大学国際北極圏研究センターは北極圏各国と協力し、多くの砕氷船を使って、15年間研究を続けてきた。その第一報が米科学誌「サイエンス」4月21日号に発表された。
それによると、北極海には北大西洋の暖流が流入しており、氷を下から融かしている証拠を突き止めたとのことである。この結果には反論も出るであろう。この問題では、気候学者はまだ結論に達していない。これは1例でしかない。
それなのに、なぜ現在、温暖化を一方的に人的変動と決めてしまったのか。実際には、現在進行している温暖化については、自然変動と人的変動を正確に確定して区別できないのである。
現在、気候変動問題で大活躍している人たち(報道も含めて)に、この区別について質問しても、「世界の気候学の権威からなる『気候変動に関する政府間パネル』(IPCC)が人的変動であるとしているから」という答えが返ってくるだけだ。
しかし、実際には気候学の権威の話でも「計算が合う、または計算で合わせられる」程度のことでしかないようだ。それにもかかわらずIPCCと報道は、この未熟な学問を政治的大問題にしてしまった。
地球温暖化の影響例として必ず引き合いに出されるのが「北極海の海氷の減少」である。北極点で気温が零度程度になるのは、1年でわずか1カ月ほどである。この現象について、アラスカ大学国際北極圏研究センターは北極圏各国と協力し、多くの砕氷船を使って、15年間研究を続けてきた。その第一報が米科学誌「サイエンス」4月21日号に発表された。
それによると、北極海には北大西洋の暖流が流入しており、氷を下から融かしている証拠を突き止めたとのことである。この結果には反論も出るであろう。この問題では、気候学者はまだ結論に達していない。これは1例でしかない。
●環境破壊の食い止めこそが重要
温暖化問題は、まだ世界中が大騒ぎするような問題ではない。1970年代には、「大氷河期」が近いとして、ひと騒ぎがあった。寒冷化の騒ぎもまた起きるであろう。
私は炭酸ガスの放出量を電力節約などで軽減することに異論はない。気掛かりなのは、現在、環境破壊、大気汚染、漁獲量減少、洪水、砂漠化、異常気象のすべて、その他多くの事が同一に、または混同して論じられていることだ。その結果、「地球を守ろう」のスローガンのもとに、「パリ協定」ができてしまった。
米国の協定離脱を非難するのも良いが、自然変動を忘れて気候変動を論ずることはできない。科学問題を政治問題にしてはならない。さらに気候変動では適応(自然変動)と緩和(人的変動)は別問題である。この区別を誤れば予算の無駄になる。
「地球を守る」というなら、不確実なコンピューター予測などを根拠にせず、「パリ協定」の精神を活かして、現実に目の前で起きている環境破壊を最低限に食い止めることだ。その国際協力にこそ全力で取り組むべきではないか。地球は有限である。
温暖化問題は、まだ世界中が大騒ぎするような問題ではない。1970年代には、「大氷河期」が近いとして、ひと騒ぎがあった。寒冷化の騒ぎもまた起きるであろう。
私は炭酸ガスの放出量を電力節約などで軽減することに異論はない。気掛かりなのは、現在、環境破壊、大気汚染、漁獲量減少、洪水、砂漠化、異常気象のすべて、その他多くの事が同一に、または混同して論じられていることだ。その結果、「地球を守ろう」のスローガンのもとに、「パリ協定」ができてしまった。
米国の協定離脱を非難するのも良いが、自然変動を忘れて気候変動を論ずることはできない。科学問題を政治問題にしてはならない。さらに気候変動では適応(自然変動)と緩和(人的変動)は別問題である。この区別を誤れば予算の無駄になる。
「地球を守る」というなら、不確実なコンピューター予測などを根拠にせず、「パリ協定」の精神を活かして、現実に目の前で起きている環境破壊を最低限に食い止めることだ。その国際協力にこそ全力で取り組むべきではないか。地球は有限である。
https://jinf.jp/feedback/archives/20752










![カフェ・ド・パリ カラフルパーティー スウィート・チェリー [ スパークリング 甘口 フランス 750ml ]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/414ZW%2BsF7IL._SL160_.jpg)