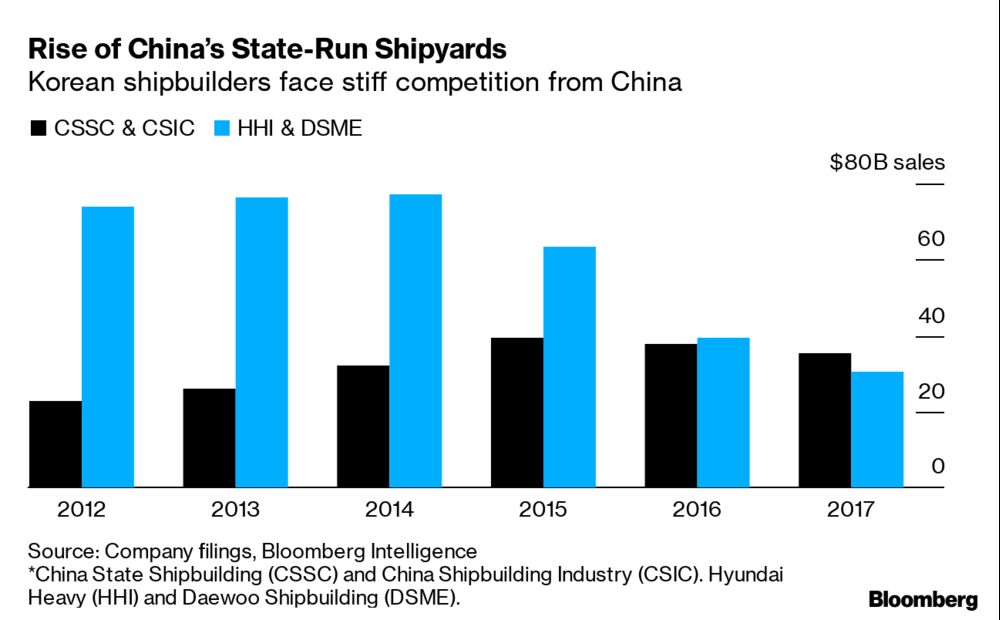2022年3月期までの3年間に借入金や社債で約1兆円を調達。本業で稼ぐ資金なども合わせて、M&A(合併・買収)や設備投資を合計約4.5兆円と倍増させる。
非中核事業の売却などで財務改善が進んだため、負債を活用して資本効率(総合2面きょうのことば)を高める戦略に転換する。
これまで日本企業は借金返済を優先し、投資などは抑制してきた。そうした縮み志向を抜け出す企業が増えていく可能性がある。
負債で設備投資などを増やして業績拡大につなげれば、少ない資本で効率的に稼ぐことになる。これを「財務レバレッジ」といい、米国企業などが得意とする戦略だ。
投資家が重視する自己資本利益率(ROE)を押し上げる効果もある。
この財務レバレッジを効かせる戦略に日立は転じる。08年の米金融危機後の業績悪化を受けた構造転換が進んだためだ。
金融や物流、工具などの事業を相次いで売却し、09年当時に22社あった上場子会社は4社まで減少した。
海外プラントなど不採算事業からも撤退した。投資は抑制し、有利子負債は19年3月末で約1兆円と36年ぶりの低い水準になった。
調達する1兆円は全額を負債でまかなう。銀行借り入れが中心で、社債も発行する。
財務改善で格付けはダブルAマイナス(格付投資情報センター)と10年ぶりの高さになっており、低利で調達できる見通し。
非中核事業や持ち合い株などの不稼働資産もさらに8000億円相当を売却する。
持ち合い株は「ゼロにするのは難しいが、できる限り減らす」(西山光秋・最高財務責任者)。現預金を2000億円取り崩し、本業で稼ぐ現金(営業キャッシュフロー)も加えて今後3年で約4.5兆円を成長投資に回す。
19年3月期までの3年の約2倍の規模となる。
最大の項目はM&Aで総額2.5兆円を投じる。スイスABBの送配電部門には負債の引き受け分も含めて1兆円規模を振り向ける。
そのほかでは、「海外のIT(情報技術)サービスなどで良い案件があれば検討する」(西山氏)。日立はあらゆるモノがネットにつながるIoTビジネスを拡大しており、相乗効果が見込めるためだ。
残る2兆円は設備投資や研究開発などに充てる。
センサー設置による工場の新鋭化などの投資や、人工知能(AI)やロボットの研究が重点分野となる。配当などの株主還元も業績拡大に応じて充実させる。
日本企業の財務は攻めの機運が徐々に強まっている。
M&Aや設備投資を増やした結果、上場約3600社(金融など除く)は18年度に手元資金を考慮した純有利子負債が約130兆円と1年前より6%増えた。金利低下を受けて、足元では社債発行が急増している。
日本企業のROEは10%弱と米国勢(15%)を下回る。日立は前期実績で6.8%だった。
財務レバレッジの効果でROEが世界水準に近づけば、日本企業は投資マネーを呼び込みやすくなる。
その半面、負債を過度に積み上げると不況には弱くなる。景況感などを見極めながら、攻めの度合いを最適化する手腕が問われることになる。