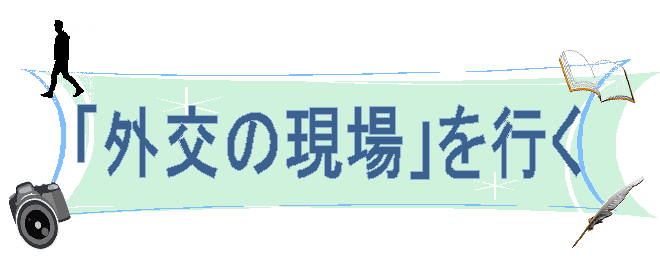
◉第7回◉ 朝鮮王朝最後の王女
1910年。日本による韓国併合。これをどう解釈するか?
日本と韓国の近代史を考える際に、避けて通れない問題である。誇り高き韓国人はこれを屈辱と感じ、できれば歴史上なかった事態にしたいと考えている。同じように植民地経験を持つ台湾人が、日本支配をおおむね肯定的に捉えているのと、それは対照的でもある。
あまり言及されることがないが、日本の明治天皇と朝鮮の高宗は、それぞれ1852年11月3日、1852年7月25日に生まれた。つまり同年生まれである。しかし歴史的事実は残酷だ。明治天皇は帝国主義時代の「名君」になり、高宗は時に「愚公」と批判されることもある。
今回のテーマは、その高宗に生まれた最後の王女・徳恵姫(1912ー1989)にまつわる物語である。
日本による韓国併合は、歴史的事実に即して言えば、「大日本帝国」による「大韓帝国」の併合である。急成長した新興国家による没落国家の「吸収合併」であった。「朝鮮王朝最後の王女」の生涯からも、そのことがお分かりいただけるだろう。
<現場①>旧李王家邸宅(港区・赤坂プリンスホテルクラシックハウス)
神宮外苑の秩父宮ラグビー場の場所には、戦前、女子学習院があった。皇族をはじめとした名門家庭の子女がここに通った。
1925年4月、京城(現在のソウル)から、ひとりの少女が転校して来た。高宗と下級官女の間に生まれた徳恵姫である。同級生には、後に満州帝国の愛新覚羅溥傑夫人になった嵯峨浩(ひろ)や、「憲政の神様」と呼ばれた政治家・尾崎行雄の3女・雪香らがいた。雪香によると、徳恵姫は「口数の少ない方で、運動会ではいつもビリで、本当にお気の毒でした」という。
「私があなたの立場なら、独立運動をやっているのに、なぜ、あなたはなさらないの?」。ある日、雪香はストレートな質問を徳恵姫に向かって発した。日本の朝鮮政策に批判的だった父親の影響があったようだ。しかし朝鮮から来た少女は、黙ったままだった。彼女の日本語理解力は十分だったが、この過酷な質問には答えられないだろう。沈黙は無理もない。
当時、彼女は宮内省から提供された麻布・鳥居坂の邸宅に、兄の皇太子・李垠(リウン)や日本人夫人の方子(まさこ、皇族梨本宮守正の長女)とともに、住んでいた。当時の住居地図をもとに探索すると、そこには現在、K-POPS公演なども行われる劇場「Zeppブルーシアター六本木」があった。その敷地のほとんどが駐車場だが、立入り禁止の庭の一角に残る鳥居や大木が、わずかに往時をしのばせる。北隣が「スヌーピーミュージアム」であり、南隣は旧岩﨑邸跡地の「国際文化会館」である。
徳恵姫は1930年3月、紀尾井町の元北白川宮邸の敷地に完成した新しい洋館「李王家東京御殿」に引っ越した。桃の節句の佳き日であったが、この邸宅が後にどういう運命をたどるか、若い彼女はまだ知らない。
この洋館が現在の「赤坂プリンスホテル・クラシックハウス」だ。ホテルの新築と合わせて改修され、今年夏に再オープンした。歴史を感じさせる建物の一階は、洒落たレストランになっている。ウェイターに聞くと、時折、韓国人観光客が訪ねて来るという。近代朝鮮の「悲運の現場」がそこにあるからだ。
李垠の戦後は悲惨だった。紀尾井町の李王家邸を参議院議長公舎として間貸しし、方子とともに侍女部屋で暮らしていた。一時期、駐日韓国大使館の候補地になったものの、韓国政府から購入資金の送付はなかった。これが「西武」の総帥・堤康次郎に4000万円で売却した背景である。しかし、この4000万円も借金返済などでほとんど消えたという。
伊藤博文から譲渡された大磯の別邸・滄浪閣(そうろうかく)は戦後、楢橋渡(政治家)の手を経て、堤康次郎の所有になった。現在の大磯プリンスホテル別館である。
2005年7月、赤坂プリンスホテルの一室で老人の遺体が見つかった。李垠皇太子・方子夫人の二男・李玖(リク、当時73歳)である。今上天皇とは「はとこ」の関係にある人物だ。子供はおらず、これで李王家の直系子孫は断絶した。当時、日本では皇位継承問題が表面化していたが、翌2006年、秋篠宮家に皇族男子(悠仁親王)が誕生したことで、危機を脱した。
日本の皇室と朝鮮王家の明暗は、このように対照的である。朝鮮王家の金銭感覚のなさも目立つ。「国運」というには、あまりに悲劇的だ。
<現場②>対馬・厳原(宗武志との結婚)
本馬恭子「徳恵姫ー李氏朝鮮最後の王女」(1998)は、悲運の王女の生涯を丹念に追った日本で唯一の著作だ。出版当時、著者は長崎の女子大講師であり、版元の「葦書房」は、かつて毎日新聞西部本社記者だった三原浩良が社長を務めていた。私も個人的恩義がある先輩だ。
この著作は、3・1独立運動直後に書かれたプロパガンダ本「朝鮮独立運動の血史」(朴殷植)を不用意に引用するなど、出版当時の時代風潮だった「贖罪史観」が背景にあるものの、取材自体はきわめて丹念に行っている。
その本の口絵に印象深い写真がある。1931年秋、対馬を訪問した徳恵姫と、結婚した宗武志(そう・たけゆき)伯爵のツーショットだ。宗家は対馬藩主の子孫という名門である。当時、徳恵姫19歳、武志23歳。新郎は東京帝大卒、長身のイケメンである。戦後は、麗沢大学教授を務めた英文学者だ。
韓国では「彼は李王家の莫大な持参金を目当てに結婚した」「徳恵姫が病気になるや精神病院に送り込んだ」との風評が少なくなかった。日本側にも同様の見方があった。いわゆる政略結婚説である。本馬の著書の目的は、これに対して「ふたりの人間関係を史実に基づいて明らかにする」ことであり、ふたりに「愛がなかった」という見方に異議を唱えることだった。「愛があったにもかかわらず、彼らは不幸だった」ことを立証したことに、この著作の意義がある。
武志は北原白秋門下の詩人だ。妻に捧げた彼の詩「閑感」がある。その一部を引用する。
愛し妻よ、鳴るや、渡殿/百千鳥 群れ羽ばたくや/離れ屋の 赤き長押に/白珠を 書けて 嘆くや。/愛し妻よ、わたりは絶えて/いとし子を われは抱けり
彼の詩的才能と妻に対する愛情は、この一編の詩から十分に推測できる。
「日鮮融和」を目的とする政略結婚説には、異論を唱える研究者が増えている。
それは最近、日韓歴史ドラマの定番になってい李垠・方子夫妻の場合でも同様だ。縁談のパイプ役だった宮内省事務官の回顧録には、二人の結婚が梨本宮家側が主導されたという記録が残されている。最近になって発掘された。ほかにも傍証は少なくない。この点は新城道彦「朝鮮王公族ー帝国日本の準皇族」(中公新書)にわかりやすく叙述してある。
新城は、徳恵姫の結婚も「政略結婚と結論づけるには留保が必要であろう」と書いている。その理由は、徳恵姫にとって、伯爵家との縁談は「必ずしも悪い話ではなかった」からだ。朝鮮の当時の事情では、「朝鮮貴族ならば子爵以下しか見込めなかったのである」という。
徳恵姫は戦後の華族解体により、一般の日本人になった。1955年には離婚して、母親の氏を名乗って「梁徳恵」となり、ソウルに戻って、韓国籍を得た。
彼女はなぜ離婚したのか。宗武志はなぜ徳恵姫と離婚したのか。この点については、明快でない。徳恵姫の精神病悪化もあり、家庭事情が複雑すぎるからだ。本馬は前著で、彼の詩を引用して宗武志の真情を弁護した。
「狂へるも 神の子なれば あわれさは 言はむかたなし」
この表現に偽善やまやかしがあるとは思えない、と本馬は断じている。
<現場③>韓国映画「徳恵翁主」の虚妄
今年の夏、韓国で徳恵姫をヒロインにした映画「徳恵翁主」が封切られた。清楚な人気女優ソン・イェジンが徳恵姫を演じた。観客動員500万人を突破するヒット作になったが、映画自体は批判に遭遇した。(翁主とは側室の王女の意。正妃の王女は公主と呼ばれる)
有力紙「中央日報」は社説「韓国史研究の新たな踏み台に」で、以下のように批判した。
「決定的なミスは、徳恵翁主を独立闘士型のキャラクターとして描いたという点だ。映画で徳恵翁主は日本に強制徴用されてきた朝鮮の民を慰め、日帝に抵抗する朝鮮留学生の集いに参加する」
なんとも荒唐無稽な人物に、映画は仕立てた訳だ。それにもかかわらず映画はヒットした。ありもしなかった「夢の歴史」を見たいという韓国人の願望が投影したと言うしかない。実証主義を基礎にしたフィクションとはほど遠い。これは実は、最近の韓国歴史映画の特徴でもある。
韓国にとってさらに残念なのは、韓国における徳恵姫研究が、18年前に刊行された本馬の著書を超えるものがないという事実だ。これは韓国近現代史研究の全般にわたる「弱点」であり、「大韓帝国亡国史」に関する韓国人の無関心と関係がある。つまり彼らにとって「見たくない歴史」なのだ。だから当時を描いた歴史映画はいきおい「史実を美化したファンタジー」になっているのだ。この虚妄に満ちた「自分の壁」を突破しない限り、韓国史叙述の未来はないと、私には思える。
1989年4月21日、徳恵姫はソウル昌徳宮にある「楽善斎」で、看護師2人に見守られて永眠した。享年76。宗武志は1985年に77歳で死去していた。二人には、ひとり娘「正恵」がいた。早稲田大学を卒業した彼女は、英語教諭と結婚したが、1956年「自殺する」旨の遺書を残し失踪した。遺体が見つかったのは、その50年後だった。
| 下川正晴(しもかわ・まさはる) 1949年、鹿児島県霧島市生まれ。大阪大学法学部卒。毎日新聞ソウル、バンコク特派員、論説委員などを歴任。韓国外国語大学客員教授、大分県立芸術文化短大教授を経て、文筆業。 |












