では本命とは何でしょうか。それはほかでもありません。言論や情報メディアのあり方に戯画化して表われる、僕らのこの社会のあり方(構造)そのものです。いいかえれば、僕ら1人1人の存在のあり方(構造)そのものです。そして、そうした僕らみんなのあり方のエッセンスを、現代日本において最もグロテスクに凝縮した象徴が、「原子力体制」(吉岡斉)という構造ではなかったかと思うのです。
原子力体制とは、狭義には、さしあたり<原子力ムラ>といわれているものに当たります。<原子力ムラ>とは、今を時めく飯田哲也氏が、かつて自らも技術者としてそこに深く関わった体験から1997年に命名したもので、飯田氏によれば、電力会社、原子力産業、原子力官庁、研究機関の「産・官・学の利益共同体」とされています(『論座』1997年2月号)。具体的に補足すると、
・「電力会社」とは、(沖縄電力を除き)原発を擁する全国9電力会社、そしてその傘下の日本原電、日本原燃
・「原子力産業」とは、原子炉メーカー(とくに東芝・日立・三菱)、ゼネコン、商社、金融機関など
・「原子力官庁」とは、通産省~経産省とくにその下の「資源エネルギー庁」「原子力保安・安全院」、科学技術庁~文部科学省の関係各課、総理府~内閣府とくにその下の「原子力委員会」「原子力安全委員会」など
・「研究機関」とは、東大を頂点とする大学、原子力機構(原研と動燃~核燃料サイクル開発機構とを統合)・理研・放医研など独立行政法人研究機関、電力中央研究所など電力会社系民間研究機関など
からなるものといえましょうが、これに政治家(中曽根康弘~田中角栄から電力族の自民党議員と、電機連合・電力総連系の民主党議員等)、マス・メディア(正力松太郎の読売新聞・日本テレビ~朝日新聞の原発推進への転向~オール・メディアの原発翼賛体制~今日のいわば”原子力記者クラブ”)をも加えて、「産」「政」「官」「学」「メ」の一大複合体とでもいうべき規模まで広げて考えるのがよさそうに思います。
とりわけ1950年代中・後半の原子力導入期に、「政」(”中曽根予算”や”正力構想”)と「メ」(読売新聞の執拗な原子力キャンペーン)が果たした牽引車的な役割は決定的で、以後やがてこの複合体の中核を占めることになる「産」「官」すらも、最初はこの「政」と「メ」の強烈な働きかけに覚醒させられて動き始め、そのあと急速に「政」と「メ」を従えるに至ったのでした。
それに対し「学」は、最初期から今日に至るまで、つねに顧問的な重要な位置に祀り上げられながら、現実には他をリードする積極的な指導力を少しも発揮することはできませんでした。”学者なんて宴席に侍らせる芸者みたいなもの”という「産」「官」界では公然の秘密を、自ら地で行って証明してしまったのでしょうか。
さてこのように<原子力ムラ>は、原子力という最先端の巨大科学技術を中心にすえながら、その下で「産」「官」を中核に、「政」「学」「メ」・・・と各セクターが一個のムラのごとくに閉鎖的な利益共同体を形成し、この共同体内における合意が原子力政策に関する意思決定権を事実上独占して、そのまま「国策」として強い効力をもつ一方、共同体外部の影響力は最小限となるように限定され排除されています。
どこか天皇制国家の”皇室の藩屏”たちとよく似て、その内部では、互いにナワバリ争い的な利害対立をつねに孕みつつも、全体としては原子力推進という共通の方向性の上にもたれあい、カネ・人・情報の流れを互いに融通し共有しあいながら(献金・人事交流・天下り・インサイダー談合等々・・・)、意思決定の最終的な責任の所在は巧みに曖昧化し、それでいて外部に対しては、まさにムラ的な閉鎖性をあらわにし、おのれの延長として服従させうる限りにおいて積極的に関わりをもち、カネ・人・情報等も支配の切り札という限りでのみ按配するのです(補助金・交付金・人事干渉・トラブル隠し・原子力神話等々・・・)。
このため<原子力ムラ>にとって外部とは、自らが支配する対象でこそあれ、自らをチェックする主体として対峙することなどはじめからありえないものなのです。実際、本来チェック機能を果たすべき、「産」における労働組合、「政」における議会、とくに(革新系)野党、「官」における規制機関、「学」と「メ」における批判的言説や代替案とその論者、さらには「産」「政」「官」「学」「メ」すべてに対する司法、等々・・・これらいずれもが、懐柔され換骨奪胎されて(時には抹殺されて)、むしろ<原子力ムラ>を補完する準構成員のようにすらなってしまうのでした。あるいは、それを嫌って”反-原子力ムラ”の立場をとっても、往々にしてあたかも”反原子力-ムラ”というもう1つの<原子力ムラ>のごときになってしまって、結局かえって<原子力ムラ>(的なもの)を維持し増殖させる結果となりかねませんでした(論者によっては、反原発運動も<原子力ムラ>の構成要素の1つに数えています)。
この増殖力はどこからくるのでしょうか。興味深いことに、もともと東電の社内では、ずいぶん前から、原子力本部(技術者約3千人)そのものが<原子力村>と呼ばれてきたのだそうです(朝日新聞5月25日付、志村嘉一郎『東電帝国その失敗の本質』pp.94-5,213)。原子力部門は他の部門との人事交流もなく、閉ざされた部門として成長し(尤も他の部門も、それぞれ”労務ムラ””営業ムラ””総務ムラ”等々になっているようですが)、その内部では原子力本部長が絶対の権限をもつヒエラルヒーを形成し、社長や会長といえども口出しできない「聖域」となってきたとのこと。なかでも一切の配電の権限を握るその運転室は、「神の座」と畏れられてきたそうです。ただ、逆にいえば東電の経営陣には原子力の専門家は入れず、だからこそ自分の村をつくらざるをえない。そのかわり、対外的に関わりの深い官僚や政治家、学者たちを自分たちの村に引き込んで、その村を拡大してできたのが、いわゆる<原子力ムラ>というわけです。今は内部となっている領域も、もともとは外部だったので、同様に今は外部の領域も、次々に内部に繰り込まれてゆく可能性があります。<原子力ムラ>にとっての外部とはそういうものです。ならば逆に、その内部の中の内部は…と遡行してゆくと、それはまさしくムラの内奥深く厳かに隠された、原子力本部の聖なる神殿だったのです。
こうしてみてくると、<原子力ムラ>はいうなれば、原子力という共通の<神>、原子力推進という共通の<神話>のもとに、異なる利権に競り合う<神官>たちを垂直的に統合する、きわめて宗教的な共同体ということができます。そう、呪術を駆逐し宗教を否定してきたはずの科学技術は、今やその最先端に至って再び、擬似呪術的・擬似宗教的にこそ維持されるしかない地点に立ち至っていると言わねばなりません。最先端の宗教教団としての高度科学技術国家・・・その教団の司祭たる<原子力ムラ>の専門家エリートたち・・・。
原子力の推進にあたって、安全神話、平和利用神話、安価神話、無資源国神話、核燃料サイクル神話、クリーン神話、安定供給神話(原発止めると電気が足りないやら、いきなり原始時代に逆戻りするやらの事実無根の神話)、etc.etc.・・・と次々に新たな神話が生み落とされねばならなかったのも、このためではないでしょうか。
いやもっといえば、「原子力」という語自体がすでに1つの神話でした。同一の原語”atomic energy”を「核エネルギー」でなく「原子力」と訳し分けて、あたかも「核」兵器や「核」爆弾とは別種の世界であるかのような印象操作を、この訳語に忍び込ませながら、涼しい顔して微笑んできたわけですから。
まして「平和利用」となれば、本当はただ端的に「核の民事利用」と言い直すべきもので、「平和」とは全く無縁な単なる神話にすぎないことは、スリーマイル島事故・チェルノブイリ事故でもとっくに明らかになっていたことですが、3・11原発震災以降、もう誰の目にも疑いないことでしょう。
前回みたような、本当は正しくないかもしれない情報が「真実」となり、本当は正しいかもしれない情報が「デマ」となりかねない基本構造は、高度科学技術国家のこの擬似宗教性にこそあったというべきでしょう。
<つづく>
原子力体制とは、狭義には、さしあたり<原子力ムラ>といわれているものに当たります。<原子力ムラ>とは、今を時めく飯田哲也氏が、かつて自らも技術者としてそこに深く関わった体験から1997年に命名したもので、飯田氏によれば、電力会社、原子力産業、原子力官庁、研究機関の「産・官・学の利益共同体」とされています(『論座』1997年2月号)。具体的に補足すると、
・「電力会社」とは、(沖縄電力を除き)原発を擁する全国9電力会社、そしてその傘下の日本原電、日本原燃
・「原子力産業」とは、原子炉メーカー(とくに東芝・日立・三菱)、ゼネコン、商社、金融機関など
・「原子力官庁」とは、通産省~経産省とくにその下の「資源エネルギー庁」「原子力保安・安全院」、科学技術庁~文部科学省の関係各課、総理府~内閣府とくにその下の「原子力委員会」「原子力安全委員会」など
・「研究機関」とは、東大を頂点とする大学、原子力機構(原研と動燃~核燃料サイクル開発機構とを統合)・理研・放医研など独立行政法人研究機関、電力中央研究所など電力会社系民間研究機関など
からなるものといえましょうが、これに政治家(中曽根康弘~田中角栄から電力族の自民党議員と、電機連合・電力総連系の民主党議員等)、マス・メディア(正力松太郎の読売新聞・日本テレビ~朝日新聞の原発推進への転向~オール・メディアの原発翼賛体制~今日のいわば”原子力記者クラブ”)をも加えて、「産」「政」「官」「学」「メ」の一大複合体とでもいうべき規模まで広げて考えるのがよさそうに思います。
とりわけ1950年代中・後半の原子力導入期に、「政」(”中曽根予算”や”正力構想”)と「メ」(読売新聞の執拗な原子力キャンペーン)が果たした牽引車的な役割は決定的で、以後やがてこの複合体の中核を占めることになる「産」「官」すらも、最初はこの「政」と「メ」の強烈な働きかけに覚醒させられて動き始め、そのあと急速に「政」と「メ」を従えるに至ったのでした。
それに対し「学」は、最初期から今日に至るまで、つねに顧問的な重要な位置に祀り上げられながら、現実には他をリードする積極的な指導力を少しも発揮することはできませんでした。”学者なんて宴席に侍らせる芸者みたいなもの”という「産」「官」界では公然の秘密を、自ら地で行って証明してしまったのでしょうか。
さてこのように<原子力ムラ>は、原子力という最先端の巨大科学技術を中心にすえながら、その下で「産」「官」を中核に、「政」「学」「メ」・・・と各セクターが一個のムラのごとくに閉鎖的な利益共同体を形成し、この共同体内における合意が原子力政策に関する意思決定権を事実上独占して、そのまま「国策」として強い効力をもつ一方、共同体外部の影響力は最小限となるように限定され排除されています。
どこか天皇制国家の”皇室の藩屏”たちとよく似て、その内部では、互いにナワバリ争い的な利害対立をつねに孕みつつも、全体としては原子力推進という共通の方向性の上にもたれあい、カネ・人・情報の流れを互いに融通し共有しあいながら(献金・人事交流・天下り・インサイダー談合等々・・・)、意思決定の最終的な責任の所在は巧みに曖昧化し、それでいて外部に対しては、まさにムラ的な閉鎖性をあらわにし、おのれの延長として服従させうる限りにおいて積極的に関わりをもち、カネ・人・情報等も支配の切り札という限りでのみ按配するのです(補助金・交付金・人事干渉・トラブル隠し・原子力神話等々・・・)。
このため<原子力ムラ>にとって外部とは、自らが支配する対象でこそあれ、自らをチェックする主体として対峙することなどはじめからありえないものなのです。実際、本来チェック機能を果たすべき、「産」における労働組合、「政」における議会、とくに(革新系)野党、「官」における規制機関、「学」と「メ」における批判的言説や代替案とその論者、さらには「産」「政」「官」「学」「メ」すべてに対する司法、等々・・・これらいずれもが、懐柔され換骨奪胎されて(時には抹殺されて)、むしろ<原子力ムラ>を補完する準構成員のようにすらなってしまうのでした。あるいは、それを嫌って”反-原子力ムラ”の立場をとっても、往々にしてあたかも”反原子力-ムラ”というもう1つの<原子力ムラ>のごときになってしまって、結局かえって<原子力ムラ>(的なもの)を維持し増殖させる結果となりかねませんでした(論者によっては、反原発運動も<原子力ムラ>の構成要素の1つに数えています)。
この増殖力はどこからくるのでしょうか。興味深いことに、もともと東電の社内では、ずいぶん前から、原子力本部(技術者約3千人)そのものが<原子力村>と呼ばれてきたのだそうです(朝日新聞5月25日付、志村嘉一郎『東電帝国その失敗の本質』pp.94-5,213)。原子力部門は他の部門との人事交流もなく、閉ざされた部門として成長し(尤も他の部門も、それぞれ”労務ムラ””営業ムラ””総務ムラ”等々になっているようですが)、その内部では原子力本部長が絶対の権限をもつヒエラルヒーを形成し、社長や会長といえども口出しできない「聖域」となってきたとのこと。なかでも一切の配電の権限を握るその運転室は、「神の座」と畏れられてきたそうです。ただ、逆にいえば東電の経営陣には原子力の専門家は入れず、だからこそ自分の村をつくらざるをえない。そのかわり、対外的に関わりの深い官僚や政治家、学者たちを自分たちの村に引き込んで、その村を拡大してできたのが、いわゆる<原子力ムラ>というわけです。今は内部となっている領域も、もともとは外部だったので、同様に今は外部の領域も、次々に内部に繰り込まれてゆく可能性があります。<原子力ムラ>にとっての外部とはそういうものです。ならば逆に、その内部の中の内部は…と遡行してゆくと、それはまさしくムラの内奥深く厳かに隠された、原子力本部の聖なる神殿だったのです。
こうしてみてくると、<原子力ムラ>はいうなれば、原子力という共通の<神>、原子力推進という共通の<神話>のもとに、異なる利権に競り合う<神官>たちを垂直的に統合する、きわめて宗教的な共同体ということができます。そう、呪術を駆逐し宗教を否定してきたはずの科学技術は、今やその最先端に至って再び、擬似呪術的・擬似宗教的にこそ維持されるしかない地点に立ち至っていると言わねばなりません。最先端の宗教教団としての高度科学技術国家・・・その教団の司祭たる<原子力ムラ>の専門家エリートたち・・・。
原子力の推進にあたって、安全神話、平和利用神話、安価神話、無資源国神話、核燃料サイクル神話、クリーン神話、安定供給神話(原発止めると電気が足りないやら、いきなり原始時代に逆戻りするやらの事実無根の神話)、etc.etc.・・・と次々に新たな神話が生み落とされねばならなかったのも、このためではないでしょうか。
いやもっといえば、「原子力」という語自体がすでに1つの神話でした。同一の原語”atomic energy”を「核エネルギー」でなく「原子力」と訳し分けて、あたかも「核」兵器や「核」爆弾とは別種の世界であるかのような印象操作を、この訳語に忍び込ませながら、涼しい顔して微笑んできたわけですから。
まして「平和利用」となれば、本当はただ端的に「核の民事利用」と言い直すべきもので、「平和」とは全く無縁な単なる神話にすぎないことは、スリーマイル島事故・チェルノブイリ事故でもとっくに明らかになっていたことですが、3・11原発震災以降、もう誰の目にも疑いないことでしょう。
前回みたような、本当は正しくないかもしれない情報が「真実」となり、本当は正しいかもしれない情報が「デマ」となりかねない基本構造は、高度科学技術国家のこの擬似宗教性にこそあったというべきでしょう。
<つづく>










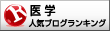


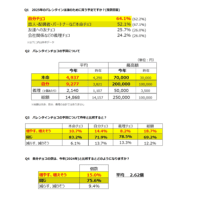
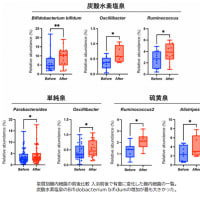


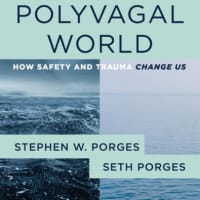
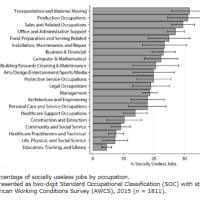
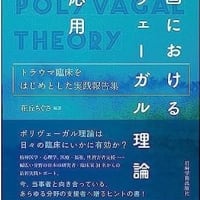
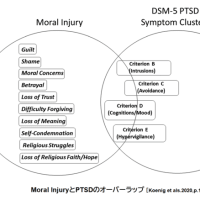
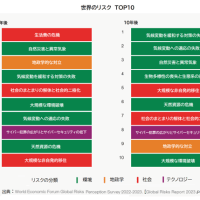






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます