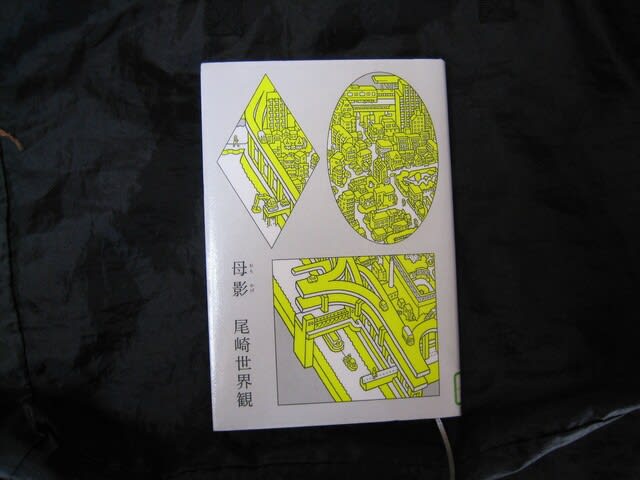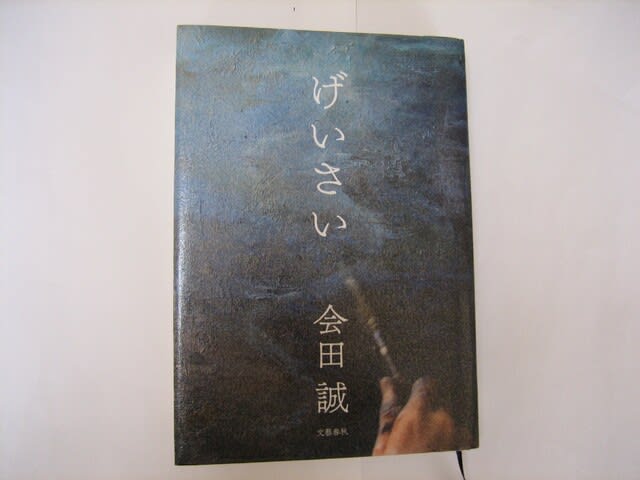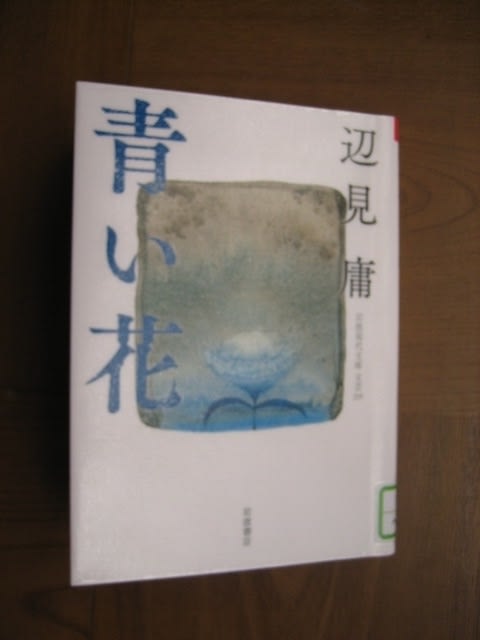村山由佳著『雪のなまえ』を読む。
これまで読んできた村山作品とは、あまりにも違うことに驚いた。
タイトルからして美しい。
小5の主人公・雪乃は、教室でいじめられている少女と話をした、
ただそれだけで今度は雪乃が標的にされる。
陰湿ないじめ、関わると自分が標的にされることを怖れて、
誰も雪乃に近づかなくなる。そして不登校。
この間に生じる両親と雪乃の苦悩や確執を丁寧に描いている。
そして編集者の母は東京に残り、雪乃と父は曾祖父母が住む
長野で暮らすことになる。
慣れない農業、都会とは違う人間関係。
こうした中で人の力を借りて、3人は自分の居場所を
見つけていく。
一日にしていじめの標的にされる怖さを、
この小説を読みながら思い出した。
私が小6の時に、町の有力者の娘と同じクラスだった。
父親は教育長も兼ねていて、先生も他の生徒たちも
彼女には一目置いていた。
当時、教室の椅子に腰かける時に、後ろからそっと椅子を引き
ずっこけさせる遊びが流行っていた。
後ろの席である彼女が、私にこれをしたのだ。
怪我はなかったものの、非常に危険な遊び、いや遊びでは
すまされないものだ。
彼女に抗議したところ、次の日からクラスの子たちは私を
避けるようになった。
そして誰も私に話しかけてくる子はいなくなった。
この状態はいつまで続いたのだろう。
記憶はそこで途切れているので、そんなに長くは
続かなかったと思う。
コロナ禍で大人も子どもも、いつ明けるとも知れない、
重く垂れこめた梅雨空の下で暮らしている。
こんな状態では、いじめが増えているかもしれない。
今、いじめを受けている子も、いじめている子も、
見て見ぬふりをしている子も、その子のお父さん、お母さん、
おじいちゃん、おばあちゃん、そして私とは関係ないと
思っている子にも、この本を読んで欲しいと思った。
この本の帯には次の言葉がある。
この言葉に癒される人が必ずいると思う。
つらいことから、どうして逃げちゃ いけないの?
自然から学んだ曾祖父の宝物のような言葉を吸収しながら、
雪乃は自分の尊厳を守りつつ居場所を見つけていく。
曾祖母の次の言葉に、涙がとまらなくなった。
だから、謝ることなんかちっともねえにょ。いいだかい?
雪ちゃんはね、ずいぶん大人になっただけど、まだ子どもだに。
そんでもって、子どもはね、大人っから心配してもらうのが
仕事だに。あんたの父やんだって母やんだって、きっと
そう思ってるだわ。な? (引用ここまで)
これまで読んできた村山作品とは、あまりにも違うことに驚いた。
タイトルからして美しい。
小5の主人公・雪乃は、教室でいじめられている少女と話をした、
ただそれだけで今度は雪乃が標的にされる。
陰湿ないじめ、関わると自分が標的にされることを怖れて、
誰も雪乃に近づかなくなる。そして不登校。
この間に生じる両親と雪乃の苦悩や確執を丁寧に描いている。
そして編集者の母は東京に残り、雪乃と父は曾祖父母が住む
長野で暮らすことになる。
慣れない農業、都会とは違う人間関係。
こうした中で人の力を借りて、3人は自分の居場所を
見つけていく。
一日にしていじめの標的にされる怖さを、
この小説を読みながら思い出した。
私が小6の時に、町の有力者の娘と同じクラスだった。
父親は教育長も兼ねていて、先生も他の生徒たちも
彼女には一目置いていた。
当時、教室の椅子に腰かける時に、後ろからそっと椅子を引き
ずっこけさせる遊びが流行っていた。
後ろの席である彼女が、私にこれをしたのだ。
怪我はなかったものの、非常に危険な遊び、いや遊びでは
すまされないものだ。
彼女に抗議したところ、次の日からクラスの子たちは私を
避けるようになった。
そして誰も私に話しかけてくる子はいなくなった。
この状態はいつまで続いたのだろう。
記憶はそこで途切れているので、そんなに長くは
続かなかったと思う。
コロナ禍で大人も子どもも、いつ明けるとも知れない、
重く垂れこめた梅雨空の下で暮らしている。
こんな状態では、いじめが増えているかもしれない。
今、いじめを受けている子も、いじめている子も、
見て見ぬふりをしている子も、その子のお父さん、お母さん、
おじいちゃん、おばあちゃん、そして私とは関係ないと
思っている子にも、この本を読んで欲しいと思った。
この本の帯には次の言葉がある。
この言葉に癒される人が必ずいると思う。
つらいことから、どうして逃げちゃ いけないの?
自然から学んだ曾祖父の宝物のような言葉を吸収しながら、
雪乃は自分の尊厳を守りつつ居場所を見つけていく。
曾祖母の次の言葉に、涙がとまらなくなった。
だから、謝ることなんかちっともねえにょ。いいだかい?
雪ちゃんはね、ずいぶん大人になっただけど、まだ子どもだに。
そんでもって、子どもはね、大人っから心配してもらうのが
仕事だに。あんたの父やんだって母やんだって、きっと
そう思ってるだわ。な? (引用ここまで)