
仕事で出張に行くと、時間がある限り、食品スーパーに立ち寄ることにしています。それぞれの地域の農林水産物の特徴がわかって勉強になりますが、それよりも、興味深いのが、「だし」と「調味料」と「漬物」です。
「だし」は、地域性だけではなく、周辺のライフスタイルによって品揃えが左右されるものだと思いますが、昆布、削り節、いりこの陳列棚の店舗全体からの割合や、だしの棚のなかの割合が、地域によって違いがあって面白いものだと感じています。
「調味料」は、もっと面白く、地域による差が多い食材です。福井県大野市の食品スーパーで、お酢の一升瓶がエンド陳列しているのを見てとても驚きました。
「漬物」は、地域の食文化の伝統を示しているもので、特に葉物の漬物は在来の葉物を使っていたり、海の近くでは野菜と魚介類を合わせた漬物だったりと、一見全国どこでも同じような棚のなかに、個性豊かな商材が隠れています。
地域の商材に興味が集まり、今は「だし」ブームでしょうか。
コレド室町のにんべん日本橋本店「だし場」が端緒でしょうか、このコレド室町では、改装拡大後、奥井海生堂、茅乃舎と、うまみ文化が広がっています。
東京駅のグランスタ4期エリアで、茅乃舎が東京駅地下丸の内口の改札前に店舗をもち、その1で触れた大宮駅のアコメヤのレジ横には、「アコメヤの出汁」という小冊子が置いてあります。
うどんチェーン店に行ったとき、枕のようなだしパックでだしを取っているのをみて、驚いたこともあります。
その一方で・・・
食品スーパーに立ち寄った時、品揃えだけでなく、そこのお客様が何を買っているのかにも興味があります。
先日、首都圏の郊外都市で大手食品スーパーチェーンに立ち寄りました。カット野菜の品ぞろえのすごさに圧倒されて、すれ違うお客様が買うものをみていると、トマトとレタス以外のカット野菜ではない野菜を買われている方にほとんど出会うことが出来ませんでした。偶然かもしれませんが。
過日、経済産業省のミニ経済分析「平成28年小売業販売を振り返る」を見ていたら、ドラッグストアの商品別売上構成比の中で、もっとも多くを占めるものが食品、さらに、売り上げの増加にもっとも貢献したものが食品。
そのドラッグストアの店頭の食品は、アルコール類が多くそれが貢献しているのでしょうが。食事に関するものも無視できない。その商品は、ナショナルブランドの、さらに一般的なもの。
「だし文化」という「こと」商品と、簡便性と価格志向という「もの」商品が、同じ消費者の異なるニーズに対応しているのだとしたら。あるいは、全く異なる消費者を対象としているのだとしたら。
経営資源を持つ者は、高度な情報技術の活用などにより、半歩先を読むツールを沢山持っているのかもしれません。
けれども、持つ者であっても、持たざる者であっても、街角に立ち街角から見ること、見る視点を増やすためにより多くのものを直接見ることが大切だと思います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
写真は、群馬県の館林市にある日清製粉の製粉ミュージアムの庭園の写真です。菩提寺が館林にあり、昨年のお盆にお参りに行った帰りに立ち寄りました。昨年のブログにも書きましたが、頭が整理できないくらい、展示にショックを受けました。自らの経営資源を最大に生かして、最先端の情報を収集し、きちんとした仕組みを作って事業を行うすごさは圧巻でした。














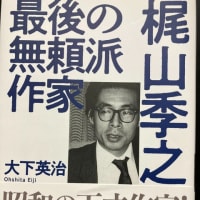





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます