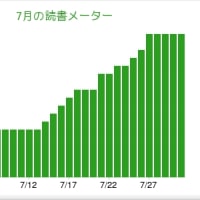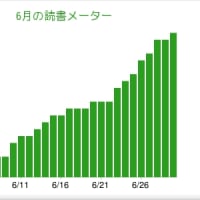引き続き、ドーバー付近の野原、狂人のリアと盲目のグロスターの会話。
リアの毒舌たっぷりの台詞をいくつか紹介したい。
'Down from the waist they are Centaurs, Though women all above. But to the girdle do the gods inherit, Beneath is all the fiend's. There's hell, there's darkness, there's the sulphurous pit; Burning, scalding, stench, consumption. Fie, fie, fie! pah,pah! Give me an ounce of civet, good apothecary, to sweeten my Imagination. There's money for thee.' (腰から下は怪獣ケンタウロス、 女であるのは上半身だけ、帯紐までが神の領域、 それより下はすべて悪魔どもの領地だ。 そこは地獄だ。暗闇だ、硫黄の燃える穴だ、火と燃え、煮えたぎり、 腐れ爛れて悪臭がすべてを飲み込む。ええい、堪らん、ぺっ!ぺっ! 麝香を一摘みくれ、頼む、薬屋、余の頭の中を清めてくれ、 さあ、金をやる)
どうしてここで、女性一般を呪う言葉出てくるのか、脈絡ははっきりとしないが、たぶん二人の姉娘のゴネリルとリーガンについていっているのだろうと思われる。
一方、女性のの下半身を地獄と見立てるのはシェークスピアのソネット129番などに通ずるものがある。シェークスピアのソネットは、彼自身の経験が反映されているといわれているので、シェークスピアは女性に、しかも性的な事柄で、よほど酷い目に遭ったのかも知れない。
一方、女性のの下半身を地獄と見立てるのはシェークスピアのソネット129番などに通ずるものがある。シェークスピアのソネットは、彼自身の経験が反映されているといわれているので、シェークスピアは女性に、しかも性的な事柄で、よほど酷い目に遭ったのかも知れない。
'What, art mad? A man may see how the world goes with no eyes' (何だと、おまえは気違いか? この世の成り行きを見るのに目など要らぬ、耳で見ろ)
眼を潰されたグロスターに対する台詞であるだけに、痛切に響く。
安易に目が見えてしまうだけに、人は簡単に騙されてしまう。グロスターもリア自身も、その愚かさにはまり、どん底の境遇に落ちてしまったのだ。
しかし、すべてを失いかけて、初めて彼らに見えて来たこともある。
二人とも、それぞれの立場で、自身の浅はかさを認識し、暗黒の境遇に自己認識の光が差し込むのだ。
そうした点で、ここは後半のターニングポイントなのだ。
安易に目が見えてしまうだけに、人は簡単に騙されてしまう。グロスターもリア自身も、その愚かさにはまり、どん底の境遇に落ちてしまったのだ。
しかし、すべてを失いかけて、初めて彼らに見えて来たこともある。
二人とも、それぞれの立場で、自身の浅はかさを認識し、暗黒の境遇に自己認識の光が差し込むのだ。
そうした点で、ここは後半のターニングポイントなのだ。
'Through tatter'd clothes small vices do appear; Robes and furr'd gowns hide all. Plate sin with gold, And the strong lance of justice hurtless breaks; Arm it in rags, a pygmy's straw does pierce it. None does offend, none- I say none! I'll able 'em.' (ボロボロの服を着ていればこそ、その破れから、些細な悪事も露見する。 お偉方が着るローブや毛皮のガウンは、すべてを隠してしまう。 罪を金の鎧で覆えば、どんな鋭い正義の槍も折れてしまい、中まで傷つくことがない。 それがボロであってみろ、小人の藁しべだって見事に一刺しだ。 この世に罪人はおらぬ。一人おらぬ、一人もな。余が保障する)
リアは、権力を持った者の横暴に繰り返し触れている。
この台詞はその締めくくりで、権威の象徴である衣服を身にまとっているだけで、権力者は大きな罪からさえ逃れることができる。反対に、ボロをまとった貧乏人は、どんなに些細な罪でも暴かれてしまう。
かつて権力者の頂点に立っていたリアが、ここで弱い者の視点から世の不正を権威というものの醜い姿を暴いているのだ。
しかし、最後には、「この世に罪人などいない」という許しの言葉である。シェークスピアは、後期の作品の中で、繰り返し「許しと和解のテーマ」を取り上げていて、『リア王』でも、すべてを失ったリアが悟った真理の一つが、「人を裁くな」という聖書にある教え、許すことの大切さであったのだ。
この台詞はその締めくくりで、権威の象徴である衣服を身にまとっているだけで、権力者は大きな罪からさえ逃れることができる。反対に、ボロをまとった貧乏人は、どんなに些細な罪でも暴かれてしまう。
かつて権力者の頂点に立っていたリアが、ここで弱い者の視点から世の不正を権威というものの醜い姿を暴いているのだ。
しかし、最後には、「この世に罪人などいない」という許しの言葉である。シェークスピアは、後期の作品の中で、繰り返し「許しと和解のテーマ」を取り上げていて、『リア王』でも、すべてを失ったリアが悟った真理の一つが、「人を裁くな」という聖書にある教え、許すことの大切さであったのだ。
グロスターとエドガーは、狂気に取り付かれたリアに涙を流し、そこへ紳士が数名の従者を伴って登場する。
彼はコーディリアがリアを探していることを告るが、リアは、それが追手であると思い込み、逃げ出し、その後を従者たちが追っていく。
彼はコーディリアがリアを探していることを告るが、リアは、それが追手であると思い込み、逃げ出し、その後を従者たちが追っていく。
そして、この場にオズワルドが現れて、賞金のかかっているグロスターを殺そうと襲い掛かるが、逆にエドガーによって討ち殺されてしまう。そして、死に際に、ゴネリルからエドマンドに渡すようにと託されていた手紙を差し出した。
それはエドマンドに、彼女が、夫のオールバニーを殺して彼女と夫婦になろうともちかける手紙であった。エドガーはその手紙の内容をオールバニーに知らせて、彼の眼を事実に向かって開かせることにする。