部屋の温度3度、ベットから飛び出しパソコンが置いてある机に向かうにはストーブを点けたとしても部屋はなかなか暖まらない。
貨幣が持つ交換機能と保存機能、それらを現代までの人間の歴史の中で考えていくと、保存機能の中の一部である政府が発行する国債。それがどのような意味を持つのかということに突き当たる。
市中に紙幣だけを大量に印刷し、出したのでは、当然ここでは通貨発行益が発生していくが、大量に発行された紙幣は労働で作られた商品とのバランスから、紙幣量に応じて労働の価値を上げていく、つまり通貨価値がきり下がっていくことになる。それを人間は歴史の中から教訓としてインフレになることを経験してきた。
そこで考え出されたのは交換機能と保存機能を分離させることが、紙幣を大量に発行してもインフレを避けることができるという道を探り出した。それが交換機能と保存機能の分離である、政府発行の国債ということになる。
国債は通貨(現在では紙幣だが)とは違い即交換機能を持たないゆえ、大量に発行しても市中に出回る通貨は量を抑えられることになる。国債をお金として使うには国債市場を通して市中に流通している通貨に変えなくてはならない。それは国債売買市場を通して変えることになる。
国債を現在流通している通貨に換えるには、売る人間と買う人間が同数にならなくては通貨に換えることはできない。売りが強ければ当然額面割れを起こし、その分金利が上げることになる、逆に金利が目当てで国債を持っていたいという人が多くなれば額面は上がり金利が低くなる。
そのことによって、より多くの量の通貨を発行させても、インフレを起こさず保存できる道を考え出した。
国債を購入できるのはお金にゆとりのある人でしかない。つまり国債発行残高が膨れあがるということは庶民のお金がそこにあるのではなく、一部の生活にゆとりのある人のお金がそれを購入しているのである。
それは人間の欲望の、多くの量のお金を持っていたいという気持ちのなにものでも無い。

上記写真は中国旅行時の京劇鑑賞時のお茶のもてなし。
貨幣が持つ交換機能と保存機能、それらを現代までの人間の歴史の中で考えていくと、保存機能の中の一部である政府が発行する国債。それがどのような意味を持つのかということに突き当たる。
市中に紙幣だけを大量に印刷し、出したのでは、当然ここでは通貨発行益が発生していくが、大量に発行された紙幣は労働で作られた商品とのバランスから、紙幣量に応じて労働の価値を上げていく、つまり通貨価値がきり下がっていくことになる。それを人間は歴史の中から教訓としてインフレになることを経験してきた。
そこで考え出されたのは交換機能と保存機能を分離させることが、紙幣を大量に発行してもインフレを避けることができるという道を探り出した。それが交換機能と保存機能の分離である、政府発行の国債ということになる。
国債は通貨(現在では紙幣だが)とは違い即交換機能を持たないゆえ、大量に発行しても市中に出回る通貨は量を抑えられることになる。国債をお金として使うには国債市場を通して市中に流通している通貨に変えなくてはならない。それは国債売買市場を通して変えることになる。
国債を現在流通している通貨に換えるには、売る人間と買う人間が同数にならなくては通貨に換えることはできない。売りが強ければ当然額面割れを起こし、その分金利が上げることになる、逆に金利が目当てで国債を持っていたいという人が多くなれば額面は上がり金利が低くなる。
そのことによって、より多くの量の通貨を発行させても、インフレを起こさず保存できる道を考え出した。
国債を購入できるのはお金にゆとりのある人でしかない。つまり国債発行残高が膨れあがるということは庶民のお金がそこにあるのではなく、一部の生活にゆとりのある人のお金がそれを購入しているのである。
それは人間の欲望の、多くの量のお金を持っていたいという気持ちのなにものでも無い。

上記写真は中国旅行時の京劇鑑賞時のお茶のもてなし。










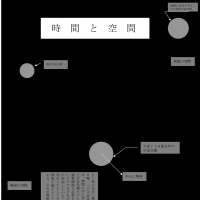
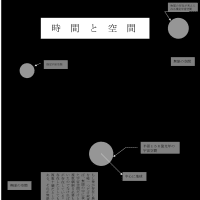



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます