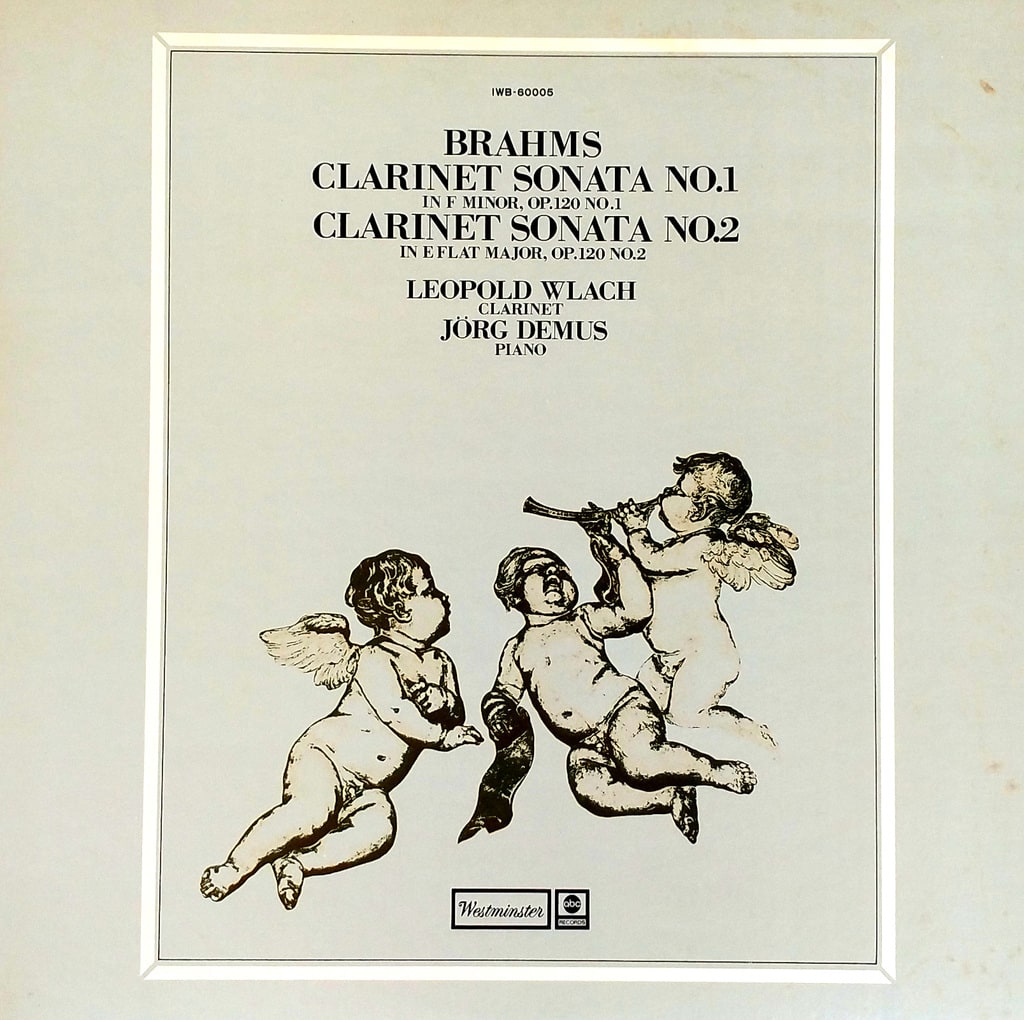ブラームス:弦楽五重奏曲第1番/第2番
弦楽五重奏:ブタペスト弦楽四重奏団+第2ヴィオラ:ワルター・トランプラー
ヨーゼフ・ロイスマン(第1ヴァイオリン)
アレクサンダー・シュナイダー(第2ヴァイオリン)
ボリス・クロイト(第1ヴィオラ)
ワルター・トランプラー(第2ヴィオラ)
ミッシャ・シュナイダー(チェロ)
録音:1963年11月14日~15日(第1番)/1963年11月21日、26日(第2番)、アメリカ、ニューヨーク
LP:CBS/SONY SOCL 1138
ブラームス:弦楽五重奏曲第1番は1882年に、 そして弦楽五重奏曲第2番は1890年に、それぞれ完成している。第1番は、如何にもブラームスの作品らしく、緻密で内向的な性格の曲。地味ではあるが完成度の高さでは、ブラームスの室内楽曲の中でも屈指の作品とも言える。どちらかというと一般向けの曲というよりは、プロ好みの室内楽曲。一方、第2番は、作品全体にワルツの主題が流れ、終末部にはロマの音楽が展開されるなど、ブラームスの室内楽としては、明るく陽気な作品となっており、耳に心地良く、楽しい作品。どことなく弦楽六重奏曲第1番と雰囲気が似かよっている。ブラームスは、この曲を書く直前にイタリアに旅しており、その影響を指摘する向きもある。さらにドイツ風のユーモア、スラブ風のメランコリー、それにハンガリー風の誇らしげな雰囲気などを加え合わせ、これら4つの性格が巧みに融合されているところが、この曲の魅力の源泉とも指摘されている。これら2曲を演奏しているのが、20世紀を代表する伝説のカルテットであるブダペスト弦楽四重奏団。1917年にブダペスト歌劇場管弦楽団のメンバーによって結成され、メンバーの変遷を経ながら1967年2月まで活動した。1938年からアメリカに定着して活動し、最終的なメンバーは全員がロシア人。伝統的なロマン主義的を避け、新即物主義的な解釈を行い、さらに、各声部のバランスを取ったことなどから、現代の弦楽四重奏演奏のスタイルに大きな影響を与えたカルテットと言われている。1940年から長年にわたりアメリカ合衆国の議会図書館つきの弦楽四重奏団としても活躍したが、ストラディヴァリウスを演奏に使用した。そして1962年以降の後任がジュリアード弦楽四重奏団である。このLPレコードで共演の第2ヴィオラ担当のワルター・トランプラー(1915年―1997年)は、ドイツ出身の名ヴィオラ奏者で、1939年以降、アメリカにわたり演奏活動を行った。このLPレコードでの演奏内容は、第1番については、ブラームス特有の内省的で緻密な曲想に合わせるかのように、実に求心的で濃密なロマンの香りを馥郁と漂わせた演奏に終始し、一分の隙のない名演を聴かせる。一方、第2番は、明るく、活動的な室内楽の楽しみを、リスナーと分け合うかのように、軽快に弾き進んで行き、ブラームスの別な側面を明らかにしてくれている。(LPC)