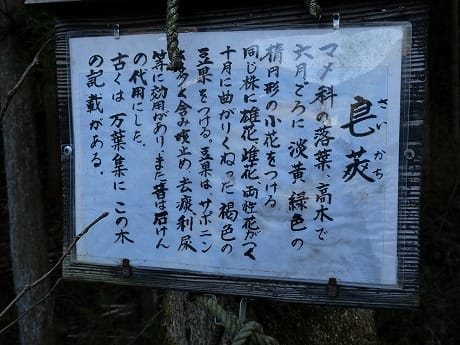桜井にいったん戻ったけれど
この日どうしても行きたかった場所が~~
桜井でもうこの時刻なのに・・
十数年来こころに暖め続けて来た磐余(いわれ)の地に立つその日だと。
悲劇の姉弟
この記事はずっと以前に載せてあるので
ここでは訪ねたその歌碑を載せておきたいと思う。
日が落ちた見知らぬ土地の道はただただ長く、
方向は分かっても歩いている道が果して合っているのか不安。
まだまだ遠そうな最初の地図標識
先が見えて来た二つ目の地図
二上山が右手奥のグランドの向こうに見える
急がなくては、暗くなってしまうと・・・気ばかりが焦る。。。
何人もの方にお聞きし、その都度詳しく教えていただけてありがたかった。
ナズナの花咲く畑にいたご婦人
ランニングしていた高校生の男子お二人・・・など幾たりも。
この通りを進んだ辺りだろうか。

こんな風景・・・好きだなぁ~ やっぱり奈良っていいネ♪

標が~




何とか暗くなる前にたどり着くことが出来た。
春日神社

ホッっと一息などはあとで。 めざす歌碑をさがさなくちゃ!!
大津皇子のお屋敷があった辺りと云われる吉備池。
本当の磐余の池はもっと西だったのではないかと本には記されている。
それでも時代を万葉に戻す場所として私には充分だった。

大津皇子の辞世は鴨だけれど・・・ここにいたのは鷺だった。


池に沿い左側へ進んでみたけど・・・歌碑らしきものなど見えない・・・
さまよった時は元にもどる これは
山に限ったことではないだろう、と 戻って見まわすと
右手の草叢に黒いものが見える。
はたせるかな。
行ってみると久恋のその歌碑であった。
確かに読める 大津皇子のみうた と。
長く長く願い続け、やっとたどり着けた場所。
この日たどった道のりも遠く感じた。
歌を手でなぞってみた。
「 もゝづたふ磐余の池に鳴く鴨を今日のみ見てや雲かくりなむ 」

そして更に見渡すと
皇子の歌碑の向いている方向の先にも歌碑らしきものが見える。
近づいてみると
二上山を背に建つ大伯皇女の歌碑であった。

「うつそみの人なるわれや明日よりは二上山をいろせとわがみむ」
歴史の真相はわからないが、
もし謀反の罪が企てられたものだとしたら悲しい。
そんな出来事がこの地であったという事、語り継がれて欲しいと願う。
妃の山辺皇女は髪を振り乱して素足で後を追い殉死したという。
吉備池は暮れて来て、空も赤く染まっていた。
このような夕べであったのだろうか・・・


薄暗くなったそこを去り、もう一基の歌碑をさがす。
先ほど寄った神社かもしれない・・・
あゝ、やっぱり。見落としていたのだった。
注意力が欠けている・・・

『臨終一絶』 懐風藻に収められている漢詩である。
検索してみたら詳しく解説してくださっているサイトが見つかったので
漢詩はここでは省いた。
漢詩の横には大伯皇女のみ歌も添えられていた。
「神風の伊勢の国にもあらましをなにしか来けむ君もあらなくに」

謀反の罪と言う事で死を賜ったった皇子は
まだ二十四歳であった。
伊勢の斎宮から戻った大伯皇女は四十歳で亡くなったとあるが
吉隠(よなばり)にお寺を建て、弟皇子の菩提を弔う半生であったという。
この日どうしても行きたかった場所が~~
桜井でもうこの時刻なのに・・

十数年来こころに暖め続けて来た磐余(いわれ)の地に立つその日だと。
悲劇の姉弟
この記事はずっと以前に載せてあるので
ここでは訪ねたその歌碑を載せておきたいと思う。
日が落ちた見知らぬ土地の道はただただ長く、
方向は分かっても歩いている道が果して合っているのか不安。
まだまだ遠そうな最初の地図標識

先が見えて来た二つ目の地図

二上山が右手奥のグランドの向こうに見える

急がなくては、暗くなってしまうと・・・気ばかりが焦る。。。
何人もの方にお聞きし、その都度詳しく教えていただけてありがたかった。
ナズナの花咲く畑にいたご婦人

ランニングしていた高校生の男子お二人・・・など幾たりも。
この通りを進んだ辺りだろうか。

こんな風景・・・好きだなぁ~ やっぱり奈良っていいネ♪

標が~





何とか暗くなる前にたどり着くことが出来た。
春日神社

ホッっと一息などはあとで。 めざす歌碑をさがさなくちゃ!!
大津皇子のお屋敷があった辺りと云われる吉備池。
本当の磐余の池はもっと西だったのではないかと本には記されている。
それでも時代を万葉に戻す場所として私には充分だった。

大津皇子の辞世は鴨だけれど・・・ここにいたのは鷺だった。


池に沿い左側へ進んでみたけど・・・歌碑らしきものなど見えない・・・
さまよった時は元にもどる これは
山に限ったことではないだろう、と 戻って見まわすと
右手の草叢に黒いものが見える。
はたせるかな。
行ってみると久恋のその歌碑であった。
確かに読める 大津皇子のみうた と。
長く長く願い続け、やっとたどり着けた場所。
この日たどった道のりも遠く感じた。
歌を手でなぞってみた。
「 もゝづたふ磐余の池に鳴く鴨を今日のみ見てや雲かくりなむ 」

そして更に見渡すと
皇子の歌碑の向いている方向の先にも歌碑らしきものが見える。
近づいてみると
二上山を背に建つ大伯皇女の歌碑であった。


「うつそみの人なるわれや明日よりは二上山をいろせとわがみむ」
歴史の真相はわからないが、
もし謀反の罪が企てられたものだとしたら悲しい。
そんな出来事がこの地であったという事、語り継がれて欲しいと願う。
妃の山辺皇女は髪を振り乱して素足で後を追い殉死したという。
吉備池は暮れて来て、空も赤く染まっていた。
このような夕べであったのだろうか・・・


薄暗くなったそこを去り、もう一基の歌碑をさがす。
先ほど寄った神社かもしれない・・・
あゝ、やっぱり。見落としていたのだった。
注意力が欠けている・・・

『臨終一絶』 懐風藻に収められている漢詩である。
検索してみたら詳しく解説してくださっているサイトが見つかったので
漢詩はここでは省いた。
漢詩の横には大伯皇女のみ歌も添えられていた。
「神風の伊勢の国にもあらましをなにしか来けむ君もあらなくに」

謀反の罪と言う事で死を賜ったった皇子は
まだ二十四歳であった。
伊勢の斎宮から戻った大伯皇女は四十歳で亡くなったとあるが
吉隠(よなばり)にお寺を建て、弟皇子の菩提を弔う半生であったという。