消費税は廃止!!消費税収の約25%が輸出戻し税の還付金と残りの73%が大企業減税の穴埋めに使用されている!!

輸出取引における消費税還付金についてわかりやすく解説します
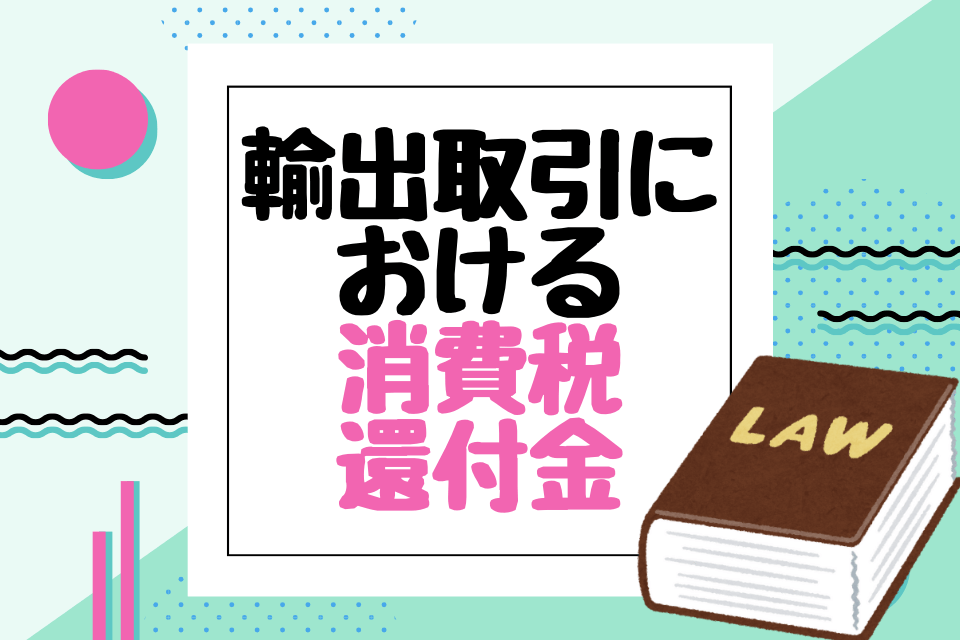
国内での商品取引では、消費税が発生します。
ただし、輸出取引では消費税が免除され、還付金として還付されるケースがあります。
とはいえ、すべての輸出取引が消費税還付金の対象ではありません。
輸出取引における消費税還付金を受けるためには、一定の条件を満たし、申告することが必要です。
この記事では、輸出取引における消費税還付金についてわかりやすく解説します。
輸出取引における消費税の還付について

なぜ、輸出取引においては、消費税が還付されることがあるのでしょうか。
以下では、輸出取引における消費税の還付について解説します。
輸出取引における消費税の還付とはどういう意味ですか?
輸出取引における消費税の還付とは、輸出取引の事業者が仕入や経費として支払った消費税の還付を受けることです。
国税庁のHPでは、以下のような記載があります。
| 事業者が国内で商品などを販売する場合には、 原則として消費税がかかります。 しかし、販売が輸出取引に当たる場合には、 消費税が免除されます。 これは、内国消費税である消費税は 外国で消費されるものには課税しないという考えに基づくものです。 引用:国税庁「No.6551 輸出取引の免税」 |
このことから、輸出取引は『国外で商品などを販売する場合』に該当するため、消費税の課税対象とはならず、還付されることがあります。
輸出取引における消費税の取り扱い
では、輸出取引において消費税はどのように取り扱われているのでしょうか。
以下では、輸出取引における消費税の取り扱いについて詳しく解説します。
輸出する商品は消費税が免税となる
原則として、消費税は『国内取引で課せられる税金』です。
そのため、輸出取引では、消費税が免除されるものとなります。
たとえば、輸出取引で500万円の売上があった場合でも、
消費税は免税されるため、0円ですみます。
輸出のために仕入れた商品の消費税は還付される
輸出のために仕入れた商品は、海外で取引されるものです。
そのため、消費税の課税対象とはなりません。
この還付は、仕入れや経費として消費税を支払った場合も、還付されます。
たとえば、仕入れで300万円がかかっていた場合、以下のように処理されます。
- 国内での取引・販売:30万円の消費税が課される
- 海外における輸出取引:消費税の課税対象外、支払った30万円が還付対象になる
輸出にかかる消費税の還付を受ける条件
「輸出取引なら消費税が戻ってくるなんて、すごくお得!」と感じる方もいると思いますが、注意が必要です。
この輸出取引における消費税の還付は、無条件で発生するわけではありません。
あくまで、一定の条件を満たすことで、初めて還付が受けられるものとなります。
以下では、輸出にかかる消費税の還付を受けるための条件について詳しく解説します。
まずは、どのような状況であれば『免税』されるのか、その条件を確認していきましょう。
消費税が免税となる条件
ここでは、還付される前に、そもそも『消費税が免税される』ことになる条件から確認しましょう。
課税事業者が以下に該当する輸出取引などを行った場合は、消費税が免除となります。
- 国内からの輸出として行われる資産の譲渡または貸付け
- 国内と国外との間の通信または郵便もしくは信書便
- 非居住者に対する鉱業権、工業所有権、著作権、営業権などの無体財産権の譲渡または貸付け
- 非居住者に対する役務の提供
※非居住者:本邦内に住所又は居所を有しない自然人及び本邦内に主たる事務所を有しない法人(外国為替及び外国貿易法第6条1項6号)
参照:国税庁「No.6551 輸出取引の免税」
消費税の還付を受けるための条件
続いて、輸出にかかる消費税の還付を受けるための条件は、以下の2つです。
- 課税事業者による輸出取引であること
- 輸出取引である証明ができること
詳しくご紹介していきます。
1.課税事業者による輸出取引であること
まず1つ目の条件として、輸出にかかる消費税の還付は、課税事業者でないと受けられません。
そもそも、消費税を支払っていない業者は、当然ですが還付の対象とはなりません。
そのため、以下に該当する場合は、事業者を変更しない限り、輸出にかかる消費税の還付を受けられません。
- 免税事業者
- 新規設立法人(資本金1,000万円以下)
- 新規個人事業主
- 簡易課税制度を選択している事業者
変更には、以下の届出が必要です。
| 事業者分類 | 届出書 | 注意事項 |
|---|---|---|
| 簡易課税制度を 選択している事業者 |
消費税簡易課税制度 選択不適用届出書 |
簡易課税2年継続後に変更可能なので、 期間が決まっている方は注意 |
| 免税事業者・新規設立法人 (資本金 1,000万円以下) |
消費税課税事業者 選択届出書 |
ー |
2.輸出取引の証明ができること
続いて2つ目の条件として、輸出にかかる消費税の還付を受けるためには、該当する取引が輸出取引などであることを証明できないといけません。
さらに、証明するための帳簿や書類は、納税地などに7年間保存する必要があります。
輸出取引があることを証明するための帳簿や書類は、以下のようなものが該当します。
【申請方法】輸出還付金はどうやってもらうの?

輸出における消費税の還付金を受け取るためには、必要書類を用意して、税務署にきちんと申告する必要があります。
以下では、輸出における消費税の還付金を受け取るためにはどうすればよいか、申告の流れや必要書類について解説します。
申告の流れ
先ほどお伝えした通り、輸出における消費税の還付金は、消費税課税対象者でないと受けられません。
消費税課税事業者となるためには、以下のいずれかの条件を満たしていることが必要です。
- 課税売上高が1,000万円を超えた事業者
- 資本金が1,000万円以上の事業者
- 消費税課税事業者選択届出書を提出している事業者
そして、申告の流れは事業者ごとに変わってきます。
以下では、3つに分けて解説します。
| 消費税課税法人事業者 | 課税期間の末日の翌日から2カ月以内に、 必要書類を所轄税務署長へ提出します。 |
| 消費税課税個人事業主 | 課税期間の翌年3月末日までに、 必要書類を所轄税務署長へ提出します。 |
| 輸出取引と国内取引を 併営している場合 |
消費税の納付と還付が同時に発生します。 |
あくまで還付税額と納税税額が相殺される仕組みなので、
- 還付税額が上回った場合→還付が受けられる
- 還付税額が下回った場合→追加で消費税を納める
となります。
申告に必要な書類
申告に必要な書類は、法人と個人事業主で異なります。
| 消費税課税法人事業者 | ・課税期間分の消費税および地方消費税の確定申告書 ・仕入控除税額に関する明細書(法人用) ・付表2 課税売上割合 ・控除対象仕入税額等の計算書 |
| 消費税課税個人事業主 | ・課税期間分の消費税および地方消費税の確定申告書 ・付表2 課税売上割合 ・控除対象仕入税額等の計算書 |
申告書の書類などは、申告時期前になると税務署から送付されます。
そして、申告は書面で提出するだけでなく、電子納税申告システム「e-Tax」を利用できます。
還付金を受け取った後の経理処理

輸出における消費税の還付金を受け取った後は、社内においてはどのように経理処理を行えばよいでしょうか。
以下では、還付金を受け取った後の経理処理の方法について解説します。
自社の経理方式により仕訳方法は異なる
消費税の還付金の経理処理は、大きく2種類あります。
- 税抜経理方式
- 税込経理方式
自社がどちらの経理方式を採用しているかによって、仕訳方法も変わります。
また、記載する勘定科目においても、どの勘定科目を選択するかは、会社の経理方式ごとに異なるため注意が必要です。
それぞれの経理方式の例を使って詳しく解説しますので、該当する方をご確認ください。
税抜経理方式
税抜経理方式を採用している場合の経理処理例は、以下のとおりです。
<決算時>
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 仮受消費税 | ◯円 | 仮払消費税 | ◯円 |
| 未収消費税 | ◯円 | 雑収入 | ◯円 |
- 仮受消費税:課税売上に対する消費税
- 仮払消費税:課税仕入れに対する消費税
- 未収消費税:還付金額が分かっている場合には、未収消費税として計上
- 雑収入:確定申告書を作成して計算された実際の還付金の額と、仮受消費税と仮払消費税の差額に端数処理が発生し一致しない場合には、雑収入として計上
<入金時>
| 借型 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | ◯円 | 未収消費税 | ◯円 |
還付金が入金されたら、未収消費税を減らして「普通預金」に振り替えます。
税込経理方式
税込経理方式を採用している場合の経理処理例は、以下のとおりです。
<決算時>
| 借型 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 未収消費税 | ◯円 | 雑収入 | ◯円 |
税込経理方式を採用した場合、仮受消費税の金額は収入金額または収益の額に含まれます。
また、仮払消費税の金額は、仕入れや経費などの金額に含まれます。
そのため、還付を受ける消費税については「雑収入」などにして計上するのが税抜経理方式との大きな違いです。
<入金時>
| 借型 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | ◯円 | 未収消費税 | ◯円 |
還付金が入金されたら、未収消費税を減らして「普通預金」に振り替えるのは税抜経理方式と同様です。
還付金の金額を確認する
最後に、還付金の金額を確認しましょう。
還付される金額が数万円程度の場合は問題ありません。
ただし、多額の消費税還付を申告した場合は、契約書などの提出を求められることがあります。
また、申告額が数百万円単位になると、税務署からの問い合わせや税務調査が入ることがあるといわれています。
申告のときに必要な書類はしっかりと保管しておきましょう。
還付金で不正を疑われた場合
万が一、還付金における不正を疑われてしまった場合、税務署による調査が行われます。
不正を疑われないためには
- 申告は正しい手順と書類を使って正確に行うこと
- 申告後は必ず還付金の勘定を帳簿に記載すること
- 証明するための帳簿や書類は、納税地などに7年間保存すること
「国税庁レポート2024」では、消費税不正還付について数ページを割いて取り上げています。消費税不正受還付事案の告発件数及び不正受還付額は、以下のとおりです。
| 年度 | 告発件数(件) | 不正受還付額(百万円) |
|---|---|---|
| 令和元年 | 11 | 323 |
| 令和2年 | 9 | 384 |
| 令和3年 | 9 | 434 |
| 令和4年 | 16 | 1,347 |
| 令和5年 | 16 | 454 |
※告発件数は、ほ脱犯との併合事案を含みます。また、不正受還付額は加算税を除き、未遂の還付額を含みます。
不正をしたとみなされると、追徴や事業停止、最悪の場合は廃業などになりかねません。
必ず正しい手順で還付を受け、その後の保管も行いましょう。
まとめ
この記事では、輸出取引における消費税還付金についてわかりやすく解説しました。
輸出取引は国内取引と異なり消費税の課税対象とはならず、還付されることがあります。
ただし、輸出取引における消費税の還付は、無条件で発生するわけではありません。一定の条件を満たすことで、初めて還付が受けられます。
そして、還付金を受け取るためには、必要書類を用意して申告する必要があります。
還付金の経理処理において、金額が大きくなると税務署からの問い合わせや税務調査が入ることがあるといわれているため、申告のときに必要な書類はしっかりと保管しておきましょう。
輸出取引における消費税還付金を受けたい方は、この記事を参考に還付金の手続きを検討してみてください。
輸出ビジネスを始めたい方へ
輸出取引における消費税還付金について、大きな恩恵を受けることが出来るビジネスの一つが輸出ビジネスです。
























