タイのお正月、ソンクラン祭りは「水掛け祭り」とも称され、本来の意味合いは「豊作のための雨乞い」の儀式の一つでもありました。
また 沢山の水を掛けられれば、掛けられた分だけその年に良いことがあるとも言い伝えられています。かつては、
金属の器に入れた水を道行く人の肩にコップで少しだけ掛けたり、昨日のpriusさんのコメントにあるように、
本来は、知人同士が声を掛け合ってから静かに少量の水を掛けるのが慣わしで、厳粛なものであったようです。
それが今では、時代と共に過激さを増して、水鉄砲やら、パウダーまで塗り合う等、意味不明なものとなってしまっています。
お目出度いお祭りですから、楽しむ人達が水を掛け合って喜ぶのは構いませんが、嫌がる人にまで悪ふざけするのはいけません。
ですからウィラサク観光スポーツ相は「ソンクラン祭りが優美かつ優雅な行事であることを再認識してもらいたい」と訴えています。
今年は例年と異なり、カオサン通りでは荷台に水の入ったタンクを置き、道行く人々に水を掛けまくる軽トラックの
乗り入れを大幅に制限したり、ソンクラン期間中、王宮前広場(サナムルアン)やチトラダ宮殿など王室関連施設の
周辺での走行は禁止したり、違反者には1000バーツ以下の罰金が科す、とも発表しています。
更に、水掛けでは清潔な水を使用すること、異性に意識的に触れないこと、ラジカセを大音響でかけないこと・・・等々の
協力を呼びかけています。また カオサン通りではパウダーの使用が禁止されるほか、露出度の激しい服装の人は
入場させない、とも宣言しています。
処で、雨の恵みと豊作を祈る水掛けの起源はいろいろあるようですが、神話上の蛇が「海上で水遊びをすると雨が降る」と
言う由来から、農民達も「耕作期に十分に雨が降りますように」と願い、人間同士で「水を掛けあい、歌い、踊って、遊んで」と、
大騒ぎするようになったそうです。華人が移住するずっと前からのお祭りで、タイだけでなくラオスやカンボジア、ミャンマーでも
行われており、如何に古くからのものであるか理解できます。
タイは、農業国ですが、農業と水はたいへん密接に関係していますので、昔から農家が水を大切にしながらの
祈りの儀式や祭りごとが、その他にも多くあったようです。
また ソンクラーンでは初日に仏像を洗う儀式と習慣がありますので、この時期になると、スーパーマーケットの入り口に、
水掛け用の仏像とお水が用意されています。そう言えば、エンポリアム デパートの入り口にも置かれていましたっけ。
仏像を洗った後、目上の人に対しての敬意を表すために、手のひらによい香りのする水を注ぎ、タオルや入浴に必要なものを
贈るという習慣もあるそうです。水を掛け合う、にも昔から深い意味がある訳です。仏像を洗うのと同じく、体をきれいに
する行為は、宗教的なものであり一日に何回ものシャワーを浴びるタイ人の習慣もよく理解できます。
それがいつの間にか「体をきれいにするお手伝い」と、かけ離れて相手構わず水を掛けることで、日頃の鬱憤を解消する
イベントに変わってしまった感があります。現代の若い人が中心で行うこの水掛けは、真夏の暑い時期も手伝って、
それはそれは、物凄い国をあげての単なる「水かけっこ」です。バンコクや観光都市では欧米人も加わって盛り上がります。
国全体のスケールで「水かけっこ」をやりますから、タイの4月の水道代は、きっと世界一になることでしょう。
タイの水掛け祭りに参加する際は、水を掛ける意味合いをよく理解して参加しましょう!
「タイでゴルフ友達になりましょ」 のホームページです

 タイ・ゴルフを何でもランキングで紹介する情報サイト
タイ・ゴルフを何でもランキングで紹介する情報サイト
また 沢山の水を掛けられれば、掛けられた分だけその年に良いことがあるとも言い伝えられています。かつては、
金属の器に入れた水を道行く人の肩にコップで少しだけ掛けたり、昨日のpriusさんのコメントにあるように、
本来は、知人同士が声を掛け合ってから静かに少量の水を掛けるのが慣わしで、厳粛なものであったようです。
それが今では、時代と共に過激さを増して、水鉄砲やら、パウダーまで塗り合う等、意味不明なものとなってしまっています。
お目出度いお祭りですから、楽しむ人達が水を掛け合って喜ぶのは構いませんが、嫌がる人にまで悪ふざけするのはいけません。
ですからウィラサク観光スポーツ相は「ソンクラン祭りが優美かつ優雅な行事であることを再認識してもらいたい」と訴えています。
今年は例年と異なり、カオサン通りでは荷台に水の入ったタンクを置き、道行く人々に水を掛けまくる軽トラックの
乗り入れを大幅に制限したり、ソンクラン期間中、王宮前広場(サナムルアン)やチトラダ宮殿など王室関連施設の
周辺での走行は禁止したり、違反者には1000バーツ以下の罰金が科す、とも発表しています。
更に、水掛けでは清潔な水を使用すること、異性に意識的に触れないこと、ラジカセを大音響でかけないこと・・・等々の
協力を呼びかけています。また カオサン通りではパウダーの使用が禁止されるほか、露出度の激しい服装の人は
入場させない、とも宣言しています。
処で、雨の恵みと豊作を祈る水掛けの起源はいろいろあるようですが、神話上の蛇が「海上で水遊びをすると雨が降る」と
言う由来から、農民達も「耕作期に十分に雨が降りますように」と願い、人間同士で「水を掛けあい、歌い、踊って、遊んで」と、
大騒ぎするようになったそうです。華人が移住するずっと前からのお祭りで、タイだけでなくラオスやカンボジア、ミャンマーでも
行われており、如何に古くからのものであるか理解できます。
タイは、農業国ですが、農業と水はたいへん密接に関係していますので、昔から農家が水を大切にしながらの
祈りの儀式や祭りごとが、その他にも多くあったようです。
また ソンクラーンでは初日に仏像を洗う儀式と習慣がありますので、この時期になると、スーパーマーケットの入り口に、
水掛け用の仏像とお水が用意されています。そう言えば、エンポリアム デパートの入り口にも置かれていましたっけ。
仏像を洗った後、目上の人に対しての敬意を表すために、手のひらによい香りのする水を注ぎ、タオルや入浴に必要なものを
贈るという習慣もあるそうです。水を掛け合う、にも昔から深い意味がある訳です。仏像を洗うのと同じく、体をきれいに
する行為は、宗教的なものであり一日に何回ものシャワーを浴びるタイ人の習慣もよく理解できます。
それがいつの間にか「体をきれいにするお手伝い」と、かけ離れて相手構わず水を掛けることで、日頃の鬱憤を解消する
イベントに変わってしまった感があります。現代の若い人が中心で行うこの水掛けは、真夏の暑い時期も手伝って、
それはそれは、物凄い国をあげての単なる「水かけっこ」です。バンコクや観光都市では欧米人も加わって盛り上がります。
国全体のスケールで「水かけっこ」をやりますから、タイの4月の水道代は、きっと世界一になることでしょう。
タイの水掛け祭りに参加する際は、水を掛ける意味合いをよく理解して参加しましょう!

「タイでゴルフ友達になりましょ」 のホームページです


 タイ・ゴルフを何でもランキングで紹介する情報サイト
タイ・ゴルフを何でもランキングで紹介する情報サイト










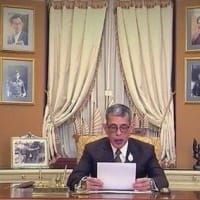

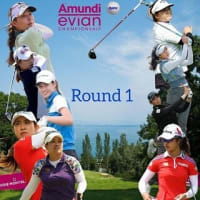



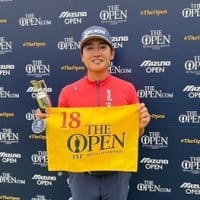


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます