村上春樹の新作「街とその不確かな壁」を先日読了したので、その感想。
感想だけど、ストーリーの概略も書きます。がっつりネタバレするので、まだ読んでない人は注意してください。
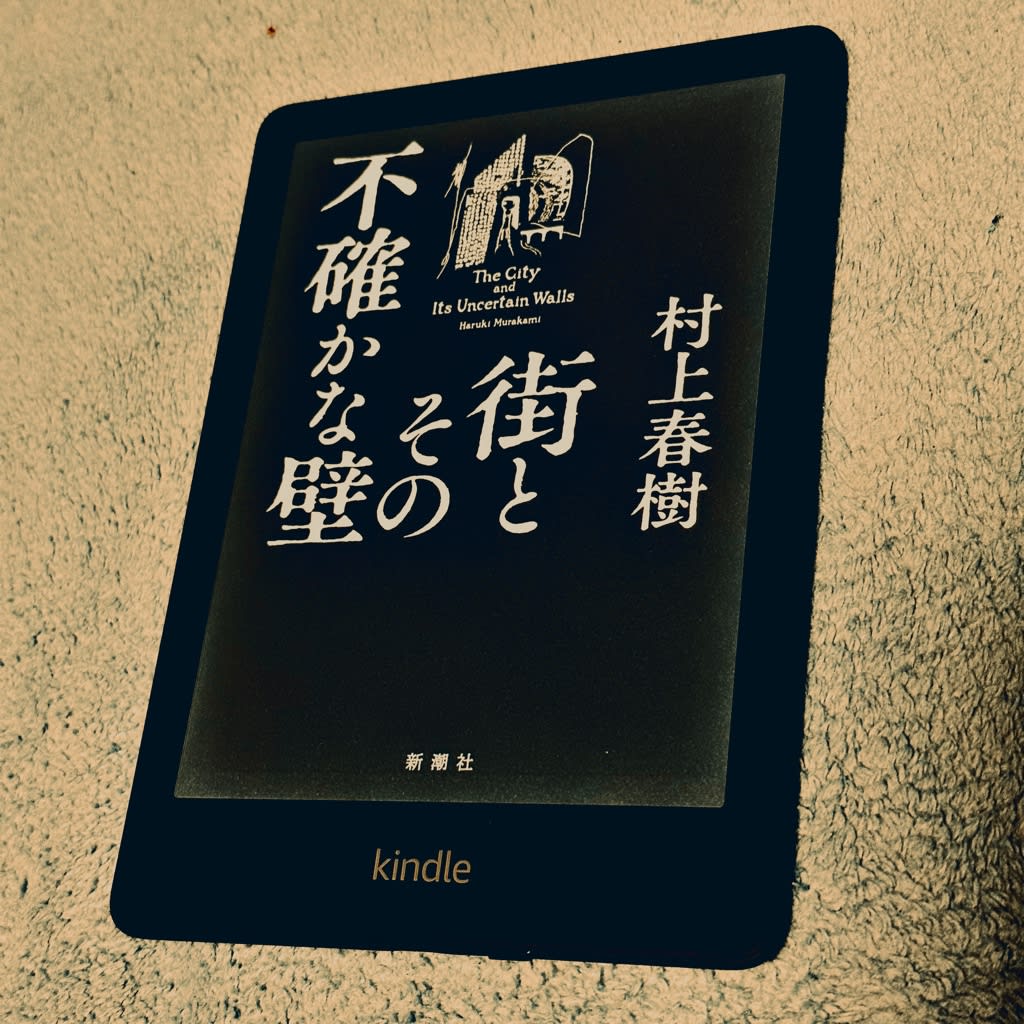
今回はKindle版にした。0時にダウンロードできて感動しようとかではなく、単行本だとデカくて重くて通勤電車で読みにくいから。
各所で語られていると思うが、本作の成り立ちについては、多少説明がいる。僕の体験順に書く。
世間一般やニワカはともかく、ファンにとっての村上春樹の最高傑作は「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」(1985年)だとされてきた。たぶん「海辺のカフカ」(2002年)が出るまでは。
「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」は、タイトルの通り「世界の終り」と「ハードボイルド・ワンダーランド」の2つの異なる物語が合体した作品である。高い壁に囲まれ、暗く静かな「世界の終り」という街で夢読みとなる「僕」のファンタジーと、脳の一部を外部記憶領域として機密情報を運ぶ「私」のスパイサスペンスが、章ごとに入れ換わりながら進行していく。
僕もこの作品が長編では最高傑作だと思っていて、特に「世界の終り」部分が好きだった。陰鬱な雰囲気の中に隠れている温もりとか、作り込まれた世界観とか、厳しそうだけど幸せもありそうな未来を予感させる結末とかが。「世界の終り」部分に影響を受けているというアニメ「灰羽連盟」も見た。

「世界の終り」の地図。結局本作に地図はついてなかった。
「世界の終わり」部分だけ何度か読み返すうちに、原型となった中編「街と、その不確かな壁」の存在を知った。雑誌に一度掲載されただけで書籍化されていない幻の作品。結末が「世界の終り」と違うらしい。出来がよくなくて書籍化していないとか。
僕はなんとかしてそれを読みたくて、ネット中を探し回って雑誌をスキャンした画像を手に入れた。昔の話なのでスキャンが粗く、文字の判別も難しいほどだったが、なんとか一度だけ読んだ。確かに完成度は高くないかも。
それから十数年後。4月13日の朝、新刊のニュース(夜中にハルキストたちが買うやつ)を知った。タイトルは「街とその不確かな壁」…だと…?!
そのタイトルだと買わざるを得ない。またあの街に行けるなら3000円は、まあ、払えるかな。というわけで、帰宅してからKindle版をポチった。
・・・・・
野球で言えば3回裏まで、現実世界の高校生「ぼく」と街の夢読み「私」の話が交互に進む。というか、私の回想がぼくの話である。ぼくは「きみ」に激しく恋をしている。きみは壁に囲まれた街のことを詳細に教えてくれる。
ある日突然きみの消息が分からなくなる。手紙の返事が来ない。電話も「現在使われておりません」状態。ぼくは一番大事な部分を失くしたまま生き、45歳で唐突に街に転移して、まだ若いきみ(私のことは知らない)と再会する。
「ノルウェイの森」じゃん。バイト先が中古レコード店だし。街はこんがらがった彼女の頭の中だろうか。彼女は空想の街に引きこもってしまったのだろうか。私は、ノルウェイの森の直子のように、おかしくなっちゃった彼女を救い出すために街に入るのか。
「世界の終り」の「僕」は若かった。20代半ばくらい。今回はおじさんだ。「おっさん版・世界の終り」か。これは面白いわ。感情移入しやすい。実らなかった激しい恋を抱えて生きていくのも共感できるし(何故かな)。
ところが、街の話は3回裏で終了。ちょっと早いけど、また戻ってくるのだろう。
最初の「街と、〜」は、影と一緒に街から脱出して終わる。影はその人の感情や魂を意味していると思われる。街では影を切り離さないといけない。
「世界の終り」での「僕」は、図書館の彼女を愛してしまう。感情を持ってしまった人が隔離される森で彼女と生きることを選び、影だけが街から脱出する。
今作「街と〜」は、影だけ脱出するが、残った私がどうなるかはとりあえず描かれずに第1部が終わる。ちなみに第3部まである。ということは目次で知って読んでいる。第3部が街再び編だろうか。
第2部は、また唐突に現実世界に戻った?私(45)の話。あの子に会える街に戻りたいけど、戻り方がわからない。勘に任せて会社を辞め、福島の山奥の町の図書館の館長になる。
この図書館は古い日本酒の醸造所を改造した趣のある建物で、僕は埼玉県小川町の図書館がモデルじゃないかと勝手に思っている。
前の館長の幽霊にアドバイスされながら、図書館を運営し、少しずつ街に戻るであろう雰囲気に近づいていく。前の館長の子易さんも、かつて深く愛した人を失っていた。図書館司書の添田さんがめちゃくちゃ有能。不自然なほど何でも知ってる。
添田さんは既婚者なので、この人とはくっつかないなと思っていたら、名もなきコーヒーショップの女性店主とくっつく。けど、この人は性的に不能だった。村上春樹の長編では滅多にないことだが、性行為のシーンがない。
イエローサブマリンのパーカーを着たサヴァン症候群の少年登場。超人的な記憶力で図書館の本を全部記憶する勢いで本を読む。この少年が消失して長い第2部福島編終了。
もうKindle表示で残り10%しかない。9回裏だ。第3部は予想通り街の話だが、ここの私は第2部の私の記憶がないので、おそらく第1部ラストで残った私だ。第2部の私は、第1部で溜まりに飛び込んで脱出した影だったのだ。
そこにイエローサブマリンの少年がやってきて、私と一体化する。夢読みとしての能力が強化され、「きみ」に評価されるが、街からの脱出を決意。脱出するためにロウソクを吹き消したところで物語は終了する。
・・・・・
深く愛した人、忘れられない人を精神の迷宮から救い出す「おっさん版・世界の終り」だと思っていた第1部では、このまま行ったらノーベル賞かもと思った。心の震えとかは迫真の描写だし、世界共通普遍的なテーマでもあるし。何より作者の書きたいことがいつになくわかりやすい。
だが、街の作り込みが甘いのが気になっていた。老人が「大佐」じゃない。発電所がない。心を捨てきれなかった人たちが暮らす森がない。寓話的童話的なイメージを強化する地図がない。この街は「世界の終り」ではなさそうだ。
第2部が長い。田舎暮らしの描写が上手くて臨場感あるが、生活様式はいつも通り。テレビを見ない。パソコンは持ってるけど好きじゃない。インターネットとGoogleとSNS(!)が出てくるが「私」には関係ない。休日には洗濯してアイロンかけて、簡単な料理(凡人からするとおしゃれな)を作ってラジオでクラシックを聴いて過ごす。いつものじゃん。
主人公の設定を変えればいいってもんじゃないけどさ。でもあまりにもいつもと同じじゃん。
「ぼく」が美しいと絶賛する「きみ」の描写も引っかかった。前髪パッツンでショートヘア。小柄で丸顔で目が大きくて鼻が小さい。ちびまる子ちゃんかな? 目の大きさはともかく。
添田さんは子易さんの過去を知りすぎてるとか、コーヒーショップの女性がいつもの「美人ではないが体つきがほっそりしていて感じが良い」だとか、唐突に奇妙な少年が出てきて、なんだかなあと思っているうちに第2部が終わって、ノーベル賞は無理だな今年もと思った。淡々とした話に小さな変化が生じて、何が起きるのかな?という興味が断続的にやってきて、グイグイ読ませる作品だとは思うけど。
僕がもし村上春樹をプロデュースできたら(=陽子夫人だったら)、あの「世界の終り」を長くした本格的な幻想小説を書かせる。世界観と設定をさらに詳細に詰めて、主人公と図書館の彼女はそのままで、他の登場人物を増やす。影と別れた後、彼女と放逐者の森に入って生きる。彼女が心を取り戻すのを手伝いながら。現実とのリンクは、付けてもつけなくてもいい。失われた大事なものを探す話にマイノリティーの問題とかも絡められて、ノーベル賞間違いなしだ。たぶん。というか、僕がそういう作品を読みたかった。















