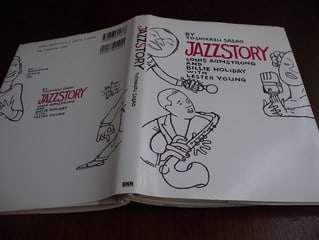今年の夏は梅雨明けの10日くらいが猛暑だったのだろう?休みの日は居間の横にある小部屋が避暑地になっている。日向薬師の参道に面して竹林があって、その隙間からここ数日、北東からの乾いた微風が高窓を通してそよそよと吹き込んでくる。夏に翳りが出始めていると思う瞬間だ。今朝は熱い煎茶を飲んでみたい気分になって朝食の冷麦・トマトサラダの後は鹿児島は知覧産の煎茶を南蛮手の急須に入れて呑んでみた。煎茶を体が欲しがるのもやはり秋の兆しなのかもしれない。

パブロ・カザルスといえばいわずと知れた20世紀を代表する最高のチェロ奏者だ。そのカザルスに秘書的に仕えていたホセ・マリア・コレドールが纏め上げたカザルスの回顧記が「カザルスとの対話」(白水社1962年刊 増補再版)で1950年代前半にこの本は発行されたらしい。旧盆にあたる来週は勤務先が一斉の休暇になる。24時間おきに当直仕事をするわけだが、その隙間に読む候補をこれに決める。この本はカザルスの本職話(音楽家自伝)は無論のこと、無類のユマニストだったカザルスが戦争や圧制・暴力のはびこる20世紀を音楽表現によってどのように処したかを豊かに証言した歴史書としても読めるから面白い。加えてピレネ山脈沿いのスペインの風光地誌も官能に溢れた述懐が感得できるという一挙両得が含まれている。
拾い読みをしていたら、後半のページでカザルスがオーディオについての面白い発言をしている箇所があった(257P)
この対話の時期は多分、戦後の10年以内だったのだろう?秘書のコレドールがレコードにパッケージされたカザルスの演奏を先生はどのように聴いているのか?と水を向けている。これはちょうどSPからLPへの移行時期と重なっていたと思われる発言だ。

カザルスの答えは「いや いつもではない。ときどきこれは私の音ではない、と思う。
私の考えでは、機械を通すことによって、芸術家の演奏の精気が失われるのだと思う。
そしてそうなることはどうにも致し方がないのかもしれない。」
これに対して秘書は「けれど録音技術の進歩は驚くべきものがあります。」とジャブを放つ。
これにも「そう考えるのは自由だが、私は三、四十年前の録音のほうがまだ好きだ。
音色の輝かしさは少ないが、もっと忠実だ。私が1937年から39年にかけて、一年以上も準備してから吹き込んだバッハの組曲のレコードが与えてくれるようなものを、長時間レコードで聴きたいものだね。ゆるい楽章が機械化によっていっそうよくなったか、また機械を通したパッセージが演奏者の活力と個性の特徴をさらに生かしているか、などが見られて興味深いだろう」
さらに「一般に録音された作品を聞くとき、私はレコードの回転を速くする方が好きだ。私のバッハの組曲の録音では、一音も一音半も高くして聞く必要を覚える。」とも付け加えている。

じつに興味深い会話で生音とオーディオ再生の超えられない溝についての経験と叡智に裏づけられた発言だ。この端的な会話以上にはその後、さらに60年を経た現在も、この問題の呪縛からは解放されていないことを痛感せざるをえない。そう思いながら、モノラルLP時代それも10インチ時代にカザルスに嘆かれている対象の一つでもあるベートーベンのイ長調ソナタにしばし耳を傾けてみることにした。

パブロ・カザルスといえばいわずと知れた20世紀を代表する最高のチェロ奏者だ。そのカザルスに秘書的に仕えていたホセ・マリア・コレドールが纏め上げたカザルスの回顧記が「カザルスとの対話」(白水社1962年刊 増補再版)で1950年代前半にこの本は発行されたらしい。旧盆にあたる来週は勤務先が一斉の休暇になる。24時間おきに当直仕事をするわけだが、その隙間に読む候補をこれに決める。この本はカザルスの本職話(音楽家自伝)は無論のこと、無類のユマニストだったカザルスが戦争や圧制・暴力のはびこる20世紀を音楽表現によってどのように処したかを豊かに証言した歴史書としても読めるから面白い。加えてピレネ山脈沿いのスペインの風光地誌も官能に溢れた述懐が感得できるという一挙両得が含まれている。
拾い読みをしていたら、後半のページでカザルスがオーディオについての面白い発言をしている箇所があった(257P)
この対話の時期は多分、戦後の10年以内だったのだろう?秘書のコレドールがレコードにパッケージされたカザルスの演奏を先生はどのように聴いているのか?と水を向けている。これはちょうどSPからLPへの移行時期と重なっていたと思われる発言だ。

カザルスの答えは「いや いつもではない。ときどきこれは私の音ではない、と思う。
私の考えでは、機械を通すことによって、芸術家の演奏の精気が失われるのだと思う。
そしてそうなることはどうにも致し方がないのかもしれない。」
これに対して秘書は「けれど録音技術の進歩は驚くべきものがあります。」とジャブを放つ。
これにも「そう考えるのは自由だが、私は三、四十年前の録音のほうがまだ好きだ。
音色の輝かしさは少ないが、もっと忠実だ。私が1937年から39年にかけて、一年以上も準備してから吹き込んだバッハの組曲のレコードが与えてくれるようなものを、長時間レコードで聴きたいものだね。ゆるい楽章が機械化によっていっそうよくなったか、また機械を通したパッセージが演奏者の活力と個性の特徴をさらに生かしているか、などが見られて興味深いだろう」
さらに「一般に録音された作品を聞くとき、私はレコードの回転を速くする方が好きだ。私のバッハの組曲の録音では、一音も一音半も高くして聞く必要を覚える。」とも付け加えている。

じつに興味深い会話で生音とオーディオ再生の超えられない溝についての経験と叡智に裏づけられた発言だ。この端的な会話以上にはその後、さらに60年を経た現在も、この問題の呪縛からは解放されていないことを痛感せざるをえない。そう思いながら、モノラルLP時代それも10インチ時代にカザルスに嘆かれている対象の一つでもあるベートーベンのイ長調ソナタにしばし耳を傾けてみることにした。