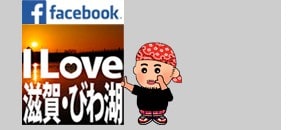炎のクリエイター 撮影 & 画像補正
このブログに使用の画像は、殆んどを「iPhone15 pro」で撮り「CANON Power Shot G7XⅡ」と「CANON一眼」などの撮影機器でフォローしています。画像に補正を施せば、とっておきの一枚を奇麗にできます。 ※画像の転載・転用は禁止させて頂きます。
 京都の蹴上インクラインは、明治中期から昭和の終戦直後まで、実際に稼働していた「びわ湖疏水」を利用した舟での運搬システムの一部分のことをいう。近江から京都まで荷を運んだ舟を、高低差がある滋賀へ引っ張り上げるシステムをインクライン(傾斜鉄道)と言うそうだ。時を超えて今は桜並木の観光スポットになっている。
京都の蹴上インクラインは、明治中期から昭和の終戦直後まで、実際に稼働していた「びわ湖疏水」を利用した舟での運搬システムの一部分のことをいう。近江から京都まで荷を運んだ舟を、高低差がある滋賀へ引っ張り上げるシステムをインクライン(傾斜鉄道)と言うそうだ。時を超えて今は桜並木の観光スポットになっている。
 京都の蹴上インクラインは、明治中期から昭和の終戦直後まで、実際に稼働していた「びわ湖疏水」を利用した舟での運搬システムの一部分のことをいう。近江から京都まで荷を運んだ舟を、高低差がある滋賀へ引っ張り上げるシステムをインクライン(傾斜鉄道)と言うそうだ。時を超えて今は桜並木の観光スポットになっている。
京都の蹴上インクラインは、明治中期から昭和の終戦直後まで、実際に稼働していた「びわ湖疏水」を利用した舟での運搬システムの一部分のことをいう。近江から京都まで荷を運んだ舟を、高低差がある滋賀へ引っ張り上げるシステムをインクライン(傾斜鉄道)と言うそうだ。時を超えて今は桜並木の観光スポットになっている。