
水産庁は、漁港を活用した地域振興をめざす海業の全国展開を推進するため、3日午後から農林水産省で第2回海業推進全国協議会(ウエブ併催)を開き、海業推進に向けた政策、講演、取組事例の報告を行って機運盛り上げを図った。

開会に当たり、庄子賢一農林水産大臣政務官が「漁港を活用した海業が各地でみられ、漁港や漁村は水産物をはじめ景観など大きな魅力あるポテンシャルをもつ。インバウンドを地方に波及させ、政府が進める地方創生2.0にも役割を果たし、地域が一致団結しさらなる発展的な取り組みを期待する」と述べ、海業のマスコットキャラクターを紹介した。

次いで、渡邉浩二計画・海業政策課長が漁村の人口減少や高齢化を背景にした海業推進の意義、根室市歯舞漁港など海業の取り組み事例、漁港漁場整備法の改正(漁港施設等活用事業制度など)、海業に関わる取り組みを説明した。その中で、海業振興関係予算は、海業振興支援事業として海業の立ち上げ支援(国)および体制構築(地元)、実施計画の策定を支援するほか、また、海業の施設整備は浜の活力再生・成長促進交付金の海業推進事業、水産業強化支援事業で対応する。海業支援パッケージとして各省庁にまたがる予算の目次を作成し、水産庁に相談的口(海業振興コンシェルジェ)を設置した。「海業の推進に取り組む地区」を募集し54地区を公表し、現在募集中の地区も3月に公表する予定。

このあと、基調講演では、工藤貴史東京海洋大学教授が「人口減少社会における海業推進の意義と課題」として従来からある海業と今日的な海業の違いを明らかにし、漁港の計画的活用、集積効果の発揮、漁港DX(デジタル技術)の課題を指摘した。
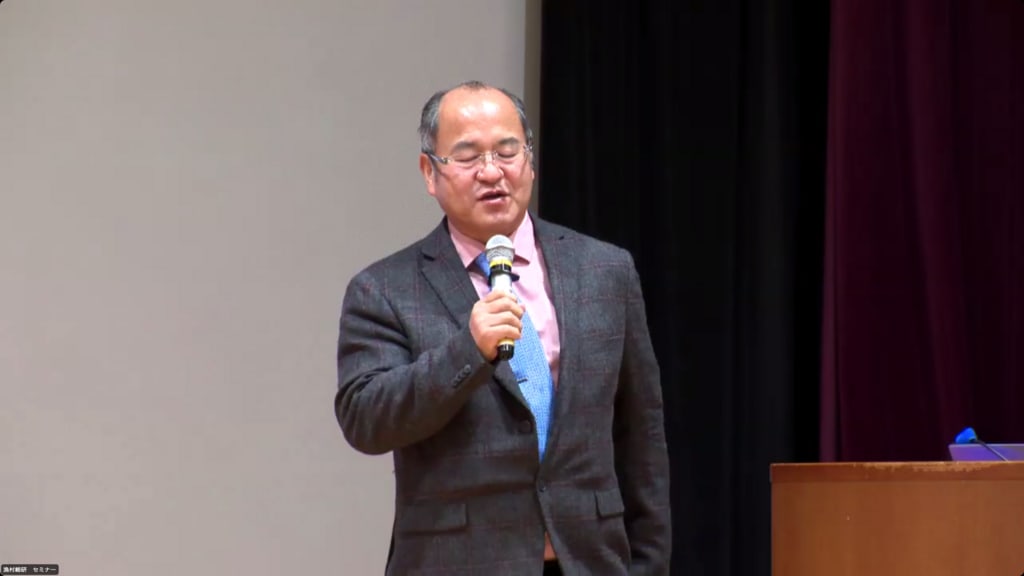
特別講演では、笹川平和財団の小林正則部長が「日本版ブルーエコノミーとしての海業推進」として国内外の事例を紹介し、海業の成功に欠かせない「意欲的、協力的な人材」を課題にあげた。
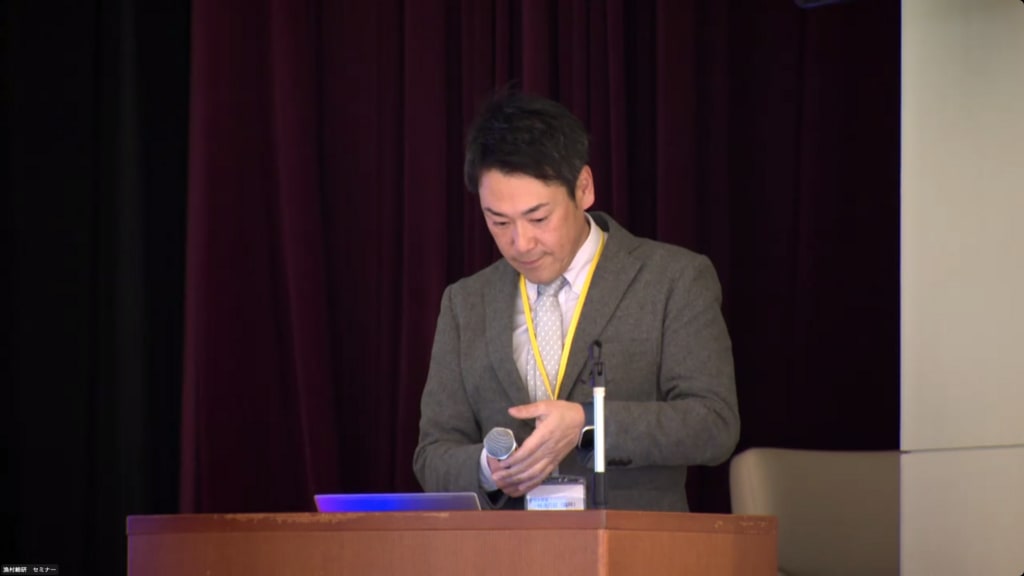
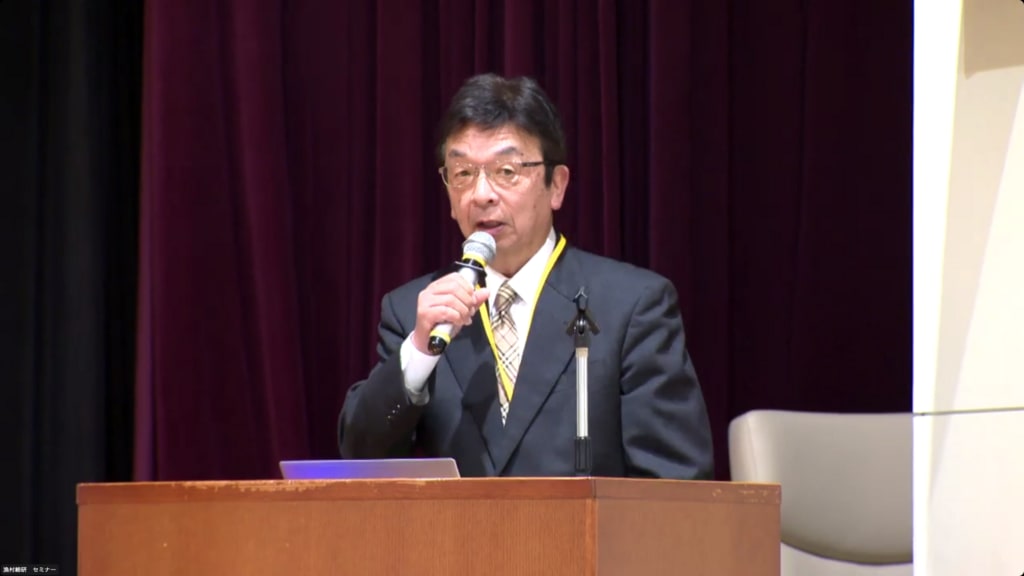
休憩を挟んで取組事例の講演に移り、静岡県西伊豆町の松浦城太郎係長が「海と共に生きるまち「西伊豆町」の「海業推進」に関する取組事例紹介」、富山湾の魚津漁協の濱住博之代表理事組合長が「漁協主体の海業」(魚津丸プロジェクト)、日間賀観光ホテルの中山勝比古顧問が「日間賀島(愛知県三河湾の離島)の海業」、結屋の川村結里子代表取締役が「関わりしろ型海業のすすめ」をそれぞれ報告した。






















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます