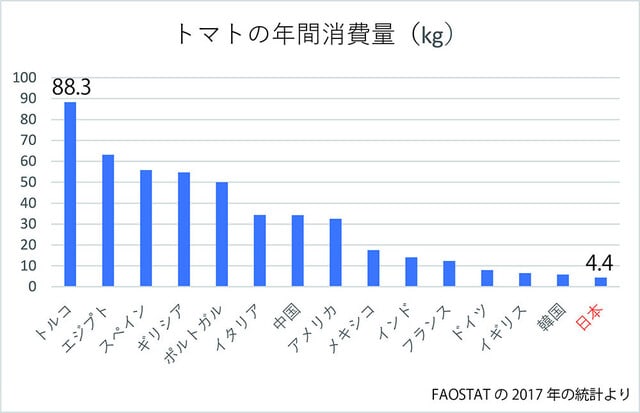チョコレートの歴史②-ヨーロッパにやって来た新しい食(5)
私は毎日昼食後にチョコレートを食べています。また、朝と昼にコーヒーを飲み、夜にはお茶を飲んでいます。
実は、チョコレート(カカオ)・コーヒー・茶がヨーロッパに入ってきたのは同じ頃です。カカオは中南米、コーヒーはエチオピア、茶は中国を原産地としていますが、まったく異なる出自の作物が同時期にヨーロッパにやって来たのです。
さらに、この3つはいずれも、カトリック国であるスペイン・ポルトガル・イタリア・フランスなどにまず広まり、その後にイギリス・オランダなどのプロテスタント国に広まりました。この裏には、スペインとポルトガルの海外進出で始まった大航海時代の主役がイギリス・オランダに移って行くという歴史の流れがあります。
今回は「チョコレートの歴史②」として、カカオがスペインなどのカトリック国に広まって行く様子について見て行きます。

カカオポッド(MaliflacによるPixabayからの画像)
************
カカオがいつスペインに持ちこまれたかについては正確なことは分かっていない。ネット上では、1504年にコロンブスが持ち帰ったとか、アステカ帝国を征服したエルナン・コルテスが1528年にスペイン国王に献上したとか書かれていたりするが、どちらも根拠に乏しいようだ。
ヨーロッパの歴史にカカオが最初に登場するのは1544年のことだ。キリスト教修道士にともなわれてスペインにやって来たマヤ族の貴族が、スペイン皇太子のフェリペに泡立てたカカオ飲料を献上したとされている。
本格的に貿易品としてカカオがアメリカ大陸からスペインに運ばれるようになったのは1585年になってからのことだ。しかし、それ以前にメソアメリカを支配したスペイン移住者たちの間でカカオは重要な飲料としての地位を固めていた。
そのいきさつは次の通りだ。
エルナン・コルテス(1485~1547年)率いるスペイン軍が1521年にアステカ帝国を滅ぼすと、メソアメリカは植民地としてスペイン人によって支配されるようになった。その頃のスペイン人は、カカオの実がメソアメリカで通貨として利用されるほど価値があることは理解していたが、積極的に口にしてみようとは思わなかったようだ。あるスペイン人はカカオ飲料を「人よりもブタにふさわしい飲み物」と断じている。
しかし、時が経つにつれてスペインからの移住者たちにメソアメリカの文化が浸透してきた。インディオの女性たちがスペイン人の妾や妻として台所を任されていたことや、現地で生まれたスペイン人の子供たちが成長してきたことがその大きな要因となったと考えられる。
こうしてスペイン人たちはコムギの代わりにトウモロコシを食べるようになったし、カカオ飲料も口にするようになった。特に上流階級の女性の間でカカオ飲料が大変好まれるようになったそうだ。
ただし、スペイン人たちの好みに合わせてカカオ飲料も変化したそうだ。スペイン人たちになじみのある砂糖や、トウガラシの代わりにシナモンやコショウ、アニスなどが入れられるようになった(バニラはそのまま使われた)。また、アステカのカカオ飲料は冷たかったのに対して、スペイン人たちは温かいカカオ飲料を好んで飲んだ。
ところで、アステカ帝国の時代までカカオを口にできるのは上流階級や兵士だけだったが、スペイン人が支配すると一般庶民もカカオ飲料を飲むようになった。この背景にはカカオ栽培の広がりがあった。カカオが儲けになることを知った人々が盛んにカカオを栽培するようになり値段が下がったのだ。ただし、多く栽培されたのは育てやすいフォラステロ種の方だった。味は良いが育てにくいクリオロ種は敬遠されたのだ。
大量に生産されるようになったカカオはスペイン本国にも送られるようになる。当時はスペイン-アメリカ大陸間には頻繁に輸送船が行きかい、多くの物資が運ばれていた。その一つとしてカカオがスペインに運ばれるようになったのだ。そして17世紀なるとスペイン宮廷を中心に上流社会でカカオ飲料が大流行するとともに、一般国民も大きな催事の際などにカカオ飲料を楽しむようになった。
スペインに伝わったカカオは、スペインが支配していたポルトガルやイタリア南部にも広がって行った。ポルトガルは1580年に王朝が断絶しスペインに併合されていた。一方、イタリア南部も1556年からスペインの支配地となっていた。この両地域には遅くとも17世紀初めまでにカカオが伝わったと考えられる。
カカオは次に、ヴェネツィアやジェノヴァ、フィレンツェ(のちのトスカーナ)などの小国やローマ教皇領などがひしめき合っていた北イタリアに伝えられた。ヴェネツィアやジェノヴァ、フィレンツェは貿易で成り立っている商業都市国家であった。これらの国々にはカカオを新しい交易品とする商人の手を通して持ち込まれたと考えられている。
一方、ローマ教皇領にカカオを持ちこんだのは「イエズス会」ではないかと考えられている。イエズス会はフランシスコ・ザビエルが属していたことから歴史の授業で習うことが多い。この修道会は新興のプロテスタントに対抗してローマ教皇の権威を高めるために1540年に設立されたものだが、活動資金を得るために商業活動も盛んに行っていた。その一環としてアメリカ大陸ではキリスト教に改宗させたインディオを使って、大農園で綿やサトウキビ、そしてカカオを栽培していた。このカカオをローマに持ちこんだと推測されている。
フランスにカカオがいつ、どのように伝わったかについてはよく分かっていない。スペイン王女アンヌが1615年にフランス国王ルイ13世の妻となった時に伝えられたという説もあるが、確たる証拠はないらしい。
確実でもっとも古い記録は、ルイ14世(在位:1643~1715年)が1659年にダヴィッド・シャリューと言う商人にフランス国内のカカオ商品の製造・販売の独占権を与えるとした勅許文だ。そのため、これ以前にはフランスにカカオが伝えられていたと考えられている。
1660年にスペイン王女のマリア・テレサがルイ14世と結婚した。彼女はスペイン王宮から連れて来た女官たちとカカオ飲料を日々楽しんだと言われている。おそらくこの行為がフランスの上流階級にカカオを定着させる役割を果たした。と言うのも、マリア・テレサがやって来た頃は、カカオ飲料は高貴な女性にふさわしくないとみなされていたのだが、その後急速に上流階級の女性に飲まれるようになったからだ。そして宮廷の公的行事では、常にカカオ飲料がふるまわれるようになったという。
さて、16~17世紀のカトリック教会においては、カカオ飲料をさまざまな断食日に飲んで良いかという議論が長く続いていた。実は、カカオだけでなく、コーヒーや茶、ジャガイモ、トウモロコシ、トマトなどの新しい食品について宗教的に許されるかという議論が起こっていたのだ。しかし、現代社会の様子から分かるように、新しい食品たちは宗教的にもヨーロッパ社会に受け入れられて行った。