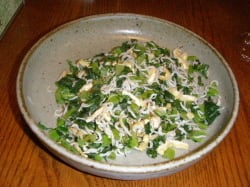デミグラスソースではなく、ドゥミグラスソース(demiglace sauce)というのが
発音的に近いということが百科事典の『ウィキペディア(Wikipedia)』でわかったが、
この手間のかかるソース作りに一度チャレンジしてみたかった。
しかし、時間がかかりすぎるので、ハインツのデミグラスソースを購入し、
ビーフシチュー作りのほうに時間をかけることにした。
それでも、出足のタマネギを炒めるのに40分ほど時間がかかってしまった。
16時30分にスタートし、出来上がりが19時なので、
手際よくやっても2時間30分かかる。
ただ、煮込んでいる時間は、タイマーをかけておけば、ほかのことが出来るので
実質は下ごしらえ、タマネギ炒めの1時間ちょっとぐらいですむ。
とにかく、大きな鍋一杯に作り、最初はスープ的に食べ、
温めなおすうちにデミグラスソース的に使うことが出来るので重宝だ。
オムレツにかけたり、ステーキに添えたり使い勝手がよい。
1週間のメニューとして応用性がある柱ができるので、男の料理としては合理的だと思う。


【材 料】
・牛肉600グラム (1256円)
・タマネギ2個 (56円)
・ジャガイモ2個 (116円)
・にんじん2個 (70円)
・マシュルーム (248円)
・ぶなシメジ (88円)
・エノキ (200円)
・ホールトマト (99円)
・ハインツデミグラスソース2缶 (700円)
・日本酒、赤ワイン、コショウ、片栗粉
【手 順】
1.下準備
・牛肉 600グラムを一口サイズに切る。
・これに、こしょう・日本酒の順で下味をつけ、片栗粉をまぶし10分ねかせる。
・タマネギ2個を千切り。
・ジャガイモ2個、にんじん2個を一口サイズに切る。
・マッシュルーム、ぶなシメジ、エノキを切る。
2.炒める
①シチュー用の深鍋で、タマネギをアメ色になるまで炒める。(30分くらいで透明になる。)
②ジャガイモ、にんじんを炒め、炒めたタマネギが入っている深鍋に入れる。
③この深鍋にカップ8杯の水をいれ、強火で沸騰させる。沸騰したら弱火にする。
④鍋が沸騰するまでに、フライパンで牛肉を焦げ目がつくまで炒める。
赤ワインお猪口2杯をいれアルコールが飛ぶまでさらに炒める。
⑤炒めたものを野菜などが入っている鍋に入れ、最後に、きのこを炒めて入れる。
3.煮込む
①ホールトマト1缶を入れる。
②ブイヨン2個をいれる。
③1時間煮込む。
4.味を調える
①ハインツデミグラスソース2缶をいれる。
②ブルドックソースを大さじ2杯程度入れ味を調える。
③さらに30分煮込む。
【感 想】
調味料は、肉の下味(こしょう、日本酒)、赤ワインお猪口2杯、ブイヨン2個、
デミグラスソース2缶、ブルドックソース大さじ2杯のみで
他の調味料は使っていないが、素材からの甘味が引き出されており、
塩味はこれだけで十分にある。
赤ワイン1本をあけたが、使用したのはお猪口2杯だけであり、後は飲むしかない。
のんべいの割には、ワインはあまり飲まないのでこの後始末に困る。
発音的に近いということが百科事典の『ウィキペディア(Wikipedia)』でわかったが、
この手間のかかるソース作りに一度チャレンジしてみたかった。
しかし、時間がかかりすぎるので、ハインツのデミグラスソースを購入し、
ビーフシチュー作りのほうに時間をかけることにした。
それでも、出足のタマネギを炒めるのに40分ほど時間がかかってしまった。
16時30分にスタートし、出来上がりが19時なので、
手際よくやっても2時間30分かかる。
ただ、煮込んでいる時間は、タイマーをかけておけば、ほかのことが出来るので
実質は下ごしらえ、タマネギ炒めの1時間ちょっとぐらいですむ。
とにかく、大きな鍋一杯に作り、最初はスープ的に食べ、
温めなおすうちにデミグラスソース的に使うことが出来るので重宝だ。
オムレツにかけたり、ステーキに添えたり使い勝手がよい。
1週間のメニューとして応用性がある柱ができるので、男の料理としては合理的だと思う。


【材 料】
・牛肉600グラム (1256円)
・タマネギ2個 (56円)
・ジャガイモ2個 (116円)
・にんじん2個 (70円)
・マシュルーム (248円)
・ぶなシメジ (88円)
・エノキ (200円)
・ホールトマト (99円)
・ハインツデミグラスソース2缶 (700円)
・日本酒、赤ワイン、コショウ、片栗粉
【手 順】
1.下準備
・牛肉 600グラムを一口サイズに切る。
・これに、こしょう・日本酒の順で下味をつけ、片栗粉をまぶし10分ねかせる。
・タマネギ2個を千切り。
・ジャガイモ2個、にんじん2個を一口サイズに切る。
・マッシュルーム、ぶなシメジ、エノキを切る。
2.炒める
①シチュー用の深鍋で、タマネギをアメ色になるまで炒める。(30分くらいで透明になる。)
②ジャガイモ、にんじんを炒め、炒めたタマネギが入っている深鍋に入れる。
③この深鍋にカップ8杯の水をいれ、強火で沸騰させる。沸騰したら弱火にする。
④鍋が沸騰するまでに、フライパンで牛肉を焦げ目がつくまで炒める。
赤ワインお猪口2杯をいれアルコールが飛ぶまでさらに炒める。
⑤炒めたものを野菜などが入っている鍋に入れ、最後に、きのこを炒めて入れる。
3.煮込む
①ホールトマト1缶を入れる。
②ブイヨン2個をいれる。
③1時間煮込む。
4.味を調える
①ハインツデミグラスソース2缶をいれる。
②ブルドックソースを大さじ2杯程度入れ味を調える。
③さらに30分煮込む。
【感 想】
調味料は、肉の下味(こしょう、日本酒)、赤ワインお猪口2杯、ブイヨン2個、
デミグラスソース2缶、ブルドックソース大さじ2杯のみで
他の調味料は使っていないが、素材からの甘味が引き出されており、
塩味はこれだけで十分にある。
赤ワイン1本をあけたが、使用したのはお猪口2杯だけであり、後は飲むしかない。
のんべいの割には、ワインはあまり飲まないのでこの後始末に困る。