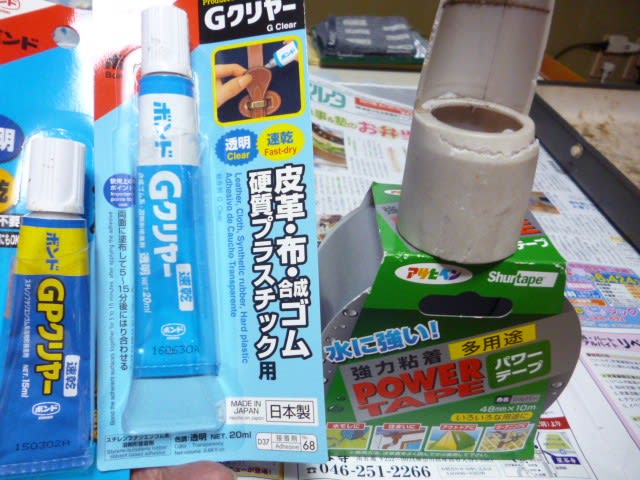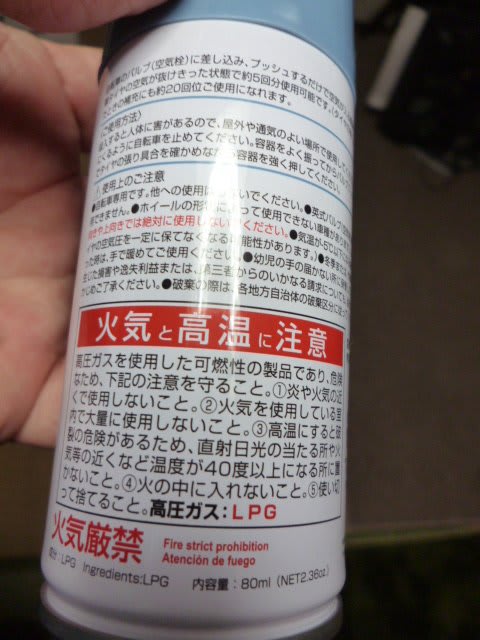9月21日(木) 晴れ
先日つけたブレーキライトが点かないようなので外してしまおう。
またもや減速感知(慣性)ブレーキライトの製作は失敗か。

ごちゃごちゃしすぎ。
はずしてみたら・・・
あれ、電池が無くなっているかと思ったら点くじゃん。
まあ、いいや。これは外してしまって、通チャリ1号の壊れたスイッチを取換えよう。
あれ、タイヤの空気が少ないな。昨日入れたばかりなのに。
虫ゴムの破れが原因かな。
この際「スーパーバルブ」にしてみよう。
さて、レバーが飛んでしまったマイクロスイッチを交換しよう。
左が代わりのもの。まるっきり同じものではないがなんとかなるかな。
リード線をはんだ付けし、周囲をグルーガンで固めた。
左ブレーキを握ると、カチカチとスイッチが動くので、これでいいのではないか。
試すのは、前輪を回して電気を起こさないとできないので、また今度やろう。
すると・・・
あれ、また空気が抜けている「スーパーバルブ」が原因か?
でもバルブ先端に唾(つば)をつけてみたけど、膨らんでこなかったしな。
じゃあパンク?
あ、パンクしていた。
パッチを張って直す。
ところが・・・
空気漏れが止まらないと思ったら、ゴム糊が着いていない。
ゴム糊が古くなっていたのか、粘りが強くなっていたんだよな。
ゴム糊は一つしかないので、何とかもう一度やってみる。
今度は着いたようだ。
それにしてもこれはひどい。
タイヤからチューブを外すときに、バリバリにくっついていた。
サンドペーパーや、スポンジやすりでこする。
このように左右両面に筋(すじ)のようにくっついている。
ナイフでそいだりもしてみたが、なかなかはがれない。
全部取り去るのに2時間半もかかった。
これはタイヤが駄目なんだろうなぁ。
どこのタイヤだ?
あれ、いつものチェンシンタイヤだ。
内側を見ると、異常は無い。
え、ということはチューブが原因?
チューブはiRC(井上ゴム工業)製のちゃんとしたメーカー品だ。
どこが悪くて、ゴムの撚(よ)りがくっついたのだろう?
あのこらさんがくっつかないように使っている粉をつけてみるか。
同じものはないが、シッカロールでいいだろう。
トンサン「おかあ、シッカロールは?」
おかあ「古いから捨てたよ。」
トンサン「えっ、残念。」
おかあ「片栗粉では?」
トンサン「濡れたりしてべたつかないか?」
おかあ「べたつかないよ。」
ということで片栗粉を塗る。
タイヤの内側にも軽く。
ということで完成。
【覚書】 前輪に片栗粉を塗って、スーパーバルブを使った。