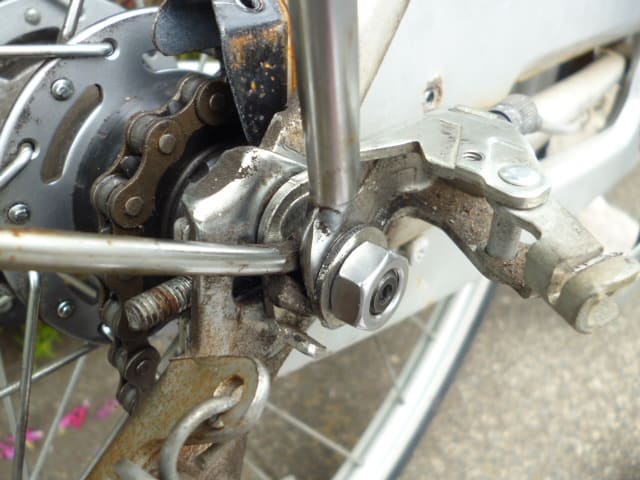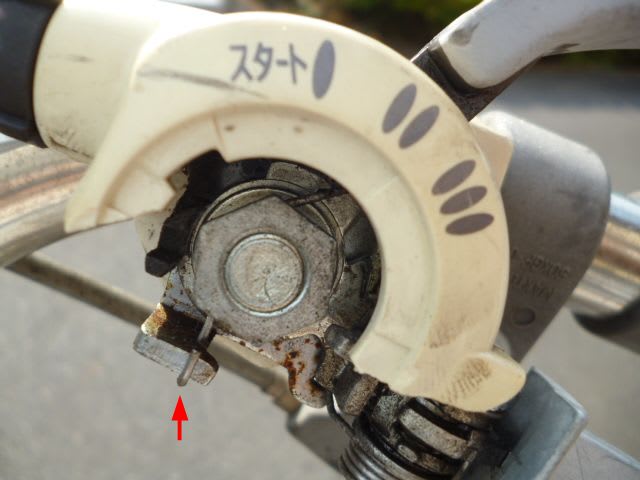10月24日(月) 曇りのち晴れ
「シュワルベ英式バルブコア」を通チャリ1号の後輪に装着しているが、
シュワルベ 英式バルブコアを試してみよう。
プッシュバルブ(弁)があるので、空気圧が測定できるのではないかと思っていたが、あのこらさんによると、
「シュワルベのエアマックス プロ AIRMAX PROという圧力計でしか空気圧は測れないみたいです。」
http://www.g-style.ne.jp/item.php?brand_id=16&item_category_id=98
とのこと。
そのコメントを見ながら、『そうだ、車のエアゲージは気圧が低くなければ使えないのだが、米式バルブに合う。もしかして・・・』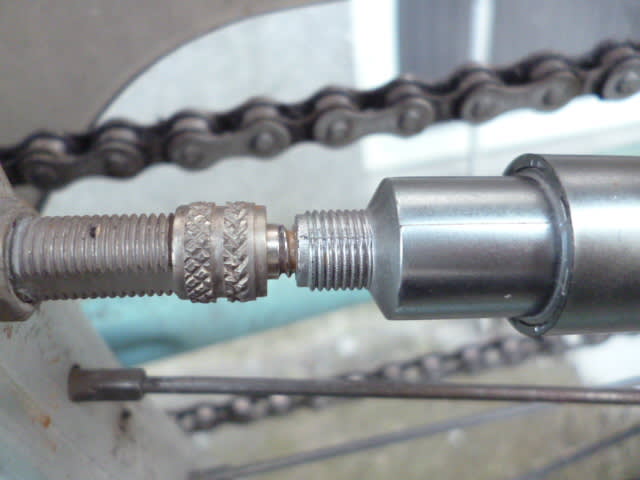
まずは振動で点灯するLEDを外さないと・・・
ところが外そうとすると、「シュワルベ英式バルブコア」が回ってしまい、緩めることができない。
「シュワルベ英式バルブコア」は回り止めがないので、LEDと一緒に回ってしまう。
先の細いラジペンでつかもうとしたが無理。
結局、トップナットを外して、「シュワルベ英式バルブコア」ごと引き抜いた。
そしてここをラジペンでつかみ、LEDのケースを回す。
素手では無理なので、このLEDを装着しているときは、ラジペンの携帯が必要。
LEDと「シュワルベ英式バルブコア」のネジのなじみを良くするために、何回か付けたり外したり。
さて「シュワルベ英式バルブコア」をつけて空気圧を測ろうとしたが・・・
サイズが全然違い、これじゃあ測れるわけがない。
シュワルベのエアマックス プロ AIRMAX PROという圧力計が必要なのだ。
やっぱり英式バルブを米式に変換するアダプターがいいのかな。
Panaracer(パナレーサー) エアチェックアダプター
こちらは試した人の記事。