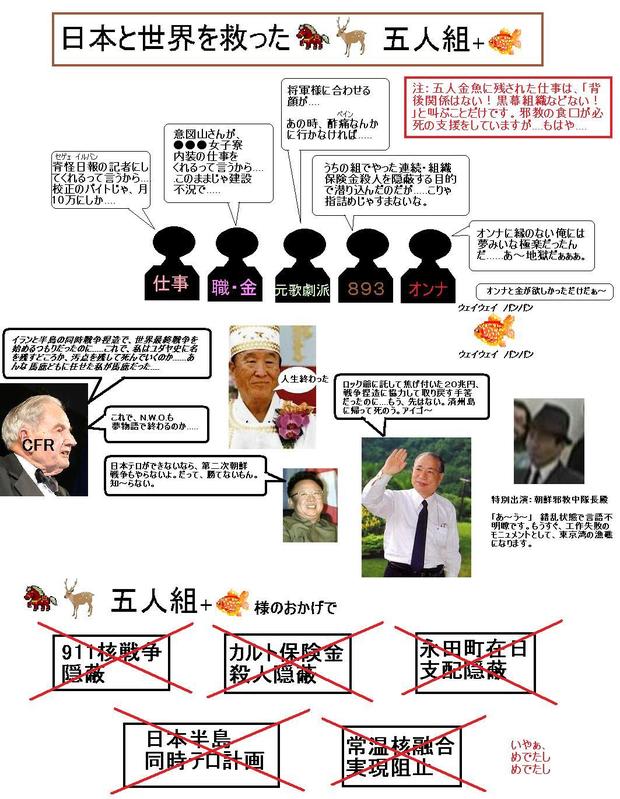水で走る車!! ホンモノか?!!
検証第2弾 システムは納得出来るか?
■質疑応答<http://www.genepax.co.jp/news/wes_008.asx>
原理は、簡単である。不思議でも何でもない。先ず、水を分解する。その方法は要するに化学反応で分解する。分解した水素を使い、燃料電池で発電する。その方法は、すでに開発されている水素燃料電池と変わらない。その発電した電気を、すでにある電気自動車のバッテリーの充電して走る。それだけのことである。
問題は、その性能と耐久性、そして、化学反応で出来た副生成物が何か。その処理と環境影響はないか、化学反応を起こす元の物性は何か。そのコストはいくらか。それらについては詳しい資料はない。 「wes_20080613_ver1.pdf」をダウンロード <http://hyouhei03.blogzine.jp/tumuzikaze/files/wes_20080613_ver1.pdf> に依れば、水が金属(?)と反応して、先ず、分解されるとある。これが味噌である。その金属の種類、組み合わせはブラックボックスなので確認しようがない。それから先は、水素燃料電池と同様であるので、水しか排出されない。クリーンである。 そのブラックボックスは、確認できないが電気分解が出来たとしよう。十分に必要量が分解できたとしよう。それは画期的なことである。電気分解にいかなる化石燃料(電気を含む)も使用しないからである。化学反応であれば金属(?)かなにか、消費されるからそのコストと副生成物が何か。消費されないとすると触媒か。そのコストは。? 私見ではあるが、水を原料とした水素エネルギーはそこに集約される。水の分解である。水の分解が、化石燃料を用いず、太陽等フリーエネルギーもしくは触媒、きわめて低エネルギーコストで可能ならば、水素エネルギーはフリーエネルギーに近く、紛れもなくクリーンエネルギーである。 フリーエネルギーとは、永久機関ではない。そこを取り違えていて、頭から疑問視する向きがあるが、ナンセンスと言うほかない。自由に誰でも利用でき、無尽蔵にあるエネルギーのことである。それは必ず可能である。石油も独占がなければ、フリーエネルギーではないか。クリーンとは使いすぎると言えなくなるだけである。 水の分解は、電気分解、化学分解、物理分解がある。物理分解と言う言葉は造語であるが、ある一定の要するに物理的エネルギーを加えることで起こる。電気分解もその一種であろうが、そうではない何かがある。そうして、これまでも実現してきたが隠された。触媒もその一つであろう。いずれにしても成功したと言うことが本当ならば、喜ばしいことだが、又、隠されることがないように祈る。 早速、メールで連絡を取ったら、次のような返事が来た。 《ジェネパックス広報担当の大西です。 何でもそうであるが、新しいものは暖かく育てなければならない。それは見守ることである。取り分け、エネルギーは国策上最大の課題であるから、尚更のことである。 しかし、利益欲得だけで走るものも多い。現今の問題は、利益欲得で潰そうとすることが多いかも知れない。故に、検証し、注目していく。
ご連絡が大変遅くなりました事をまず深くお詫び申し上げます。
弊社のウォーターエネルギーシステム(WES)に対するお問い合わせをいただき、
ありがとうございます。
温かいご支援のメールを大変感謝しております。
現在ご指摘の通り、慎重に行動をさせて頂いております。
弊社の内容・資料等のお問い合わせは弊社WEB上での情報がすべて
となっております。新しいリリースや情報はWEB上で順次公開させて
頂く予定です。
よくあるご質問を随時更新させて頂きまして、皆様のご質問にお答えさせて頂く予定です。
http://www.genepax.co.jp/faq/
また技術に関しましてはWEB上で公開しております情報以外では、
日経BP様・日経エレクトロニクス様が記事にしていただいております内容をご覧いただ
けますでしょうか。
http://www.nikkeibp.co.jp/news/biz08q2/575019/?bzb_pt=0
また現在プレス発表資料をPDFにてWEB上で配布しております。
http://www.genepax.co.jp/pdf/wes_20080613_ver1.pdf
英文ページにつきましても一部HPを公開しております。
http://www.genepax.co.jp/en/
すべての英文ページ・資料等を近日にアップさせて頂きますので今しばらくお待ち下さい。
一部WEB上では、弊社のシステムについて、エネルギー保存の法則に反している
というような批判的書き込みがされておりますが、現時点では弊社としてはこれ
に応えるためにこれ以上の技術情報を開示することは、弊社の独自技術の流出に
なるものとして控えさせて頂いておりますので、その点はどうぞご承知おきくだ
さい。
現在公的第三者機関でのテスト等も行う段階となっております。
今後とも、弊社WESに対する応援を賜りますよう、お願いいたします。
㈱ジェネパックス 広報担当
大西
_________________________________________________
株式会社ジェネパックス http://www.genepax.co.jp
広報担当 大西 淳(Jun Onishi)j.onishi@genepax.co.jp
■OSAKA OFFICE
〒532-0003 大阪市淀川区宮原2-14-14
新大阪グランドビル4F
TEL 06-6394-7100 / FAX 06-6394-7110
■TOKYO OFFICE
〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-6-4
千代田ビル11F
TEL 03-3502-3922 / FAX 03-3502-3923
_________________________________________________》
【転載開始】
「水と空気だけで発電し続けます」,ジェネパックスが新型燃料電池システムを披露
図1 披露した試作車<http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20080612/153229/?SS=imgview&FD=1763070391&ad_q>
図2 120Wの燃料電池システム<http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20080612/153229/?SS=imgview&FD=1761223349&ad_q>
図3 120Wの燃料電池システムの内部<http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20080612/153229/?SS=imgview&FD=1762146870&ad_q>
図4 300Wの発電システムを荷室に搭載(左)<http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20080612/153229/?SS=imgview&FD=1763070391&ad_q>
ジェネパックスは2008年6月12日,水を燃料とする燃料電池システム「WES:Water Energy System」についての技術発表会を大阪府の議会会館で開催した(図1,2)。燃料極に水を,空気極に空気を供給するだけで発電できることから,CO2を排出しない。
基本的な発電の仕組みは水素を燃料とする燃料電池と同じ。ただし,同社のMEA(膜/電極接合体)には水を水素と酸素に化学反応で分解させることが可能 な物質を含ませているのが最大の特徴という。詳細は明かさなかったが,「昔から知られている水から水素を取り出す方式をMEAにうまく組み込んだ」(ジェ ネパックス 代表取締役 社長の平澤潔氏)とする。これは金属水素化物と水を反応させた際に水素が取り出せる仕組みと近い方式としているが,こうした方式よりも長期間,水から水素 を取り出せるのが特徴とみられる(金属水素化物を利用した燃料電池の記事1,記事2)。
その結果,セルには水と空気を供給するだけで済み,水素の改質器や高圧の水素タンクなどを不要にできる。しかも,MEAには特別な触媒を使っていない上,白金などのレアメタルも従来の燃料電池システムとほぼ同じ使用量で済むという。
このほか,メタノールを燃料とするダイレクト・メタノール型燃料電池(DMFC)とは違い,燃料電池からCO2が発生しない上,燃料極側でCOによる触媒の劣化(被毒)が起こらず,長寿命化が期待できるとしている。寿命については試作してからまだ1年ちょっとしか経ておらず,これからデータを蓄積していくとのこと。
発表会では定格出力120Wの燃料電池スタックと,同300Wの燃料電池システムを披露した。120Wの燃料電池スタックの実演では,最初に水を乾電池 式のポンプで供給し,発電後はポンプを停止させて,パッシブ型として作動させた。その際の燃料電池スタックの電圧は25~30V。燃料電池スタックは40 セルを直列接続させているため,1セル当たりでは出力が3W以上,電圧が0.5~0.7V程度,電流が6~7A程度とみられる(図3)。セルの反応部分は 10cm×10cmであることから,出力密度は30mW/cm2以上はあるもよう。
一方,300Wの燃料電池システムは,水や空気をポンプで供給するアクティブ型である。実演ではこのシステムで鉛蓄電池を充電してテレビや照明に電力を 供給させたほか,タケオカ自動車工芸の小型電気自動車「Reva」の電源として荷室に300Wの燃料電池システムを搭載して実際に走行させた(図4)。同 社は実際には500Wのシステムにする予定だったが,MEAの材料が間に合わず,300Wの燃料電池スタックになってしまったという。
今後の展開について,1kW級の発電システムを電気自動車や家庭などに供給したいとしている。電気自動車についてはこの発電システムだけで駆動さ せるのではなく,電気自動車の2次電池を充電する発電機としての利用を想定している。コストについては現状で200万円くらいだが,量産できれば1kW当 たり50万円以下にできるとのこと。この製造コストを実現できれば,家庭用の太陽電池システムと競合できるとの見解を示した。【転載終了】