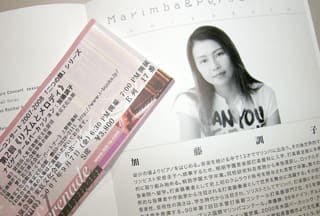
加藤 訓子 東京文化会館レクチャーコンサート「二つの顔」シリーズ2
『リズムとメロディ』
久々のコンサート編。
約一年ぶりの加藤訓子。
武満 徹/ムナーリ・バイ・ムナーリ
オープニング暗転した会場の中ほど
観客入り口からシャリーンというチャイムとともに登場。
(去年の「カシオペア」と同じ演出。「カシオペア」は指定だが
本曲は加藤のアイデア、だそう)
小柄な体に金属のチャイムと木質の連鈴などを巻きつけ
(招き猫の首についているような)大きな鈴を持った両手を振りら
少し腰を落として弧を描くように足を振りながら、ゆっくりと通路を進む。
そのしなやかな身のこなし方は、まるで猫のようだ。
ステージ前を通り過ぎながら身に着けた楽器を一つずつ置き捨て
登壇すると口にくわえたスティックを取り、演奏がはじまる。
この曲の楽譜はフランスのブルーノ・ムナーリというデザイナーの
つくった<Invisible book>(読めない絵本)に
武満さんが手を加えているらしい。
赤、黄、白、黒それぞれの色に意味があり
白い紙にはいくつかの短いセンテンス(風と木をイメージするとか)
で指示が与えられている。
非常に即興性が高い曲だと思うが
根底には「土、木、風、水、火」といった自然の要素があり
森羅万象を直感的に表現する、ということなのだと思う。
加藤の演奏は、(勝手な?)期待通りダイナミズムに富み
一方で理知的な繊細さを感じさせ
色彩感と自在感に溢れるものだった。
打楽器のもつプリミティブなリズム感と
時の流れによる人間の機智の融和を肯定する
前向きなエネルギーを感じさせてくれた。
はなはだ個人的な思い入れになるけれど
こういう曲を演奏する彼女の姿は
まるで巫女(シャーマン)のように見える。
最後は波の音(水)を表現して終わるという
(原曲の指示、らしい)いかにも武満らしい終わり方になる。
ま、これもレクチャーコンサートという形式上
演奏後に彼女が解説してくれたのでわかったことだけど。
またタイトルの『ムナーリ・バイ・ムナーリ』には
デザイナーの名とともに「無なり」の掛詞になっているとのこと。
最初の、身に付けた楽器を一つずつはずしていくのが
「束縛から解放されるという、私なりの“無なり”の表現です」
というのにもなるほど、と納得させられました。
デビット・ラング/アンビル・コーラス
初めて聴く作曲家。中世の鍛冶屋の物語を
モチーフにしているらしいが
ドラム缶やらレールの切れ端やらを使って
複雑なリズムを騒々しく演奏する曲。
1曲目の深遠なイメージ表現とはうって変わって
インダストリアルリズムをアナログにトレースするという
ある意味ミニマル的な発想の曲(でもないか)。
厳格なリズム感が要求されながら
演奏パフォーマンスとしては非常にユーモラスで楽しめた。
曲の前に観客を相手に複合リズムの練習をさせて
笑いを取るところもレクチャーコンサートならではのいいところ。
単に曲を聴いただけでは、素人にはあのリズムの複雑怪奇さと
それをこなすプレイヤーの力量というものが分からなかっただろう。
フレデリック・ジェフスキ/To the Earth
大小4つの植木鉢をならべてそれを叩きながら
大地の女神ガイヤを讃える詩を語る、という実にシンプルな曲。
スポンジの上に横たえた、何の変哲もない4つの鉢が
ステージに座り込んだ加藤の2本のマレットによって
素朴な、それでいて思いもよらない
透き通った響きを持つ楽器に変容する。
土の焼き物でできた鈴もあるくらいだから
考えてみれば驚くことも無いのかもしれないが
それは、コロンブスの卵というもの。
英語の詩は意味は良く分からないが
(概要は演奏する前に説明してくれた)
とつとつとした語りと「鉢」のリズムは
さながら絵本を読み聞かされているような
あるいは、わらべ歌そのままのようで
どこか懐かしく、やさしく、心に残る。
ジェフスキーの意図としては政治的メッセージとして
大地の神=植木鉢(土の楽器)=生命の根源=労働のシンボル
という図式なのかもしれない。
しかし現代の耳で聴くとそれはむしろ
土=環境という読み替えができる、というのは曲解だろうか。
最後に鉢のひとつをささげるように目の前に持ち上げて
コ~ンと叩いて曲が終わる、というのも象徴的。
シンプルなだけに、メッセージは強い。
やっぱり、シャーマン、だな。
今日聴いた曲の中では最も印象的で、面白かった。
もし前述の曲解がゆるされるなら
もっともっと多くの人に聴いてもらいたい曲だと思う。
ここまでが前半で、打楽器の多彩さを楽しませてくれた。
後半はマリンバの独奏。
バッハ/マタイ受難曲より「コラール」
マリンバの深い響きの世界に引き込まれる。
特に低音の、叩く、というより空気ににじんでくるような
ウォーンという響きが実に心地よい。
「武満さんが好んで聴いていた」ことによる選曲とのこと。
加藤訓子/ルーツ・オブ・マリンバ
彼女の自作曲。
冒頭、アフリカン・リズムを髣髴とさせる
最低音のフレーズから始まり
ミニマル的なリズム転換を経て、最高音域にいたって終わる。
彼女の言葉によると、最後のメロディーには沖縄的な
イメージがあるとのことで
アフリカから沖縄まで、場所と時間の「旅」を表現したとのこと。
マリンバのルーツは長さの違う木片拾い集めて
ひざの上に並べ、座った地面に穴を掘って共鳴させるものだったという。
実際に木の切れ端を並べて、ステージに座り込んで叩いて見せた
彼女は、とてもかわいらしくまた、全身楽器になって奏する様は
本当に楽しそうに見えた。
太古の人間のそんなプリミティブな喜びが、
現代の洗練されたマリンバの中にも残っている、ということなのだろう。
三善 晃/トルスⅢ
75~76年の作品。時代的に、日本の「現代音楽」が
最も先鋭的に、意欲的に想像されていた時代の曲。
総じて今日の演奏が「加藤訓子」という
パーソナリティに追うところが大きかったとすれば
この曲はある意味でその対極にあるものだと思う。
マリンバの楽曲としては世界的に定番として
認められた重要な曲であるらしい。
技術的な難度を徹底して追求し、新しい地平を開くという
70年代の前衛的手法の典型ではないかと思う(違うかな・・・)。
演奏家の技量も、もちろんパーソナリティの重要な要素ではあるが
難技法を要求するあまりに、奏者の創造性が排除されかかる。
そのぎりぎりのところで葛藤しながら表現の完成度を高めるという
実にストイックで、職人的作風。
作曲、演奏するほうは一種の挑戦であり
演奏すること自体のカタルシスはあるのかもしれないが
今の耳で聴くと、あまり面白くは聴こえない(と思う)。
曲が始まったとたん(初めてだったので)
あ、いかにも!って感じ。
まあ、そういう時代だったのだから仕方ないし
そこを究めて認められて残っているのなら、
それはそれで素晴らしい成果なのだろう。
最後に「アンコールピース的にリラックスして聴いて」という
プッチーニオペラからのアレンジ。
「蝶々婦人」「ラ・ボエーム」「トゥーランドット」からの抜粋。
編曲は彼女自身で、演奏会で披露するのは今日が初めてとのこと。
布を巻いたマレットでアタック音を極力抑えた
にじむような響きを堪能させてくれた。
木を叩いているにもかかわらず
まるで水の滴りのような濡れた響きがあって心地よい。
クラシックの編曲ではあっても
抽象的なモザイク画のようにちりばめられた音のしずくに
目を凝らすと形が浮かび上がってくる
そんな印象があった。
後半の解説の中で彼女は
一般論として、ある意味で崩壊、または
やりつくされた感がある「現代音楽」にも
若い世代の成長で、新しい創造が生まれている、と語っていた。
ここからはあくまでも個人的な感想であるが、
ビジュアル的なデザインを重視する現代にあって
彼女自身、まさに時代が求める表現者のひとりなのだ。
音楽にとって、奏者が男であるか女であるかは関係ない
といえばそれまでだが
彼女が「演奏する」というパフォーマンスの中に
ビジュアル的な「美しさ」は説得力があり、
力があると思うのは私だけだろうか。
自由、開放といいながら必要以上にストイックであった
前衛の時代にあってすら、吉原すみれや高橋アキ、安倍圭子など
奏者としての女性の存在は光っていた。
30年の時間を経て、それが時代の流れとして定着した
ということなのではないか。
昨年、初めて彼女の演奏する『カシオペア』を聴いた時にも
その時間の流れによる変化を、確実に感じた。
「リズムはメロディでありメロディはリズムである」という彼女が
今現在、マリンバを弾くという行為で何ができるのか
「できる限りやってみたい」という言葉に
「ムナーリ・バイ・ムナーリ」の演奏にもみなぎっていた
自由で前向きなエネルギーを感じたのである。
もう終わった、という「現代音楽」の埋もれた作品が
あるいは新しい創造の芽が
猫のごとき優美な巫女(シャーマン)の手によって
息を吹き込まれることを期待したい。
東京文化会館レクチャーコンサート 2nd
「リズムとメロディ」
ナビゲーター&パーカッション:加藤訓子
『リズムとメロディ』
久々のコンサート編。
約一年ぶりの加藤訓子。
武満 徹/ムナーリ・バイ・ムナーリ
オープニング暗転した会場の中ほど
観客入り口からシャリーンというチャイムとともに登場。
(去年の「カシオペア」と同じ演出。「カシオペア」は指定だが
本曲は加藤のアイデア、だそう)
小柄な体に金属のチャイムと木質の連鈴などを巻きつけ
(招き猫の首についているような)大きな鈴を持った両手を振りら
少し腰を落として弧を描くように足を振りながら、ゆっくりと通路を進む。
そのしなやかな身のこなし方は、まるで猫のようだ。
ステージ前を通り過ぎながら身に着けた楽器を一つずつ置き捨て
登壇すると口にくわえたスティックを取り、演奏がはじまる。
この曲の楽譜はフランスのブルーノ・ムナーリというデザイナーの
つくった<Invisible book>(読めない絵本)に
武満さんが手を加えているらしい。
赤、黄、白、黒それぞれの色に意味があり
白い紙にはいくつかの短いセンテンス(風と木をイメージするとか)
で指示が与えられている。
非常に即興性が高い曲だと思うが
根底には「土、木、風、水、火」といった自然の要素があり
森羅万象を直感的に表現する、ということなのだと思う。
加藤の演奏は、(勝手な?)期待通りダイナミズムに富み
一方で理知的な繊細さを感じさせ
色彩感と自在感に溢れるものだった。
打楽器のもつプリミティブなリズム感と
時の流れによる人間の機智の融和を肯定する
前向きなエネルギーを感じさせてくれた。
はなはだ個人的な思い入れになるけれど
こういう曲を演奏する彼女の姿は
まるで巫女(シャーマン)のように見える。
最後は波の音(水)を表現して終わるという
(原曲の指示、らしい)いかにも武満らしい終わり方になる。
ま、これもレクチャーコンサートという形式上
演奏後に彼女が解説してくれたのでわかったことだけど。
またタイトルの『ムナーリ・バイ・ムナーリ』には
デザイナーの名とともに「無なり」の掛詞になっているとのこと。
最初の、身に付けた楽器を一つずつはずしていくのが
「束縛から解放されるという、私なりの“無なり”の表現です」
というのにもなるほど、と納得させられました。
デビット・ラング/アンビル・コーラス
初めて聴く作曲家。中世の鍛冶屋の物語を
モチーフにしているらしいが
ドラム缶やらレールの切れ端やらを使って
複雑なリズムを騒々しく演奏する曲。
1曲目の深遠なイメージ表現とはうって変わって
インダストリアルリズムをアナログにトレースするという
ある意味ミニマル的な発想の曲(でもないか)。
厳格なリズム感が要求されながら
演奏パフォーマンスとしては非常にユーモラスで楽しめた。
曲の前に観客を相手に複合リズムの練習をさせて
笑いを取るところもレクチャーコンサートならではのいいところ。
単に曲を聴いただけでは、素人にはあのリズムの複雑怪奇さと
それをこなすプレイヤーの力量というものが分からなかっただろう。
フレデリック・ジェフスキ/To the Earth
大小4つの植木鉢をならべてそれを叩きながら
大地の女神ガイヤを讃える詩を語る、という実にシンプルな曲。
スポンジの上に横たえた、何の変哲もない4つの鉢が
ステージに座り込んだ加藤の2本のマレットによって
素朴な、それでいて思いもよらない
透き通った響きを持つ楽器に変容する。
土の焼き物でできた鈴もあるくらいだから
考えてみれば驚くことも無いのかもしれないが
それは、コロンブスの卵というもの。
英語の詩は意味は良く分からないが
(概要は演奏する前に説明してくれた)
とつとつとした語りと「鉢」のリズムは
さながら絵本を読み聞かされているような
あるいは、わらべ歌そのままのようで
どこか懐かしく、やさしく、心に残る。
ジェフスキーの意図としては政治的メッセージとして
大地の神=植木鉢(土の楽器)=生命の根源=労働のシンボル
という図式なのかもしれない。
しかし現代の耳で聴くとそれはむしろ
土=環境という読み替えができる、というのは曲解だろうか。
最後に鉢のひとつをささげるように目の前に持ち上げて
コ~ンと叩いて曲が終わる、というのも象徴的。
シンプルなだけに、メッセージは強い。
やっぱり、シャーマン、だな。
今日聴いた曲の中では最も印象的で、面白かった。
もし前述の曲解がゆるされるなら
もっともっと多くの人に聴いてもらいたい曲だと思う。
ここまでが前半で、打楽器の多彩さを楽しませてくれた。
後半はマリンバの独奏。
バッハ/マタイ受難曲より「コラール」
マリンバの深い響きの世界に引き込まれる。
特に低音の、叩く、というより空気ににじんでくるような
ウォーンという響きが実に心地よい。
「武満さんが好んで聴いていた」ことによる選曲とのこと。
加藤訓子/ルーツ・オブ・マリンバ
彼女の自作曲。
冒頭、アフリカン・リズムを髣髴とさせる
最低音のフレーズから始まり
ミニマル的なリズム転換を経て、最高音域にいたって終わる。
彼女の言葉によると、最後のメロディーには沖縄的な
イメージがあるとのことで
アフリカから沖縄まで、場所と時間の「旅」を表現したとのこと。
マリンバのルーツは長さの違う木片拾い集めて
ひざの上に並べ、座った地面に穴を掘って共鳴させるものだったという。
実際に木の切れ端を並べて、ステージに座り込んで叩いて見せた
彼女は、とてもかわいらしくまた、全身楽器になって奏する様は
本当に楽しそうに見えた。
太古の人間のそんなプリミティブな喜びが、
現代の洗練されたマリンバの中にも残っている、ということなのだろう。
三善 晃/トルスⅢ
75~76年の作品。時代的に、日本の「現代音楽」が
最も先鋭的に、意欲的に想像されていた時代の曲。
総じて今日の演奏が「加藤訓子」という
パーソナリティに追うところが大きかったとすれば
この曲はある意味でその対極にあるものだと思う。
マリンバの楽曲としては世界的に定番として
認められた重要な曲であるらしい。
技術的な難度を徹底して追求し、新しい地平を開くという
70年代の前衛的手法の典型ではないかと思う(違うかな・・・)。
演奏家の技量も、もちろんパーソナリティの重要な要素ではあるが
難技法を要求するあまりに、奏者の創造性が排除されかかる。
そのぎりぎりのところで葛藤しながら表現の完成度を高めるという
実にストイックで、職人的作風。
作曲、演奏するほうは一種の挑戦であり
演奏すること自体のカタルシスはあるのかもしれないが
今の耳で聴くと、あまり面白くは聴こえない(と思う)。
曲が始まったとたん(初めてだったので)
あ、いかにも!って感じ。
まあ、そういう時代だったのだから仕方ないし
そこを究めて認められて残っているのなら、
それはそれで素晴らしい成果なのだろう。
最後に「アンコールピース的にリラックスして聴いて」という
プッチーニオペラからのアレンジ。
「蝶々婦人」「ラ・ボエーム」「トゥーランドット」からの抜粋。
編曲は彼女自身で、演奏会で披露するのは今日が初めてとのこと。
布を巻いたマレットでアタック音を極力抑えた
にじむような響きを堪能させてくれた。
木を叩いているにもかかわらず
まるで水の滴りのような濡れた響きがあって心地よい。
クラシックの編曲ではあっても
抽象的なモザイク画のようにちりばめられた音のしずくに
目を凝らすと形が浮かび上がってくる
そんな印象があった。
後半の解説の中で彼女は
一般論として、ある意味で崩壊、または
やりつくされた感がある「現代音楽」にも
若い世代の成長で、新しい創造が生まれている、と語っていた。
ここからはあくまでも個人的な感想であるが、
ビジュアル的なデザインを重視する現代にあって
彼女自身、まさに時代が求める表現者のひとりなのだ。
音楽にとって、奏者が男であるか女であるかは関係ない
といえばそれまでだが
彼女が「演奏する」というパフォーマンスの中に
ビジュアル的な「美しさ」は説得力があり、
力があると思うのは私だけだろうか。
自由、開放といいながら必要以上にストイックであった
前衛の時代にあってすら、吉原すみれや高橋アキ、安倍圭子など
奏者としての女性の存在は光っていた。
30年の時間を経て、それが時代の流れとして定着した
ということなのではないか。
昨年、初めて彼女の演奏する『カシオペア』を聴いた時にも
その時間の流れによる変化を、確実に感じた。
「リズムはメロディでありメロディはリズムである」という彼女が
今現在、マリンバを弾くという行為で何ができるのか
「できる限りやってみたい」という言葉に
「ムナーリ・バイ・ムナーリ」の演奏にもみなぎっていた
自由で前向きなエネルギーを感じたのである。
もう終わった、という「現代音楽」の埋もれた作品が
あるいは新しい創造の芽が
猫のごとき優美な巫女(シャーマン)の手によって
息を吹き込まれることを期待したい。
東京文化会館レクチャーコンサート 2nd
「リズムとメロディ」
ナビゲーター&パーカッション:加藤訓子

























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます