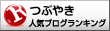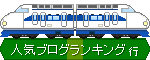今朝の信州は昨夜から暖かな夜、そして今朝の気温は
16度、昨夜から暖房機はお休みです。
今日は、霜降、二十四節気の一つ 旧暦九月中気霜始め
て降る七十二候の一つですが、信州では数日前から一
足早く降霜となっていました。
電信電話記念日
1869年(明治2年)の9月19日(新暦では10月23日)に
東京・横浜間に日本で初の公衆電信線の架設工事が始
められたことに由来する。1950年に電気通信省が「電
気通信記念日」として制定した記念日でしたが、1956年
に現在の名称に変更されました。
KDDIの資料によれば・・・
日本の電話の発端から数えて155年。ケータイやスマホ
での通信や情報交換、人と人を結ぶ通信手段が当たり
前になった現在、電話がどのように身近なものへと変
わってきたのか?初期の電話料金は?、意外と知らない
電話にまつわる歴史の当初について検索してみた。
電話サービス開設当初の加入者はたったの197世帯で
した。教科書でもおなじみ、グラハム・ベルが電話機
を発明してから14年後の1890年(明治23年)に、日本
初となる東京〜横浜間での電話サービスが開始。
明治23年といえば、第一回目となる衆議院の総選挙や
帝国議会が開かれるなど、日本が近代化に向けて本格
的に動き出した年です。当初の加入数は、東京で155
世帯、横浜で42世帯のわずか197世帯とのことです。
日本最古の電話帳「電話加入者人名表」には、省庁
など政府関連施設から、銀行、新聞社、通信社、交換
局など、1から順に番号と加入者名が並んでおり、住所
などの記載はなかった。ちなみに栄えある「1」番は、
東京府庁(現在の都庁)。中には個人名もいくつかあり
のちの内閣総理大臣となる大隈重信、「日本資本主義の
父」と称される実業家の渋沢栄一といった歴史に名を
残す人物名も。当時の電話がいかに特別なものであった
のかがわかる。
電話サービス開設当時は5分で約2,250円だった
明治から昭和にかけて使用された2号共電式壁掛電話機
開局当時の電話代はいくらだったのか? 資料によると
開局当時の明治30年頃、月額40円。当時の物価を現代
に換算すると約3,800倍。つまり月額15万円! 東京市内
(当時)の通話は月額料金を払えば無料だったのだが、
東京から横浜の通話(市外電話)には、5分で15銭(現代
に換算すると2,250円相当)かかったというから、まだ
まだ気軽なコミュニケーション手段ではなかったのだ。
電話から電話には直接つながらなかった時代・・電話
交換手は人気の職業今も昔も、電話の発信者と受信者
をつなげるためには「交換機」が必要だ。現在では、
コンピュータ化されたシステムの登場により発信者から
受信者への接続は自動化されているものの、電話の開設
の初期から自動交換機の登場以前は「交換手」を介し、
手動で回線をつなげていた。
この時代の電話には、まだダイヤルやボタンはついて
いない。電話をかけるには、まず電話機についている
ハンドルを回して「交換手」を呼び出し、つないでほ
しい電話番号を口頭で伝えて通話の申し込みをする。
すると交換手が手動で交換機の線でつないで、通話が
成立するというもの。
ちなみにこの交換手の仕事、海外から輸入された最先
端の職業だったことから人気の職種だったそうで、対応
のやわらかさから女性が多く登用されたそうだ。
日本で電話が生まれて155年 黒電話や公衆電話などから
『電話の歴史』を振り返るKDDI トビラを参照ください
楽しい記事です。










コメント欄はお休みさせて頂いてます