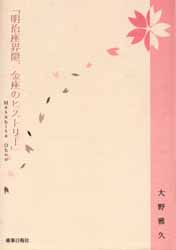 地元に住んでいながら、明治座には行ったことがない。明治座ビルの医者はかかりつけなので月にいっぺん診てもらっているが(故・梅本洋一と同病なり)、明治座の演し物に食指が動かないのは、演劇ファンの偽らざる気持ちだろう。ヘンテコな商業演劇か、細川きよしや石川さゆりのショー、下町の玉三郎だったり、果てはモー娘。だったり韓流スターだったり──。最近はずいぶんと歌舞伎も打っていたようだが、これは単に歌舞伎座が閉館していただけのこと。ようするに節操なく田舎臭い芝居を年中打っている印象である。
地元に住んでいながら、明治座には行ったことがない。明治座ビルの医者はかかりつけなので月にいっぺん診てもらっているが(故・梅本洋一と同病なり)、明治座の演し物に食指が動かないのは、演劇ファンの偽らざる気持ちだろう。ヘンテコな商業演劇か、細川きよしや石川さゆりのショー、下町の玉三郎だったり、果てはモー娘。だったり韓流スターだったり──。最近はずいぶんと歌舞伎も打っていたようだが、これは単に歌舞伎座が閉館していただけのこと。ようするに節操なく田舎臭い芝居を年中打っている印象である。かつて名優の左団次が明治座の座主をつとめ、新劇の父・小山内薫が若き日にこの界隈を徘徊していた時代、そして溝口の『残菊物語』(1939)で神業の領域に踏み込んだと映画ファンなら誰もが認める花柳章太郎がスポットライトを浴びて新派が輝いた時代、川口松太郎が新進劇作家として多忙を極めた時代、明治座はたしかに東京演劇シーンの重要な一翼を担っただろう。
地元の企業・ミツワ石鹸の社主・三輪善兵衛のはからいで、旧・歌舞伎座の座主・田村成義と松竹の大谷竹次郎が芳町(現・人形町)の料亭「百尺(ひゃくしゃく)」で落ち合い、三輪の取りなしで手を握り合ったのは1911(明治44)年のことである。この会合をもって歌舞伎座は松竹の所有物となったのだ。
それよりもむかし、浜町は江戸期、細川家をはじめとする武家屋敷が軒をつらね、大判・小判を製造するための金を陸揚げする港であった。明治維新のとき、この地は新政府によって没収され、井上馨をはじめとする薩長の要人に分割・所有され、彼らは東京(江戸)史上最初の地上げを実行したのである。このあたりの、長州人の金銭欲にかられた一連の蛮行をそれとなくあげつらう筆致こそ、本書『明治座界隈、金座のヒストリー』(薬事日報社 刊)のもっともスリリングな場面であろう。
日本橋、とくに人形町・水天宮前・浜町というこの素晴らしい界隈で生活し、夜ごと食べ歩き、愉しく飲み歩かせていただいている輩としては、三田家と新田家は、いまなお無視できない家である。両家とも中央区を代表する一家と言ってよく、誰もが認める存在である。古くは力道山のデビューも勝新太郎のデビューも新田家との関係なくては語れないし、小津『秋日和』の撮影も成瀬『流れる』の撮影も、三田家の存在なくしてはあり得なかった。フジテレビの女子アナ、ミタパンは三田家の出身であり、彼女の実家は、料亭で唯一ミシュラン三つ星を獲った「玄冶店 濱田家(げんやだな はまだや)」である。この「玄冶店 濱田家」を経営し、現在の明治座をも手中に収める三田家はかつて日本橋中洲の料亭「中洲 三田(なかす みた)」も経営し、そこは『秋日和』『流れる』の舞台ともなったのだ。そんな、この界隈の人間の有象無象を、地元人(著者は浜町二丁目の料亭「島鶴(しまづる)」の出身であり、現在は明治座ビル1階で処方材薬局「しまづる薬局」を経営)ならでは筆致で活写するのが本書だ。
郷土史というジャンルがある。地味なジャンルであるが、柳田國男の本にかぶれたことのある人なら分かってもらえると思うけれど、この郷土史というジャンルの、麻薬のような魔力、本書はその一端にある。このジャンルは、取り憑かれると一生ものである。本書の著者もそうした人の一人なのであろう。









