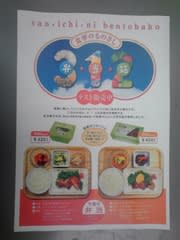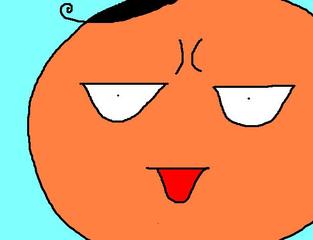野口武彦氏の「鼻と自意識」を読みながら、フルトヴェングラーの交響曲第2番を聴く。
発売された当時買いそびれたCDであった。私はそのころ、バレンボイムとシカゴ交響楽団の相性が悪いと決めつけていて……というのは、マーラーの第5番の演奏を聴いてなんかとっちらかっている印象を受けていたからである。そこにもってきて、フルトヴェングラーの大交響曲とくれば、「こりゃまた散漫な……」と聴かないうちから脳内で何かを聴いてしまったらしい。
今回聴いてみたら、すごくスマートな優しい演奏になっていてよかった。第4楽章なんか、30分かけて緩やかなクレッシェンドをやっているような感じで、油断していたら終わっていた。フルトヴェングラーの自作自演でも、最後は、突然視界が開けたように、金管楽器が殊更虚空に向かって叫んでいるみたいな必死な調子になっているのに、シカゴ交響楽団は最後まで静かな語り口をやめなかった。
野口氏の論文は20代の頃、盛んに読んだはずである。すごい切れ味だといつも思っていたが、今日は、BGMの影響か、非常に静かな語り口に思われた。野口氏の語りは、そっちはそっちで考えてくれと言っている感じがする。こういう語りは口調とは関係ない。高圧的な文体でもそういうことがある。
最近学問面してて厭なのは、私が勝手に「スキーマ疑い系」と括っている言説である。社会学で言うところの「内部観察」にまつわる困難を考察したいところであるが、……私はもっと彼らを唯物論的に捉えることがまず必要であろうと思う。
各人のスキーマを把握しそれを疑え、とは、「常識を疑え」という旧態依然とした、それ自体良くも悪くもない、──どちらかというと人をある目標やイデオロギーに誘導しようとする時の威し文句である──を、現代風に言い換えただけのものではなかろうか。大概、このような概念を振り回す論者は、スキーマに対する疑いはあるが、プロジェクトや政策にたいする盲信がある。すなわち決して懐疑的な人間ではなく、むしろ何かを確信したいタイプなのだ。もしかしたら、そういう自分のスキーマがあまりに強固で分析しがたいという自己嫌悪があるために、他人に自己改造を強制してあるいているのではと疑われる。あるいは、一昔前のフェミニズムの一部のように、あなたは男社会の常識に縛られている、と言えば、相手がひるむので、その隙に自分の見解を押しつけようという作戦なのであろうか?いつも存在するこのような論者に共通してあるのは、ほっといたらドグマに縛れた人間は永久に変わらないだろうという蔑視である。最近は、協働や連携の名の下に、人のスキーマを勝手に理解し介入する(←出来る訳ないけど)、明らかに権力意志に支えられた行為を「支援」という言葉でカモフラージュする輩がいる。彼らが持っているのは「支援」の意志ではなくて何らかの「私怨」だろう。例えば、大学の講義を、自分が勉強するきっかけとか利用できるかもしれない知識を偶然拾ったと思わずに、教授の態度だけを問題にし「あの教授訳わからんこといいやがって、そしていばりやがって」という印象のみを勝手に受け取る。だから、授業で分からなかった「知識」と「相手の人格」が結びついて、いわゆる知を振り回すいやな人間という想像物への反発となる。だいたい、赤の他人の言葉のわかりにくさや態度をなぜそんなに気にしているのだろうか。自分で勉強し直せばすむことだ。
野口氏によれば、さすがに、芥川龍之介はそんな自意識を問題にしていたのではなかった。
他人は単なる他人だ。違う人間同士、簡単にコミュニケーションをとれると思うのは子どもである。無論、コミュニケーションは、ある程度、相手をわかった風に振る舞わなければならない。しかし本当にわかったつもりになっているのは狂気の沙汰である。