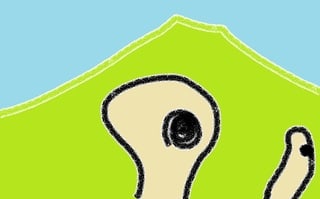

オリンピックが3兆円かかるとか言っていて、もう何が何だかわからない。慶応の先生が中心に調査したところ、そうなっていたらしい。お金を統括する所もなかったし、全てを統括する会議も忙しい素人の集まりで厳密に言えばないに等しい、らしい。これはまったく意外なことではなく明らかに意図的にそうしてると思うんだが、最近の大学や官庁では極めて普通のことだから……。権力がボス(みたいなもの。だいたい一番おおざっぱな会議体のこと多し)に集中すると、中間の権限がほぼなくなってしまうため、それぞれの下部の集団のトップが真剣にものを考えることを以前に増してやめてしまう。部下への指導もしなくなる。(それ以前に、やる気のない集団は、指導能力のある人物を選ぶことがなくなるのであるが。)そうすると、各集団の中のいまいちな能力の持ち主がボスの気に入りそうな手柄を立てようと暴走するようになり、間違いがいろいろ起こってくる。ボス(みたいなもの)はそんな間違いを指示した覚えはないから、もちろん責任は感じない(一人じゃないし)。お役人が一生懸命仕事をするとこうなると、慶応の先生は言っていたが、そうではないと思う。彼らの世界は内部の野心にあふれたポチの扱いをめぐって悩みの坩堝にあるのである。
要するに、下からのまともな反論が面倒くさいからといって、独裁(みたいなもの)をやると、下のポチがもっと面倒くさいことをやらかすようになるのである。
学力テスト?とかでも、学校の先生たちが勝手に競争を始めたとか言ってNHKが批判してたが、普段から文科省の言うことを犬みたいに聞くことを強要しているから、勝手に競争し始めるのである。子どもの教育のことなんか真剣に考えていないボス(みたいなもの)の本心を勝手に読み取っているだけではないか。
教員の世界にかぎらず、人間の見栄の張り合いというのはすごいので、我々は見栄を張るためになんでもしてしまう。しかし、耄碌した人間(みたいなもの)の見栄のために社会が滅茶苦茶になってしまう前に、もう少し考えることは出来るはずだと……思いたいが、よく分からない。

二人の討論をニュースでちょっと見た。大統領選挙は、王様を選ぶという側面があるからね……、議論で負けた勝ったは相対的な価値しかないかもしれない。ヒラリーは有能な長官である。対して、トランプは「不動産王」である。はっきりしていることは、マスコミもインテリも、ポピュリズムを単なる幻想の蔓延だと思っていると足下をすくわれるだろうということである。

最後のあたりだけ見たが――、蚊帳の中の夫婦に猫の声が聞こえてきて、漱石が「小説家になりたい」と言ったのがわざとらしくてよかった。夫婦の絆的なあれはいいから、はやく、下の場面を見たい。
「貴夫が私のものでなくっても、この子は私の物よ」
彼女の態度からこうした精神が明らかに読まれた。
その赤ん坊はまだ眼鼻立さえ判明していなかった。頭には何時まで待っても殆んど毛らしい毛が生えて来なかった。公平な眼から見ると、どうしても一個の怪物であった。
「変な子が出来たものだなあ」
「どこの子だって生れたては皆なこの通りです」
「まさかそうでもなかろう。もう少しは整ったのも生れるはずだ」
「今に御覧なさい」
――「道草」
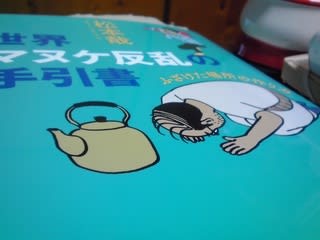
松本哉氏の名前は知っていたが、本は読んだことがなかった。上のものもまだあんまり読んでないが、とにかく、共同体による「包摂」とか言わなさそうなところがいいと思う。マヌケ反乱は、要するに「ものぐさ太郎」のあれということであるな……。大学に行っても、ほんと奴隷みたいなのが威張り腐っているだけであって、奴らまで「包摂」せんきゃならんかと思うとまあ虫酸が走るわけである。たぶんお互いにそう思っているので――、わたくしは大学でマヌケ反乱を遂行中……、という感じに実際ならないところが悲しい。まあいろいろ考えてやってはいるのであるが……。

「燃えよペン」は正統的な私漫画であろうが、それは北野武の「TAKESHI'S」に通じる(違うか)。すくなくとも、我々の業界の(締め切り間際)人も共感できる。もしかしたら、熱血漫画が近代の「内面」を辛うじて支えていたのかもしれない。

「野望の王国」は長いので、読み始めて五年もたつがまだ二巻。はたして、ここに描かれている「権力をめざす」人たちは、狂人であろうか?わたくしは、とりあえずそう疑ってみる必要があると思う。「カッコーの巣の上で」を思い出す。

最近の日本で、壮大に無視されようとしている問題に、好色の問題があると思うんだが、今日、ご飯を食べながら、所謂「渡鬼」というのを初めて観た。おもしろいのは――、それが、泉ピン子などの演技によって、とにかく一族たちの「脳内だだ漏れ」のせりふが永遠に続くドラマだということだ。影が全くない明るい画面のなかで「脳内だだ漏れ」が永遠に続く、――これはある意味、よく言われた「闇をなくした人間問題」の最先端を行っているのではないかと思った。で、その問題と好色の問題はたぶん関係がある。
山本直樹氏の作者解説で、いままで「はまった」本の紹介があったが、これはよかった。
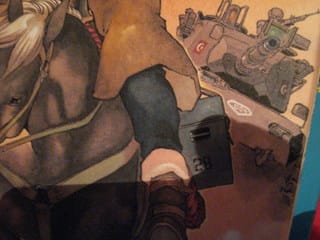
星。段ボール箱の底にあった。安彦良和氏はガン×ムの人だが、そのファーストシーズンに味があるのはこの人のおかげなのであろう。当時の子どもにとって、劇画調でもない、なんというのか、みたことのないタッチのアニメーションだったに違いない。わたくしは確か小1かそこらで観ていない。大学院になってビデオで観たが、おやじにぶん殴られながら巨人に入った例の人の声が、「おやじにも殴られたことないのに」と言っていたので衝撃を受けた。
まさに、これはエディプス的なあれである。
言うまでもないが、星飛雄馬とアムロは同一人物である。声がそうであるという意味ではなく、我々の中では同一人物だということである。
で、ドラえもんや悟空を女性がやっているという事実に、マザコン的なあれを想起せざるを得ない。
関係ないのだが、「グルドの星」を昔読んだ時に、BGMとして小倉朗の「舞踏組曲」かなんかが脳内再生されたのを思い出した。確か、ガ×ダムの音楽を三枝成彰がやってたことがあったと思う。「何かおかしいな、ださいな」と思った覚えがある。誰か研究しているのであろうが、戦後、大量にかかれてきた日本人作曲家によるクラシック風の劇伴の奇妙さは心に引っかかる。まるで、四分音の音楽を聴いている感じすら私にはあるのだ。そういえば、中学の頃、吹奏楽の課題曲になっていた「宮本武蔵」のテーマはチャンバラ劇風でかっこよかった。前期の授業でも問題にしたが、西部劇やチャンバラ時代劇のテイストが七十年代以降どうなっていったのかは興味深い問題である。例えば、不人気だった「グレートマジンガー」は、前作に比べて、ロボットやパイロットを剣豪として造形しようとする企図があったように感じられる。しかし当時のガキんちょはもうそれを理解できない。×ンダムにもそんな企図が残っているはずだが、それがそう見えない理由の一つに、安彦氏の絵もあると思う。三枝氏の音楽は、芥川氏らとの合作「交響組曲東京」なんかを聞けば、ほかの戦後を彩った作曲家たちと比べて明らかに新しさを感じるものであったが、彼の心に描くものは、失われた過去の何かだったのかもしれない。だいたい、考えてみりゃ、劇画とかガン×ムもそういう流れの一部だったのであろう。youtubeで、上の「宮本武蔵」の動画を一部見たが、やっぱり何か既に決定的に失われたものがあるというのが実感である。本当は、吉川英治の原作に既にそれがあるのであるが……。当時、中学生の私にはそんな事情がわからなかったが、西部劇世代の父親たちには分かっていたはずである。
そういえば、三枝氏もヤマトタケルかなんかをオペラにしてるし、安彦氏も古代に拘っている。案外彼らは、フロイトが心の中にギリシャを見出す如くやっているのかもしれない。しかしここでも私は「何かおかしいな」と思う。この前、ナタリー・ポートマンの「ブラック・スワン」を観て、やっぱりあちらの文化の悪魔的な内面の執拗さに警戒感を抱いたためかも知れない。

特撮とかガンダムとかエヴァンゲリオンのパロディはマニアたちを楽しませるばかりである。いっそ、「ホタルノヒカリ」とか「真夏の方程式」とか、なんかいろいろあるだろうほかにも……。ニューウェーブたちの挫折をもう一回味わうことになるかもしれないが……。しかし、問題は、特撮とかガンダムとかエヴァンゲリオンのパロディはトニーたけざきのような画力が必要だが、綾瀬はるかとか福山雅治のパロディには画力が必要ではないような気がする、この点である。

安彦良和の「ジャンヌ」は、ジャンヌダルクの幻に取り憑かれたかして、フランス王のための立ち上がる少女の話。安彦良和の作品はそうたくさん読んでないが、「選ばれし者」の物語が多いのではないかと思う。だから、主人公が苦労しても安心して応援していられる。わたくしが心底恐ろしかったのは、北野武の「アキレスと亀」みたいな作品である。主人公は絵が好きだ、が、いっこうに芸術家として浮かばれない。最後まで浮かばれなかった。おそろしいのは、彼には苦悩がないことだ。親、絵が好きな仲のよいおじさん、芸術家の仲間が次々に事故に遭ったり自殺したりする、娘は売春して死亡、美人の妻は出て行く。炎の中で絵を描いて死にかけた主人公のもとに、なぜか妻が帰ってきてハッピーエンド?。ついに亀にアキレスが追いついたのである。やはり、芸術家たるもの、欲を出してジャンヌみたいに聖人になろうとしてはいけないのであろう。途中で降りたら、世間が追いつくにせよ、追いつかれることによって死んだも同然になるにせよ、――どこまで最後までやり通すつもりだったか疑念を湧かせるというものだ。芥川龍之介や三島由紀夫にそう申し上げたい。
とはいえ、別の意味で恐ろしいのは、江藤淳であろう。江藤淳の死については、どうつっこんでいいのか、みんな困っている。さすがである。













