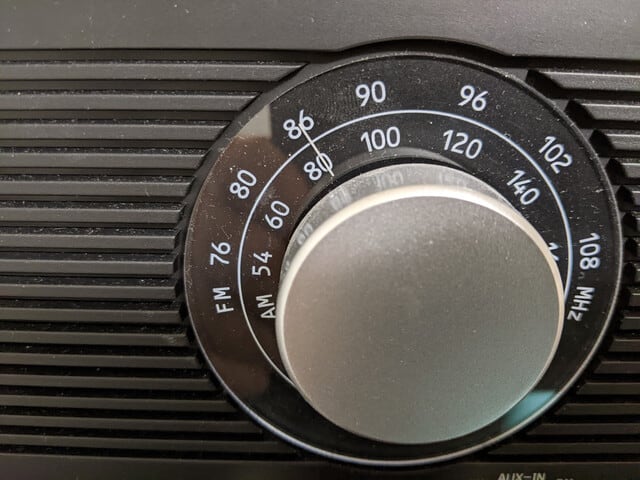ひととせ、入道殿の大井川に逍遥せさせ給ひしに、作文の船・管弦の船・和歌の船と分かたせ給ひて、その道にたへたる人々を乗せさせ給ひしに、この大納言殿の参り給へるを、入道殿、「かの大納言、いづれの船にか乗らるべき」とのたまはすれば、「和歌の船に乗り侍らむ」とのたまひて、詠み給へるぞかし、
ひととせ、入道殿の大井川に逍遥せさせ給ひしに、作文の船・管弦の船・和歌の船と分かたせ給ひて、その道にたへたる人々を乗せさせ給ひしに、この大納言殿の参り給へるを、入道殿、「かの大納言、いづれの船にか乗らるべき」とのたまはすれば、「和歌の船に乗り侍らむ」とのたまひて、詠み給へるぞかし、
をぐら山あらしの風の寒ければもみぢのにしき着ぬ人ぞなき
申しうけ給へるかひありてあそばしたりな。御みづからものたまふなるは、「作文のにぞ乗るべかりける。さてかばかりの詩を作りたらましかば、名のあがらむこともまさりなまし。口をしかりけるわざかな。さても殿の、『いづれにとか思ふ』とのたまはせしになむ、われながら心おごりせられし」とのたまふなる。一事のすぐるるだにあるに、かくいづれの道もぬけ出で給ひけむは、いにしへも侍らぬことなり。
漢詩・音楽・和歌と三艘の舟をつくってスペシャリストを乗せようという道長の魂胆はよくありがちな為政者の単細胞である。芸術の才をまさに役に立つ分野として考えているのであった。三つ出来る奴がいるに決まっているではないか。考えてみると、大谷選手の二刀流は、分業制が進んだベースボールに、自分はベースボールそのものができます、みたいなものである。野球の世界というのは、他の世界と同じく派閥のある世界で、自分の仕事におさまることが重要であるようだ。それにデータや賞が給料にそのまま反映されがちな競技である。それはもちろん、選手達自体の成熟とは関係のないものだ。
そもそも、我々は何回も成熟を崩壊させながら変容していく生物だ。
起きてからライヒやアダムスを聞いてて思ったんだが、わたくしにとっては青春の音楽だったにすぎない。これらをおもしろく聞く成熟が嘗てあったと言うことである。そういえば、最近、若手の短歌集を乱読してたら、ひとつまたパーツが埋まった感じがする。なるほど、そういうことだったかという感じだが、彼ら書き手が若いにもかかわらず、わたくしにとって、それは中年としての成熟に関係があったということである。
「カルメン純愛す」のなかで、高峰秀子氏が友人のストリッパーと彼女の赤ん坊すてちゃおうよと言って、捨てたあと蓮っ葉な歌をうたいながら国会前を歩いて行くところがいい。「どうせ日本はままならぬ~。へなちょこ野郎はけっとばせー チャー(金管)」という音楽がナンセンスですごいしそれなりに成熟しているのである。しかし、この子どもを捨てるという現実主義とナンセンスさは、高峰秀子演じるストリッパーが前衛画家に恋をして崩壊して行く。
むかしみた『小さき勇者たち~ガメラ』は、ガメラや主役達以外、逃げる群衆とかが意外に名演という、ガメラは一般人、特にガキの心に遍在するというテーマを地で行きすぎると妙なことになるみたいな映画であった。大人のマニア達が怪獣映画を難しく残酷にしていることへの抗議であったかもしれない。特撮映画やドラマに出てくる子供というのは大概演技も下手で、そのわりに大人が思いつかない良い計画を思いついたりする役回りなので、――思春期通過してから口を開けガキがと思わざるをえないのだが、やはり怪獣でドタバタやっていることじたいに、戦争ではない、子供的なものの存在が含まれていてさけて通れない。とりあえず、怪獣を子供に返してあげることは重要である。大人はもっと違うことで一生懸命仕事せにゃ
大人が子どもをきらきらした瞳がーみたいに、馬鹿な大人の範疇に取り込んでしまうのであれであるが、子どもをそれとして尊重するのは大人に対する教育的にみて重要である。中学生らしさとか大人らしさとかを主張する大人があまりに馬鹿が多かったせいで、おかしいことになってしまったが、子どもっぽさや青年っぽさとか中年親父っぽさなどはお互いに必要なのである。それを制度がダメみたいな理屈で全否定して出来上がったのが、子どもから老人まで揃いも揃ってなんのあれもないだめな大人みたいな人間なのである、もはや波瀾万丈でなく砂漠のような人生と世界なのでつまらない、でもう死ぬしかないとなる。多くの人が経験することであろうが、思春期前の子どもとしての成熟、思春期としての成熟、青年期の成熟、壮年期の成熟、クソ親父としての成熟などなど、その時期それぞれの生成の仕方があり、その頂点で雪崩を打って変容するのが我々の人生だ。それを認めた方が気が楽だ。
みごとにインテリジェンスな女の人が子供っぽいあほ男の世話をしている例があるけれども、小学校高学年とかに初恋の相手が同学年の思春期前のアホザルだったりすることが関係あるのではないだろうか。自身の思春期前の成熟が成熟した目で見出すのが、アホザルの良さなのである。で、相手が思春期に入って更なるクソザルに突入していくときにも、その成熟への未練が残っている。彼女はそのままその未練を引き摺りながら大人になって行くのであった。
一方アホ猿の方も未練はあって、その成熟した女性的なるものへに対してアホザルに過ぎなかった未練である。それは一度雄ザルになってしまえば忘れてしまうのが普通なのであろうが、それを忘れられない輩もいて、それが芸術家になってしまったりすることもあるであろう。この人達の特徴は反復である。作品が、いちいち自らの死を体験させるから、もう一回人生が必要になってしまうのだ。上のような成熟の反復が許されない。
例えば、宮崎駿がずっと引退したかったのにしてないみたいなことがほほえましく語られたりする。ほんとわたくしみたいなだめな奴が言うのもなんだが、1、みんなが観てくれなかったらどうしよう→死にたい。2、もうこんな面倒な仕事はしたくない→死にたい。3、うまくいかなかったぞ今回も→死にたい。などの感情を社会的言語になおすと「引退したい」みたいなことになるのではないかと思う。ものを書く人や作品をつくる人は達成感と希死念慮が同時に来るようなひとが結構いる。作品に魂吸い取られるし体力限界に来るせいであろう。しかし、まあ、この人たちは作品に人生を預けて死ぬ癖がついているだけ救われている部分もある。そんな重大なことを経験するせいで、根本的に他者が消失しているからである。
そうではなくて、他者だけを相手にせざるをえない人もいる。例えば、お笑いの人とかに反権力などを求める人もいるが、人を笑わせる(というより、その舞台に立つため)にはどうしても聴衆のセンスへの接近が必要になり、マスコミに出てる学者とおなじで反権力というより、ボケとツッコミをみずからのうちに体現した半権力みたいな人になるのはある意味当然である。ちなみに教師もそうである。北野武が、お笑いではなく映画監督になったのは、こういう危険性を知っていたからではないかと思う。そういえば、松本人志はそれに失敗したような気がする。「大日本人」では、迫害される大日本人の姿がアメリカからきたウルトラマンもどきたちとの漫才的コメディにかわる。これは、同世代の庵野秀明たちと同じ幹から別れたあり方であって、自らの植民地性・空虚性をどう扱うかの違いでもあるが、多くの観客を相手にすることを相対化できるかの違いでもあった。