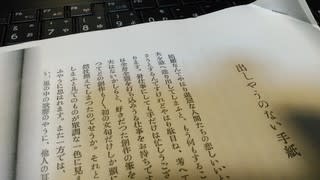「ジュラシック・エクスペディション」を観たのだが、これがなかなかの傑作であった。一般常識からいうと、とんでもないB級映画であることは明らかで、ネットでは「映画学校の学生でももっとうまくやるのでは」とか書かれていたが、確かにそうかもしれない。
しかし、わたくしは、とりあえず作品をとんでもなく褒めてみるというところから始める男である。
この映画は、これからのトレンドである「脱欲望」の映画である。
冒頭部分、「スタ-ウォーズ」よりも矮小で「レッド・ドワーフ」のそれよりも軽そうな宇宙船が宇宙を飛んで行くシーンから始まるのであるが、とにかくシーンの作り方に快感がない。そして、なんの変哲もない「題字」。
で、宇宙船の中では何が行われているかというと、中途半端なひげ面男と微妙な美人のベッドシーン。これが、二村ヒトシ(『欲望会議』)のいうところの、今はやりの実用的ザッピング●ッ★◎シーンかと思ったが、ザッピングにもなっていないのだ、途中で柔道シーンに見えてくるのだから。で、事を済ませた後よく見たら、女性が予想を超えて美人ではない。
なぜか、ある惑星に調査のために送り込まれるそのひげ男。着いてみると、どうみても地球である(たぶん、地球で撮影されたなっ)。しかも、砂漠地帯の割には、向こう側のアルプス山脈みたいな山々が妙に綺麗。これは案外、傑作なのでは思い、筋がクソでも買う価値があるのではと錯覚しそうになった。なにしろ、スターウォーズにしろ、スタートレックやゴジラにしろ、美しい風景はあるが、案外美しい山脈が描かれないのだ。ニッチなところついたすばらしい映画だ。――それはともかく、突然巨大な恐竜の石化した物体を発見。で、地震とかがある。巨大ミミズが地面から出てきた(が、以降消息不明)。で、気がつくと、砂漠で擬態化している恐竜が突然襲ってくるのである。その恐竜と言えば、ジュラシックパークででてきた小さな肉食恐竜に襟巻きをつけて、頭部をエイリアン風にした妙な人たち。しかのみならず、この惑星の水を飲むと人間は発狂してしまうのだ。で、……
草薙大佐にちょっとポテチを多く食わせたかんじの微妙な美人のアンドロイドとひげ男が頑張って惑星調査を完遂しようとするが、案外あっさりとアンドロイドを助けてひげ男の方が殺されてしまい、ラスト一分で急に主役交代。アンドロイドと恐竜の対決だ!
対決せず終わり。
なんか微妙な大音量のロックロールが鳴り響く中エンドロール。
つまり、この映画は、すべての要素が回収されずに、まさにポストモダン的に「脱臼」や「宙づり」で出来ているようにみえる。しかし、テーマは明らかで、優秀なアンドロイド(AI)がトラウマをかかえるひげ男を癒やして人間化させる愛を描いたものである。つまり、AI讃歌、癒やせよ乙女的「絆」みたいな愛の讃美、これからの介護や治療の可能性を称揚した作品なのだ。人間同士の性行為はもう時代遅れた。ジェラシックパークの殺戮で興奮するのは変態だ。美少女をだして戦わせるのもけしからん。宇宙船がかっこいいとか、男根主義のマッチョイズムだ。美男美女とかが時代遅れだ。この映画に、セクサロイドとかを期待したそこのあなた、速やかに呪われよ。
――まさにそれは超ポリコレ映画であった。「超」ポリコレではなく。