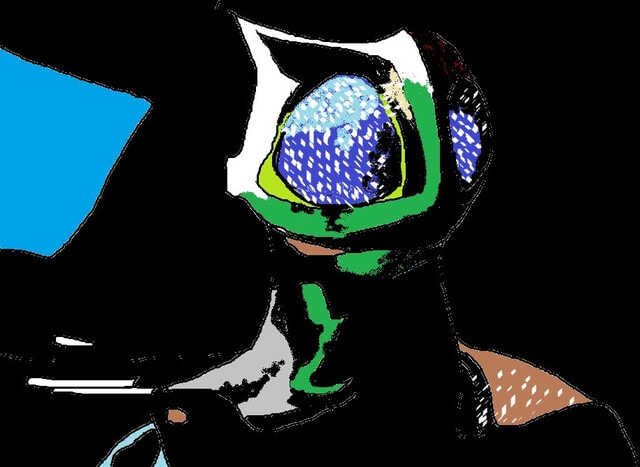ある夜、風あらく雨降りて、人音まれなる時を見合せ、乙女が案内をして、男をつれて、我が親のかたに立ち入り、夫婦のねられしうへに、畳を置きかけ、このくるしみの内に、少しの貯べ物を盗み、帽づたひに、にげ行 きしに、この大悪、いづくまでか遁がるべし。踏馴れし道筋の岩も、人影と見えて、心のやるせなく、知れたる淵に飛 び入り、男も女も、眼前に恥をさらして、葛屋の名をくだ しぬ。
「娘盛りの散る桜」もすさまじい話で、娘の四人ともに懐妊して死亡し、五人目を出家させようとしたら盗賊の嫁になってしまい、実家に盗みに入る。しかし、山道で錯乱して淵に飛び込んでしまった。
この五人目だけがなんか突然の悪行のようにおもえるが、四人目までも懐妊して死んでいて世間的親にとっては一種の不孝みたいなものであったであろうから、あまり突然とはいえないのかもしれない。いずれにしても、何が不孝で何がそれを事件として顕すのかはなんだか分からないわけである。この世の中はいつも突然に不孝が起こってしまう。原因があったとしても結果は偶然に見える。だからこそ、語り手も最後の娘の所業を「大悪」と呼ばなければならない。しかしそれだけではなにかおちつかないので、最後には「恥をさらし」「葛屋の名」を汚したと世間を味方につけている。しかも「晒葛屋」の洒落でもあることで、まじめな因果の議論を避けているようにも思える。いろいろ、我々は親不孝なことを起こしてしまうわけだが、何の因果かわからない。しかしその不安定さを口に出せば、その孝行の道徳なしで世の中が保てるのか、もともとかくもめちゃくちゃな暴力的なわれわれなのだぞ、という世の中からの呼びかけに答える勇気を出さなければならなくなる。
大河ドラマで巴御前を演じた秋元才加氏は、幼い頃、日義村の旗揚げ八幡宮に来ていたそうである。氏は「何の因果か」と言っており、実際は氏が巴御前を演じたことによって事柄の同一性が生じたにすぎず「因果」ではないのだが、――もうそういう同一性を因果と感じる我々の感情がある限り、旗揚げ八幡の場所が万が一でっち上げであってもどうでもよいといえばよいのだ。我々の感じる「因果」というのは、どちらかというと、こういうフィクションかもしれないものの伝承の動力なのである。我々のアイデンティティなんか、たいがいそういうものでできあがっているに過ぎない。だから、自己肯定感なんかは、歳をとらないと生じない、「何の因果か」という出来事がないと生じないのである。
そしてその因果は、西鶴が描くようなひどい出来事によって過去から何か因が回帰してるように感じることによって生じる。大概は、人生すべての否定されたすがたの言い換えなのである。