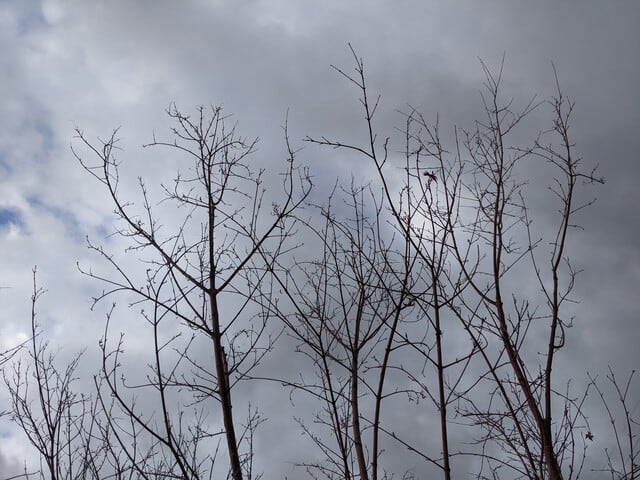今年は読んだというより書いた年だったのでまったく頭が働いた気がしない。
1、マルクス・ガブリエル他『未来への大分岐』……はじめはこの本についての評論をやろうとしてたのだが、途中で挫折。この本を読んで勉強になったとかいうてるひとにわたくしはいろいろ質問がある。
2、清水高志『実在への殺到』……これはかなり細かく読んだ。編むように書くという書き方があるのだという実感する。
3、井上弘貴『アメリカ保守主義の思想史』……井上氏は同じ世代であるためか、似たような変遷を辿っているように思った。感覚的に分かることをちゃんと説明的にするということはいつも大事。
4、藤野裕子『民衆暴力』……この本もある程度かなり前から構想はあったと思うのだ。それが言葉に出来るようになるまでに時間がかかる。井上氏の場合もそうであるが、現実が追いつかないと書けないこともあるのだ。
5、岩田健太郎『新型コロナウイルスの真実』……以前から有名だったが、コロナで一段と名が高まった人のひとりである。この本自体はそれほど感心したというわけじゃないが、
6、宇佐見りん『かか』……若き天才として評判になったので、わたくしも読んでみたぞ。わたくしも歳をとったのか、本文中の「『万年喪女にやさしくないTLやめような』」という部分が、「『万延元年のやさしくないOTLやめようかな』」と見えてしまって人生を感じた。
7、『枕草子』……随筆?みたいなものとしてはやはりすごく突出しているじゃないかと思った。研究もある程度あさってみた。
8、『土佐日記』……イメージよりだらだらした話だと思ったが、紀貫之の歌なんかもよくよく調べてみるとやっぱりすごいらしいので、油断は出来ない。
9、ブリュノ・ラトゥール『諸世界の戦争』……なんか名人芸という趣さえあった。
10、小林秀雄『本居宣長』……小林を読むこつは、小林のあとまで考えなければ小林の言いたいことはわからないということを自覚することだ。西田幾多郎も似たところがあるが、示唆のレベルが思いつきに近くても本質を射貫けばそれなりの説得力がうまれる、という書き方をしている。正にエビデンスなしという反科学をやっているところがあるのだ。逆に、吉本隆明なんかは、本質を外れてもエビデンスを出してくることがある。彼の場合は、狙いがはずれていても、狙おうとする心が正しければ正しいという感じでやっているのであった。これは本質的に共感を得ても読者にわかりにくいのが現実である。今年は、演習で江藤淳をやったが、江藤淳は小林の「本質」を、本当は読者に存在している「コモンセンス」に置き換えた。だから、読者は江藤淳の言っていることは先験的に本当は分かっているはず、ということになる。これは吉本以上の共感よりも、先取りされた共感であり、危険であった。江藤淳は犬が大好きだったが、江藤淳の読者には本質的な意味で犬がいる――ということになるからである。柄谷行人は、吉本よりも江藤淳の書き方と思想を選択したところがある。
最近は、福田和也も読み直しているのだが、――彼が大活躍している頃、大学院生の私が直観したように、文芸時評をやっている暇がほんとうはあったのであろうか、という感じがしないでもない。ほんとは絓秀実氏辺りにかわりにすべてやって貰いたかったのではなかろうか。
『夜明け前』を再読し損ねたことが残念だ。