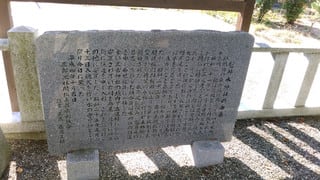古本屋で『音楽藝術』の1954年5月号(ショスタコヴィッチ特集)を見付けたので手に入れた。
1954年とはどういう状況かというと、目次の裏の「音楽会一覧」を見ると、N響定期(カラヤン指揮)、ハイフェッツV独奏会、バックハウスP独奏会、安川加寿子P独奏会、近衛定期、とか、すごいぞ、なんだか全部行きたいぞ。最後の「楽壇抄」をみると、ミトロポウロスの再契約、コプランドの新作オペラ初演、フルトヴェングラーとベルリン交響楽団の訪米、ハワイでベート-ヴェンの第九交響曲の初演、ヴィーン国立歌劇場の復興、ゲオルグ・ゼルのメトロポリタン歌劇場の辞任、など、今と表記が違うのが面白いが、とにかくコープランドやフルトヴェングラーが現役だ。(後者は間もなく急死)
そして、ショスタコーヴィチ48歳ぐらい。当時、交響曲第10番を発表したばかり。当該号の付録には、「森の歌」が付いている。
巻頭に「デ・ショスタコーヴィチ」の「平和のためにたたかう世界の進歩的音楽家たち」という、いま考えてみりゃ本人ものかどうかかなり怪しい論文。オネゲルとか、ヒンデミット、ジョルジュ・オーリック(!)とか、ロジャー・セッションズ(!)を、形式主義の誘惑に負けた者達として批判している。対して、バーナード・スティーヴンスのカンタータやアンジェル・パフヌニック、クラウディオ・サントロの交響曲とかを褒めている。この人達の作品は、最近はCDもでてある程度知られるようになってきたし、すごく粗雑な比喩を使えば、――この間の偽楽聖の曲みたいな祝祭的で劇的な作りが再評価されている気さえするが、――この当時は、まだまだ「ブルジョア音楽に対抗する」現役の音楽だったのである。この論文は、プロコフィエフの交響曲第7番がアメリカの批評家に貶されたことに憤ってもいる。タコさんはついでに「平和の守り」や「戦争と平和」なども褒めているんだが――。確かに、後にでたヴォルコフの『証言』のなかでも、プロコフィエフの第7番を彼は褒めてた。ただ、「戦争と平和」については貶してた。この点が、この論文とは違うね。
で、面白いのは、続く塚谷晃弘や園部四郎の論文であり、ショスタコヴィチに対して、ソヴィエトの方針によって鍛えられ更に発達中の作曲家であることを、なんだか妙な上から目線で激励している。ありゃりゃ、という感じがしないでもないが、ある意味、同時代人として現役の議論をしている自負みたいなものも感じる。これは当時の文学にも感じることですね……
そして一番、ある意味すごい緊張感が感じられるのが、戸田邦雄と原太郎と深井史郎の鼎談「ショスタコヴィッチとソヴィエト現代音楽」である。これは、「森の歌」の評価を巡ってはじまっているが、そのうちタコの評価はどこへやら、例の「形式主義」をどうとらえるかで、左翼の原と戸田・深井が激烈に激突。附記で、深井史郎が、戸田君の言葉に目を開かれたこともあった、この座談会で解決できなかったことについては、改めて本誌に書きたいという「欲望」があるぞ、と、原を無視した上で宣言する始末。今から見ると、すごくおおざっぱなことを言っているような座談ではあるのだが、果たして、ソ連の生み出す芸術は自分たちにとってどういう意味をもつのだろうという切迫感が全員にあって、それはそれで面白い。これはソ連のイデオロギーをどう考えるかという問題ではなく、プロコフィエフやショスタコヴィチみたいな音楽がなぜ創れちゃうんだろうという、焦りとも怒りにも似た感情から来るものだ。原だけではなく深井や戸谷にもそれはあったはずなのである。ソ連の存在は単なる制度の違い、政治的イデオロギーの問題ではなかったのだ。こういう状態だから、このあと、日本人の作曲家達は、様々な対立をしながらも結構いい音楽をつくりだしたのだと思う。
申し訳ないけれども、北朝鮮や中国からノーベル賞やすごい音楽が出てくれば、今の世界の空気は一変する。いま、世界がごたごたしているのは、主に中国人(最近は北朝鮮も)が、自分たちの予想を超えて頭がよいのを目撃したことからくる焦りが原因のひとつだと思う。政体がどうあろうとも、頭のいい人間はいるのだから、当たり前なんだが、それを認めがたいほど、「科学(ここではほぼ「制度や権力」と同義である)による人づくり」みたいな腐った発想がアメリカや日本では蔓延している。坂口安吾が言っているように人文学では当たり前であるが、科学においてさえも、「科学」に対する叛逆にしか新たなものの創出はありえない。
日本では、――様々な改革の成果を自慢するボスの下で、様々な人たちが病気になったり死んだりしておる。手前は指示を出しているだけであるから実感はないだろうが、その尻ぬぐいで大惨事になっとるやないか。大学の改革自慢なんかほとんど嘘である。ただ、嘘が通用するのはテレビと新聞と会議ぐらいである。全く恥さらしもいいとこだ。国政も嘘ばっかり。権力を握るタイプが嘘つきタイプなのでは必ずしもない。権力というものは、叛逆を嫌う、つまり下々が自分の言うことを聞いておらず、つまり成果も上がっていない時に、「自分が正しい」と自己暗示をかけなくてはならなくなる。だから、その「正しさ」が自然に、客観的には嘘になりがちになるに過ぎない。すなわち、彼は最後まで自分の「正しさ」を疑えない、権力というのは必ずそういうもんなのである。したがって、選挙制度の欠陥で、たまたま首相の座に就いていたり、少人数の精鋭(笑)のなかでリーダーに選ばれてしまったりするほど、彼が嘘をつくようになるのは必然である。権力を持つとは制度を統べることだが、――人間の独創性というのがそういう制度を食い破ってしか出て来ないのがなぜ分からないのであろうか。権力者が仮に頭がよくても、絶対にそうなのである。(9月29日附記:橋下徹が、激しい選挙戦のなかで議論が起これば、前より政治はよくなる、最後は国民の判断だ、とか――今よくある一見まともそうな哲学を披露していた。小池百合子の「アウフヘーベン」もそうだが、こういうエセ弁証法的思考が間違っているのは、最近の日本の体たらくを見りゃわかる。弁証法みたいなものがヤクザなやつらの暴力として機能するのは、――結局議論をしときゃある地点で多数決とか小池とかのガバナンス的暴力を発動してもよいことになっているからである。つまり議論をすることが暴力の一部として機能している。こういう擬制は、国政だけでなく、我々の周囲のあらゆるコミュニケーションに見られる。欠けているのは、そういう擬制に対する叛逆――「議論」になるようなレベルとは異なる言語や表現――である。)
とはいえ、「希望」もある。為政者達が調子に乗って嘘すら付かずに、脳内だだ漏れでしゃべり始めたからだ。「日本をリセット」とか頭がおかしいのではないかとも思うが、我々は屡々そんなことを夢想したことがあるであろう。為政者達が我々の先陣を切ってくれている。我々も嘘をつく必要はなくなったのかもしれない。
――しかし、そうなっちゃ、みんな地獄に落ちるね……