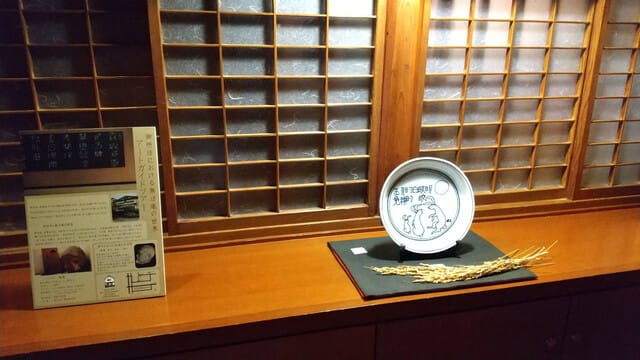「まづ年は十五より十八まで、当世顔はすこし丸く、色は薄花桜にして、 面道具の四つふそくなく揃へて、目は細きを好まず、眉あつく、鼻の間せはしからず次第高に、口ちひさく、歯並あらくとして白く、耳長みあつて縁あさく、身をはなれて根まで見えすき、額はわざとならずじねんのはえどまり。首筋立ちのびて、おくれなしの後髪、手の指はたよわく長みあって心薄く、足は八もん三分に定め、親指反つてうらすきて、胴間つねの人よりながく、腰しまりて肉置たくましからず、尻付ゆたやかに、物越・衣装つきよく姿に位そなはり、 心立ておとなしく、女に定まりし芸すぐれて、よろづにくらからず、身に黒子ひとつもなきをのぞみ」とあれば、「都は広く、女はつきせざる中にも、これ程の御物好み稀なるべし。
「まづ年は十五より十八まで、当世顔はすこし丸く、色は薄花桜にして、 面道具の四つふそくなく揃へて、目は細きを好まず、眉あつく、鼻の間せはしからず次第高に、口ちひさく、歯並あらくとして白く、耳長みあつて縁あさく、身をはなれて根まで見えすき、額はわざとならずじねんのはえどまり。首筋立ちのびて、おくれなしの後髪、手の指はたよわく長みあって心薄く、足は八もん三分に定め、親指反つてうらすきて、胴間つねの人よりながく、腰しまりて肉置たくましからず、尻付ゆたやかに、物越・衣装つきよく姿に位そなはり、 心立ておとなしく、女に定まりし芸すぐれて、よろづにくらからず、身に黒子ひとつもなきをのぞみ」とあれば、「都は広く、女はつきせざる中にも、これ程の御物好み稀なるべし。
あまりに好みがうるさいといっても、ここまで分解して記述できるのがすごい。東浩紀氏の『動物化とポストモダン』のなかでふれられていた萌え要素なんかおおざっぱすぎて話にならない。東氏がこれを出した頃、日本文学の院生室では、東氏は好色一代なんかとかの時代に帰りたいのかとか言う人もいないわけでなかったが、東氏の言いたいのは要するに空中分解しはじめている我々の人生への危機感であった。
最近の『訂正する力』なんかも、東氏が一生懸命人生の話をしているのに、読者は仕事やイデオロギーや文化のことだと思ってしまうのであった。二項対立の喧嘩地獄ではなく、幻想の訂正をととく東氏に対して、未来と希望を感じるみたいなのは読者の感想としてはありだとおもうが、著者としては「持続の絶望」というか「絶望の持続」は人生でありうるかみたいなことを言いたいのだ。しかし、まあ、「もっと深く絶望せよ」みたいな批判ばかり東氏に投げつけられているようでもなさそうだから、世の中、大江健三郎の頃よりは進歩したということにするのもあり得る「訂正」かもしれない(棒読み)。むろん、もっと事態は絶望的なのである。なぜかというと、東氏が少し希望をもっていたインターネットが、東氏が期待するコペルニクス的な転向をおこすべき「情報」をもたらすものでさえなくなっているからである。
いまだに情報の解放というのは本によってしか本質的にはなされていないような気がする。なぜネットではそれがいまいちで、雑談にしか成っていないのか、人類はよく考える必要があるのだ。やはり解放されるべき情報は情報ではなく幻想としての「物」なのである。『チ。』第6集を読んでそう思った次第で、もしかしたら、デジタルコレクションも論文のPDF公開も中世への逆行かもしれない。感覚としてはそんな気がする。すべてが情報公開の元に明らかな世界は、すべてが神のもとに善であるべきと考えられていることと何処が違うのだ。我々の生はそもそも明らかではないのに。
表面的には訂正の学であるところのサイエンスも、ルネサンスに於いて、忘れられたものが想起されてこそ新たな人間的存在であったことをわすれると、まあただの国家を支える神学なのだ。いま、それをつかって人間を焼いている。ひとつの方向性が支配的になると、2・3世代に影響がおよぶのが普通だと思ったほうがよい。現代はおそらく長い中世のはじまりである。
まあ普通に国のために殉死しそうなわれわれであり、どうみても解放されていない。
発達障害だコミュ症だ何だいろいろいうけれども実態がいまいちよく分からんし大概な人にそういう部分はあるが、品性下劣とか人を手段として使うやつとかそういう輩の方がどうみてもまずい。そろそろ病名がついて、またみんなある程度は品性下劣とか言い始めるかもしれんが、彼らを人間として裁けるのは文学や思想であって、サイエンスや法ではない。品性や人間を手段とみる領域は幻想の領域でこれを裁けるのは幻想だけである。
マルクス主義者達が勘違いしていたのは、幻想の領域の基礎付けが存在すると思ったことである。それは基礎付けではなく、幻想としての基礎付けである。黒木華がでてた映画「小さいおうち」では、倍賞千恵子が「戦争っていったって最後当たりまですごく平和だった」みたいなこと言いっていた。確かにああいう感想は当時多く存在したと思う。特に、この人物がいたようなブルジョアジーの世界では。しかし、あの役の世代は戦争に対してはちょっと若く、彼らの青春を奪われたみたいな恨みはすごいから目立つが、彼らを食べさせて育てた世代は恨み以上にいろいろあったから戦後もわりと黙ってたと思う。この沈黙による厭戦気分というアンヴィヴァレンツが、幻想としての基礎であったと思う。
小澤征爾が文革後の中国でブラームスの二番を振った番組を先日やってたが、心を打たれた。わたくし、当分の間、ブラームス信者に生成することにしたが、満州生まれの小澤も多くは語らず、満州国に夢を持った親父は死んでもう語ることはなかった。この沈黙の言葉は吉本隆明のような罵倒ではなく、非転向の平和主義となる。
そもそもプロレタリアートという存在にしてからが、なにか理念から眺められた誤解に基づいていた。だからマルクス主義者たちも市民主義に転向できたのであろう。戦前のプロレタリア文学には様々な意見があるだろうが、小学校もろくに行ってない祖父や祖母の世代には鋭利な唯物論者ぶりがあり、当時の為政者達の一部が心底びびったのも分かる気がするんだな。戦後の唯物論者達のどことなく夢心地な感じがなくて、鍛え上げられた鉄のような、というのが誇張でない感じがする。以前柄谷行人が、戦後の「なんでも迷信」みたいな風潮が自分に影響を与えていると言ってたが、これがわたくしの父とか母の世代のある種の世代的制約で、だまってしまったその親の世代にあった恐ろしい合理的な唯物論を忘れたところがあるわけだと思う。
あっち側ではなくこっち側で働け、みたいな脅迫の論理で、人に対するやつがこれほど多いのかというのが、大人になってからの感想だが、こういうものに対する抵抗が結果的に実現されるのがその唯物論である。