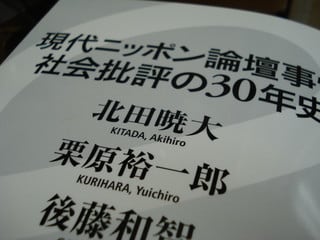「一般の方が捜査の対象になる事は、ぜっ・・・、対象になる事はありません」
といってしまった我が首相ですが、それはそうだろう。一般の方という妙な人たちが何処にいるのかわたくしに教えてほしい。たぶん、この国には一人もいないはずである。
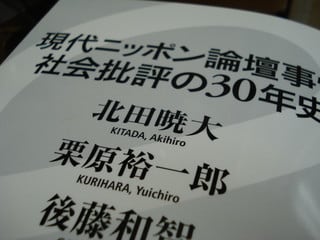
今日は出来心で上のようなやくざな本を読んでしまったのであるが、こういう本も大概、「『一般の方』というものがわかっていない浮世離れした知識人を同じような知識人がディスる」という感じであろうと思ったら、本当にそうであった。確かに、経済学を元にするマルクス主義が弱まってから、リベラルみたいな人たちは、明治以来の文三タイプ、――法学部経済学部は自分の想い人を強奪するような悪いやつらの巣窟、という倫理観に戻ってしまった側面がある。また最近は、確かに、「エビデンス厨 対 概念操作厨」の戦いを演出してツイッターで囀りあっている人たちもいる。内田樹もいつのまにか正義の味方に、東浩紀も若手を使い捨ててるだけ、宮台真司は社会学をちゃんとやってるか怪しい、柄谷行人は「比較優位説」を勉強しろ、そうじて経済学と若者の窮乏がわかっておらぬ……、某古市はいいかげんにしろ(←
これだけはわたくしでもすぐわかる)、とまあそうかもしれぬ。でも、「大学の先生は、みんないいところに住んでる」「荒川区とか足立区に住んでみろ」とかいう議論が最後の方で出てくるので、なんだかなあという感じがした。北田栗原後藤の仕事をちゃんとフォローしていないので何とも言い難いが、このままだと昔の「社会問題講座」にはまったマルクスボーイと同じではないか。
昔も、そういう人たちが「一般の方」の複雑さとバカさに絶句して何も言えなくなってしまい、相変わらずの煩悶で抵抗者面をしていた。井戸端会議のような鼎談の企画だから別に過剰な期待はできないが、もう少し小出しでいいから、おっ、という認識を入れ込んでほしいものだ。
もう、批評のプロレスで溜飲を下げる時代は様々な意味でおわっとるのである。
確かに、内田宮台東なんかがある時期から若者に対するあからさまな絶望を口にするようになったことが何らかの思想的な事件なのはわかるし、2007年の「丸山真男をぶん殴りたい」の人の登場が一つの曲がり角だったのもわかる。わたくしも、調子こいてそのころプロレタリア文学を再読して恥ずかしい論文を書いたことがあるからだ。しかし大概、そのころから数年の間に、大学で若者を相手にする教育者は、想像を超えたショッキングな目に遭っているに違いないのである。病気なのか病気のふりをしているのか、お偉方や親をまねしているのかよくわからんが……、信じがたい人間が大学で大きい顔をするようになったのだ。だから、――確かに、若者論を刷新したいのなら具体的なところから始めるのには大賛成だが、内田氏に限らず彼らは病棟みたいな大学を抜け出し、論壇で息をついているのである。――ナルシスティックになって当然だとわたくしなんかは想像する。まだ息をつく能力があるんだから煩悶するよりもましなのだ。
それにしても、誰が誰のおかげでデビューしてきたとか、業界の人はよく知ってるなあ…どうでもいい…
わたくしも、内田氏の二〇一三年の発言――「私は今の30代後半から45歳前後の世代が、申し訳ないですが、“日本最弱の世代”と考えています」
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20130108/1046779/?rt=nocnt
を覚えている。しかし、わたくしは北田氏のように激怒しなかった。北田氏とわたくしは確か同い年であるが、わたくしは大学院の頃からそのあたりの(自分たちの)世代を相対主義的な幼稚さにあふれた「日本最低の世代」と考えていたからである。わたくしは内田樹の言う「最弱の世代」に、なにか、弱い怪獣に対する哀れみみたいなものを感じて、わたくしの怨恨に凝り固まったセンスを呪った。
いずれにせよ、慷慨談は表現として心を打たなければらない。内田や宮台や東に勇み足の言説が多いのは当たり前ではないか。慷慨談なんだから。そして、慷慨談の流行は必要でもあるがそれだけではどうにもならないのも当たり前である。生身の彼らを知らないが、どのような行動をする人たちなのかが非常に重要だ。教育の世界では、こつこつと現場を支えている人と、研究授業がまあうまくて偉ぶりたいタイプというのはだいたい別人物であり、大学や思想結社の場合はちょっと微妙なところがあるが、果たして……
そういえば、朝、『週刊読書人』をめくってたら、千葉雅也氏と増田聡氏が対談してて、これがまた、ちゃんと対立すべきところが対立していない、なんとも煮え切らないものにみえた。彼らも「一般の方」への顧慮が強すぎるのではないだろうか。文章での彼らをそのまま対談でも生きればよいのにと……。