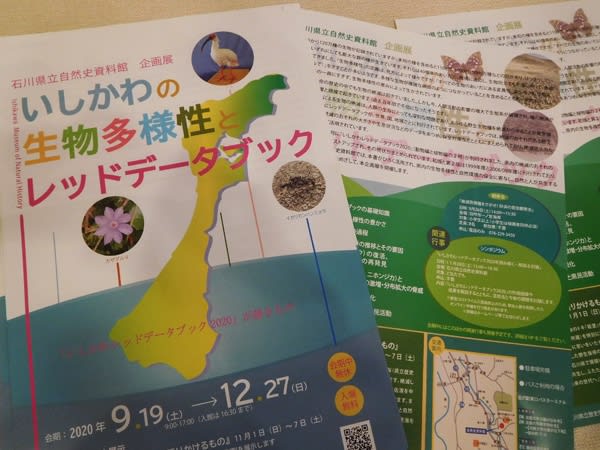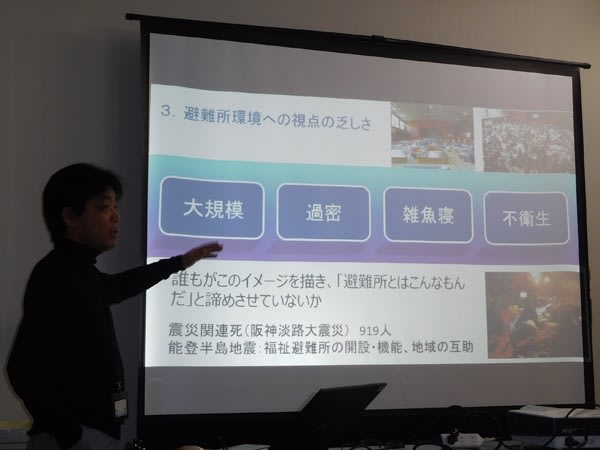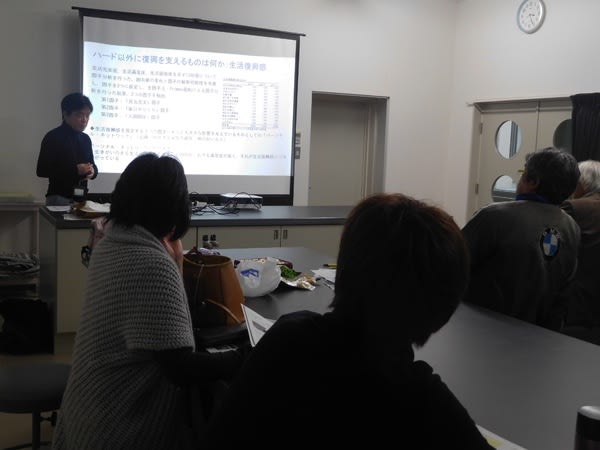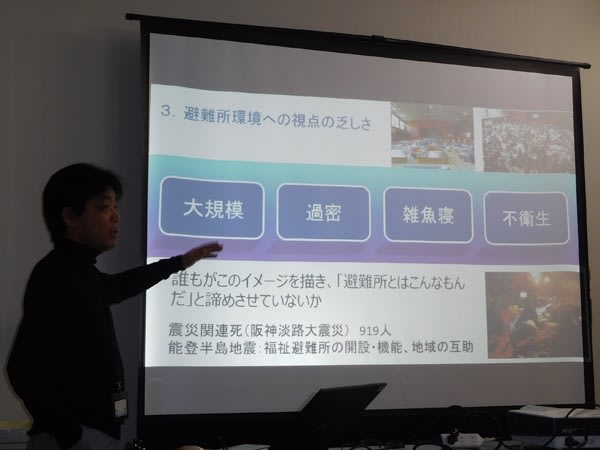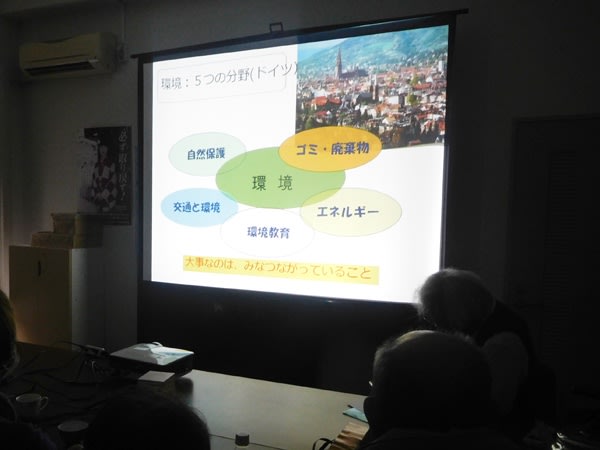今月の角間里山ゼミ会は、昨年12月にアフガニスタンで
凶弾に倒れた中村哲医師の活動がテーマでした。


水があれば救える多くの命を診てきた中村医師は、
「100の診療所よりも一本の用水を」と訴え、
大干ばつにより水不足、栄養失調、感染症に苦しむ
アフガニスタンの人々の生活を変えるため、その生涯を捧げました。
今回観たDVDは、砂漠や干ばつ地帯に用水路を作る計画を立て、
それを着々を進める中村哲さんの活動を追ったものでした。
困難が降りかかっても諦めずに問題解決していく実行力は、
私たちにも生きるパワーを与えてくれるようでした。
砂の大地が緑の大地に変貌し、田畑が復活する様は、
農民たちを蘇らせ、未来を作っていく仕事でもありました。
ペシャワール会は中村哲医師のパキスタンでの医療活動を
支援する目的で結成されましたが、それだけでも中村哲さんの
人望がどれほどのものであったのか伺い知ることができます。
人の幸せとは、「三度のご飯が食べられて、
家族がいっしょに穏やかに暮らせることだ」 中村 哲