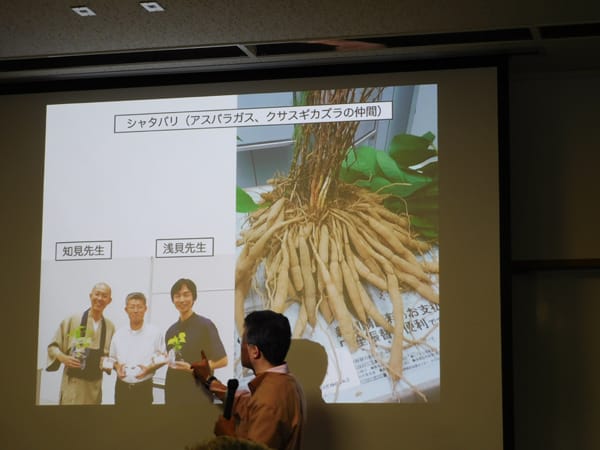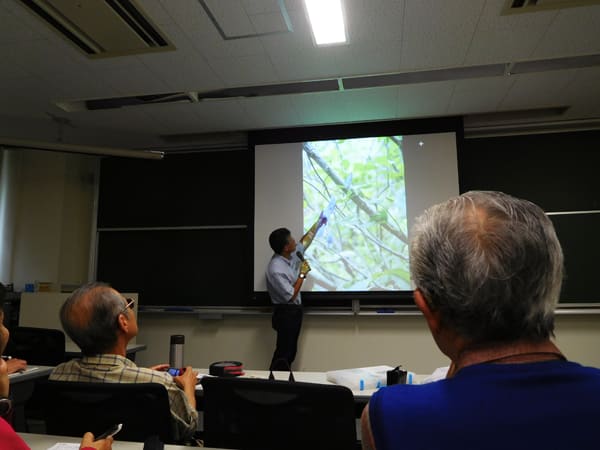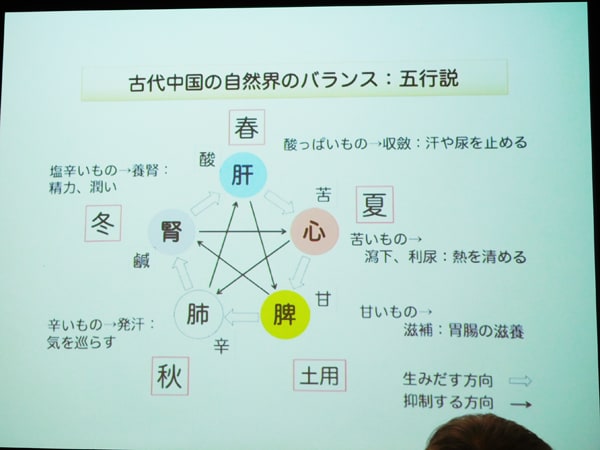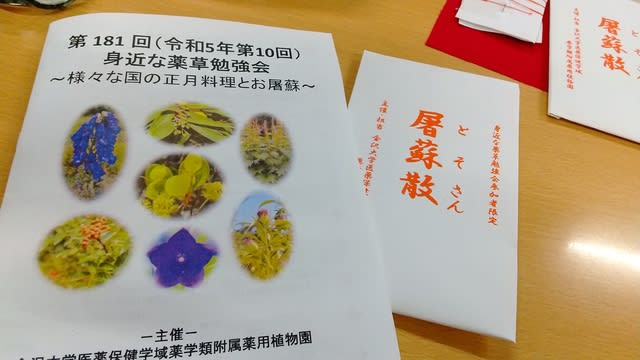

夏から慌ただしく時間が過ぎていき、
なかなか参加できなかった薬草勉強会に
久しぶりで参加しました。
12月はお気に入りの屠蘇散づくりもあります。



前半は、金沢大学の留学生たちによる
各国のお正月の食べ物の紹介。
中国河南省、中国上海、中国チベット、
ブラジル、タイの留学生たちが
それぞれの故郷料理を紹介してくれました。
当たり前ですが、お国が違えば食材もお料理の違っていて
とても面白い時間でした。


今日は大サービスで、ブラジルのマトゥーム茶、
金木犀の蓮根餅、フォイトーン(卵から作る糸のようなお菓子)、
黒豆アミーゴなどの試食がありました。
とても珍しいものばかりでした!
最後に、それぞれが布を塗って屠蘇散づくりをしました。
日本酒に漬けてお正月を楽しもうと思っています。
あ〜、楽しかった!