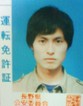5/31(水)~6/2(金)に東区プラザホールで開催された、劇団KURITAカンパニー「べっかんこ鬼」、観てきました。
個人的に演出の荒井和真さんから連絡をいただいていて、行けるようになったりやっぱり行けなくなったり返信が二転三転してしまったのですが(すみません)、最終日に観に行くことができました(ありがとうございます)。
さて、個人的にそもそも「べっかんこ鬼」は、2014年に演劇くらぶ葛の葉の公演で観て、その年のベスト演劇に選んだくらい好きな作品です。
その時は、普通の公民館の一室みたいな会場だったのですが、役者さんと手作り感のある音楽によって、昔話のようなシンプルな物語に奥深さを演出していたのが素晴らしかったなと思いました。

で、今回のKURITAカンパニーでは、荒井和真さん演出の元、やっぱり手作りの音楽や衣装、コロスの存在によってまた違う方法で物語に深みを与えていた、という印象でした。
でもやっぱり、もともと昔話のようなシンプルな物語に演出によって深みを持たせるのが、この演劇の良さなんだなあと思ったし、そもそも「物語」ってそういうものだよなあという、本当に普遍的な名作だと思ったりもしました。


まず、冒頭の曲の部分のみ撮影可能という試みが、演劇では斬新。
演劇は基本的にスマホをいじらずに物語に集中してほしいけれど、せっかくだから思い出にちょっとだけ撮影もしてほしいという、スマホ時代にも対応した感じが、なかなか面白い試みだったんじゃないでしょうか。
そんな演劇は、ピアノとウッドベースによるまさに荒井和真さんらしいジャズ的な演奏に、インドの楽器シタールが重なるという、多国籍感のある音楽によって始まります。
その音楽に合わせて舞踊家さんが踊るのですが、素人目に見ても分かるくらいの身体能力によるどこか超然とした踊りは、物語に直接かかわるわけではないものの、音楽とともに物語の世界観を表現していて引き込まれるものがありました。
さらに衣装は、物語の中では人智を調節した仙人的な存在である山母様とその横の舞踊家は中華風、鬼はまさに鬼(お面を被っている)、おゆきと父は和風というやっぱり多国籍感。
その中、3人の演奏隊と4人のコロスは地元、亀田縞の衣装を着ているというあたりも面白さ。
これがまさに「昔々あるところ」を舞台にしたが故に普遍性を持った民話的な世界観であると同時に、亀田という地元の身近な物語でもあるという。
この遠いような近いような、絶妙な距離感こそ、そもそも「演劇」という文化の醍醐味かもしれませんね…なんてことも思いました。
主な登場人物はべっかんこ鬼、おゆき、父、山母くらいしかいないのだが、まずこの4人は本当に素晴らしかったです。
特にメインの2人、べっかんこ鬼役の荒井さんはずっとお面を被っているのに声と身体だけであそこまで気持ちの変化を表現するのが凄いし、おゆき役の咲楽さんは目が見えず心に傷を抱えていても心の綺麗な少女にしか見えなかったですからね。
そして面白いのがコロスの4人で、時に狂言回しとなり、時にその他大勢のエキストラになり、時に演奏隊と共に楽器を演奏し、時に小道具や衣装の黒子になる。
誰一人欠けても演劇が成立しないわけで、みんなで一つの演劇を作っている一体感も良かったです。
で、肝心の物語は、笑い者の鬼が目に見えない少女に恋をするという、本当に昔話のような物語。
今より昔、人間と自然が身近にあり、同時にその境界線が曖昧だった時代には、その中間に生きている鬼などの曖昧な存在も自然に信じられていたのだろう。
そんな時代を生きていた視覚障害者のおゆきもまた、人間世界からこぼれ落ちた存在である。
実際、昔は差別されていた人間達を鬼と呼んでいたという説もあるくらいだし、べっかんこ鬼もまた人間社会のはみ出し者だったのかもしれない。
そう考えると、ともに社会に居場所がないべっかんこ鬼とおゆきが出会えるのも納得できる。
しかし、最後には鬼を憎む父親によってべっかんこ鬼が殺されるという悲劇が起こる。
おゆきからすれば、べっかんこ鬼を殺した父親の方こそが鬼となってしまうんですよね。
ただ難しいのは、父親も悪人ではなく、娘への愛故に行動していて、ただべっかんこ鬼に対して誤解をしていたという。
誤解から生まれる正義感が弱者を傷付ける、これって現代でも全然ある問題ですよね…
そう考えると、鬼は現代でもいるし、誰でも鬼になりうるわけで、あらためて普遍的な名作だと思いました。