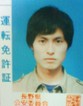江國香織さんの「なつのひかり」
僕がこの本を初めて読んだのは中学生の時で、僕が江國香織さんを知ったきっかけだったのですが、7/25(日)に参加した「あおぞら古本市」で見付けて、懐かしくて思わず購入してしまい、そして面白くて一気に読んでしまいました。
当時すごくこの本が好きになったので、夏休みの読書感想文にこの本のことを書いたくらいだったのですが、なんというか、とらえどころのない小説で(図書館の先生には、この本で書いたの?と驚かれた)、また当時は僕自身もまだ中学生でうまくその面白さをうまく言葉にして感想を書くこともできませんでした。
それから20年が経ち、あらためて読んでみたら、やっぱりとらえどころのない小説だったのですが、まさに僕が好きなタイプの物語だと思ったし、僕がこういう小説を好きになったルーツの一つであるくらいに思えてくるという、色々な発見があったので、20年ぶりにあらためて読書感想文を書いてみたいと思います。
この物語の主人公は、栞という21歳の誕生日を間近に控えた女性で、深夜のバーでの歌手と、ファミリーレストランの深夜のアルバイトをしながら、アパートで独り暮らしをしています。
アルバイト以外は特にすることがなく、午前中に寝て、昼に起きては散歩をして、野菜の販売所のおばあさんを訪ねていってはそこで読書をして過ごす、という静かで退屈な、特に事件が起こることもない平和な毎日を送っています。
栞には幸裕という兄がいて、兄には遥子さんという美人の奥さんがいて、2人には陶子という幼い子供がいます。
しかし、幸裕は結婚する前から、栞の働くバーの経営者である順子さんという年上の女性と愛人関係にもなっていて、その関係は栞も遥子さんも知った上で、兄の結婚後もなんとなく続いています。
ある夏の朝、隣の部屋の薫平という小学生の男の子が、飼っていたやどかりが逃げたから一緒に探してほしいと訪ねてきます。
それ以来、栞の行く先々にやどかりが現れ、やどかりは栞をどこかに導くかのように翻弄し、少しずつ平和な栞の生活の中には不思議な出来事が起こっていきます。
ある日、遥子さんは「それを探しにいってきます」という謎の手紙を残し、夫(栞の兄)である幸裕の前から姿を消します。
かと思えば、兄の知らないところで遥子さんが栞の前に突然現れては「それ」を一緒に探すために行動を共にしたりするのですが、「それ」が何なのかはまったく分からないまま、遥子は栞の前からも姿を消します。
遥子さんのいない間、娘の陶子の世話をすることになったのはなつみちゃんという女子高生なのですが、なつみちゃんはかつて、結婚はしたくはないが子供がほしいという理由で、陶子を盗んだことがあります。
しかし、何故かその現場を順子さんが目撃していたために犯行は未遂に終わり、その結果何故かなつみちゃんは栞も幸裕も遥子さんとも仲良くなり、陶子のベビーシッターとなっています。
そんな中、栞が家に帰るとめぐと名乗る知らない女性がいて、めぐは兄の妻だと名乗ります。
そして、めぐは兄のことを本名の幸裕(ゆきひろ)ではなく裕幸(ひろゆき)と呼び、めぐの前では兄も自分を裕幸と名乗ります。
兄が嘘をついているのか、めぐは兄に騙されているのか、そこらへんは判然としないまま、住む家がないというめぐは栞の家で暮らし始めます。
その直後、栞が拾ったキャラメルの箱が携帯電話のように鳴り出し、そこからは兄(裕幸ではなく本名である幸裕)の助けを求める声が聞こえてきます。
また、栞の部屋の真下には、人形のような風貌の双子の女の子が暮らしているのですが、ある日、双子が薫平のやどかりを隠し持っていることが判明します。
そんな感じで、平和で退屈だった栞の毎日には、兄の妻・遥子さんの失踪、幸裕と名乗る兄の不可解な行動、そんな兄と結婚したというめぐ、やどかりを探す薫平と謎の双子という、突然なんだかよく分からない出来事が立て続けに起こっていきます。
そんなある日、めぐは陶子となつみちゃん、薫平と双子を連れて、みんなで「それ」を探しに行くと言ったまま、どこかへ消えてしまいます。
そして、兄・幸裕(めぐは裕幸と呼ぶけれど)も、どこかへ消えてしまいます。
そして栞は、再び目の前に現れたやどかりとともに、消えた兄と遥子を探しにいくのですが…その先は、さらに不思議な出来事が連発する、ファンタジーな展開になっていきます。
一応、オチは書かないでおきますが、最後まで読んでも、果たして何が起こったのか、色々な謎は何だったのか判然としないまま、なんとなく物語は結末を迎えます。
一通りのあらすじを書いてみましたが、これだけ読んでも、何が何だか分からない、という人が多いと思います(実際、読んでも分かりません)。
こうして振り返ってみると、この小説、ミステリーやサスペンス、恋愛や冒険と言った、いわゆる起承転結がはっきりした小説らしい分かりやすいストーリーでは全然ないんですよね。
それでも、僕はこの小説がものすごく好きで、読めば読むほど引き込まれるし、何度も繰り返し読みたくなってしまうような魅力があります。
それが何なのか、自分なりに思うところを書いていきます。
まず、そもそも僕にとって小説を読むという行為の面白さは、いわゆる分かりやすい「ストーリー」を楽しむというだけでなく、小説の中に登場する「世界」そのものに入り込み、それを味わう、ということだと思うのです。
確かに、この小説に登場する物語は何が何だかよく分かりませんが、栞の日常生活の描写、心理描写、風景描写の一つ一つが物凄く丁寧なので、本に書かれた出来事や風景の一つ一つがまるで映画やドラマの映像ようにありありと頭の中に浮かんでくるのです(20年前もそうでした)。
そして、登場人物の行動の一つ一つやそこから見える性格や人間性みたいなものも、すごく繊細に伝わってくるので、一人一人の声が表情やまるで本当にそこに存在しているかのように頭の中に浮かんでくるし、もっと言えば、本当に自分がその人達に出会っているかのような存在感があるのです。
だから、さっき映画のようと言いましたが、映画化したらこの役者さんがやってほしい…なんてことも想像しながら読むのも楽しかったです。(僕が映画化するなら、栞は松本穂香さん、幸裕は成田凌さん、遥子は松本まりかさんとかがいいだろうか…)
例えば僕は静かな日常描写を淡々と描くような映画が好きで、派手なストーリーがなくてもまるで本当にそこにそういう人達が存在していて、本当にそういう日常が存在しているようなリアリティを感じるだけでいい映画だなあと思ってしまうのですが、この「なつのひかり」は、まさにそういう小説なのです。
また、考えてみれば、兄が結婚しながら愛人がいてさらにもう一人妻がいるとか、なつみちゃんと陶子の出会いとか、常識的に考えたら「普通」ではないような展開もたくさん登場しますが、でも考えてみればどんな人や家族にだってちょっと「普通」じゃない変わったところはあって当たり前なわけで、そういう「普通」じゃない部分があることさえも、寧ろ「普通」に受け止めてしまえる現実味があります。
そんな物語の中で、やどかりがまるで栞に対して意志を持っているかのように出現したり、キャラメルの箱が携帯電話になったり、ところどころで非現実的なファンタジー的な展開も登場しますが、それさえも、描写が丁寧だからこそ、「この物語の中でなら、起こってもおかしくない」と思えてしまえるほどの現実味がそこにあるのです。
江國香織さんって恋愛小説が有名だと思いますが、初期の頃ってこういう日常の中でちょっと不思議だけどちょっと本当に起こりそうなファンタジーをよく描いていて(愛犬を亡くした女性がまるで犬の生まれ変わりのような不思議な少年と出会う「デューク」は初期の名作!)、僕は寧ろ、江國香織さんのこういう作品が好きなんです。
また、本作の特徴として、物語のところどころで、本編とは一見直接関係のないような栞の回想シーンが大量に登場し、その度に物語は中断するのですが、でもこの回想シーンがあることで、栞や幸裕や遥子さんや陶子やなつみちゃんや順子さんの性格や人間関係をより深く知ることに繋がるので、寧ろ物語により奥深い現実味を感じられるのです。
なんというか、どんな人物にもちょっと話しただけでは分からない過去の人生や気持ちがあるわけで、そこをあえて積極的に描いている感じなんですよね。
小説って、様々な登場人物にまつわる様々な情報の中から物語に必要な部分を厳選して表現することで成立することが多いと思うのですが、でも小説の登場人物にだって物語には登場しない部分の人生があるはずだ、そんな気持ちが込められているように感じられます。
だから、この小説の登場人物は、単なる記号的なキャラクターではなく、一人一人が生きた人間として感じられる、そんな魅力があるのかなあと感じました。
どんな人にだって物語にしたら地味かもしれないけれど、その人にとっては大切な体験ってあるじゃないですか。
この小説は、確かに普通の分かりやすい小説ではないけれど、一人一人をしっかりと生きた人間として描き、一つ一つのエピソードや展開を繊細に描写することでまるで目の前に映像が浮かぶほどまるで本当に目の前で起こっているような現実感を表現することで、この「なつのひかり」という小説の世界に読者が入り込んで旅をするような気持ちになれる、本当に素敵な作品だと思いました。
僕がすごく好きな小説に、ミヒャエル・エンデの「はてしない物語」というファンタジーがあり、あれは本好きな少年が本の中に入り込んで冒険をする物語なのですが、まさにそんな体験ができる魅力がこの「なつのひかり」にはあるので、もしかしたら中学生の時にこの小説を読んだことが僕が読書を好きになった一つのルーツなのかな、なんてことも思いました。
また、僕はこの小説を初めて読んだ中学生の時はここまでこの小説の面白さを言葉で表現することができなかったものの、やっぱり当時もこういう風にこの本を楽しんだわけで、もう一度読むことで、再びその世界を味わうということができたので、読書は何度でも好きな世界を旅することのできる本当に素敵な体験だなと、あらためて気付かされました。
小説に限らず、映画や漫画など、あらゆる物語という表現って、突き詰めると人間というもの掘り下げて描くからこそ価値があるのかな、なんて思ったりするのですが、「なつのひかり」はまさにそんな小説だなと思いました(いつか自分もそんな小説を書いてみたいなと思います)。
というわけで、20年ぶりに読んでみたら、思いがけずに僕がどうして小説などの物語が好きになったのか、その原点に立ち返るような発見があったので、20年前にはうまく書けなかった読書感想文をこうして書くことができて良かったです。
最後に、この「なつのひかり」という小説に関する個人的な思い出を書きたいと思うのですが、中学生の時にこの本を買ったあと、本の上にお茶をこぼして染みを作ってしまったことがあったんです。
その後、この本を誰かに貸しっぱなしにしたのか、どこかに置き忘れてしまったのか、十数年前に紛失していたのですが、今回あらためて古本市で買ってみたら、本の同じ場所に染みが…って、まさかね!!