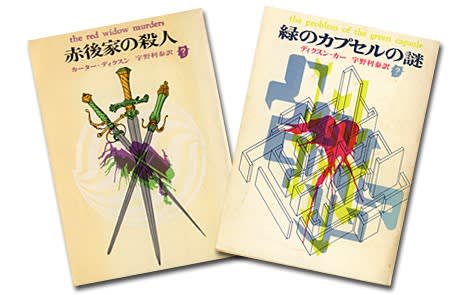
■『三つの棺』における「密室講義」を、まさかカーの研究発表だなんて思っているヒトはいないだろうね。
★ブログやアマゾンのレビューで、それらしいことを書いているヒトはけっこう見かけます。
■有名な作家や評論家のセンセイが書いたり言ったりすると、そのまま鵜呑みにしているヒトが多いってことかね。
★じつは、そこだけ読んでも面白いからという理由もありますね、あれ。
■カーは『白い僧院の殺人』『赤後家の殺人』でも、HM卿に似たようなことをさせている。
『白い僧院の殺人』では、殺人者が密室を構成する条件みたいなことをHM卿に開陳させているけど、
それはプロットの要を読者に悟られないためのミスディレクションなんだ。
『赤後家の殺人』では、HM卿とマスターズ警部、テアレン博士が密室殺人を再構成を試す場面があるが、
それも『殺人現場に犯人がいなければならない』というミスディレクション。
★『赤後家の殺人』のその場面では、マスターズ警部が意外な得意技を披露するんですね。
しかも日本産の絹糸が使われている、という豆知識。
■HM卿より先に真相をつかんだ(と思われる)マスターズ警部へ読者を誘導する展開はうまい展開だが、
そこにミスディレクションがある。『白い僧院の殺人』『赤後家の殺人』の「手ごたえ」(?)を敷衍して、
『三つの棺』で展開させた、というのはあながち間違いじゃないと思うね。
★『緑のカプセルの謎』でもフェル博士が講義してましたよね。
■こっちはミスディレクションというより、〇〇の〇なんだよ。
★は?
■作中の心理試験で、被害者が持っていたものは?
★〇〇の〇です。
■「観察力の無さと先入観で、それとは気づかぬもの」被害者は、被験者たちに心理試験を仕掛けたのだけど、
じつは著者カーは同じように「観察力の無さと先入観で、犯人とは気づかぬ登場人物」という心理試験を読者へ仕掛けた、といえる。
その自信は「心理学的推理小説」という副題に表れているね。つまり入れ子状態なった二重の心理試験が仕掛けられているんだ。
★へえ~
■「毒殺者とはー」の章は、男性であって、とある性格の犯人ばかりを集めてフェル博士に紹介させている。
読者に対して、こんな人間が犯人だぞ、とフェル博士に言わせているわけ。
毒殺者には女性も、自信のない犯人もいるのにね。つまりカーによって恣意的に選ばれた毒殺者たちなんだ。
★でも残念な点は、犯人があまり意外じゃない、というところですよね。
■そこなんだ。仕掛けは立派なんだが、プロットにヒネリがないというか。
★大多数の読者は犯人より、最後の一番いいところで披露される『フェル博士の歌』のほうが印象深いのではないですか。
■そうなんだよね。
※「虫の好かないフェル博士……」
‘I do not like you, Doctor Fell,
The reason why I cannot tell;
But this I know and know full well,
I do not like you, Doctor Fell.’
例の有名な詩は、
Carolyn Wells著『The Luminous Face』(1921 George Doran Company)の第1章「Doctor Fell」に書かれています。
たぶんカーもこの本を読んでいたはず。
★ブログやアマゾンのレビューで、それらしいことを書いているヒトはけっこう見かけます。
■有名な作家や評論家のセンセイが書いたり言ったりすると、そのまま鵜呑みにしているヒトが多いってことかね。
★じつは、そこだけ読んでも面白いからという理由もありますね、あれ。
■カーは『白い僧院の殺人』『赤後家の殺人』でも、HM卿に似たようなことをさせている。
『白い僧院の殺人』では、殺人者が密室を構成する条件みたいなことをHM卿に開陳させているけど、
それはプロットの要を読者に悟られないためのミスディレクションなんだ。
『赤後家の殺人』では、HM卿とマスターズ警部、テアレン博士が密室殺人を再構成を試す場面があるが、
それも『殺人現場に犯人がいなければならない』というミスディレクション。
★『赤後家の殺人』のその場面では、マスターズ警部が意外な得意技を披露するんですね。
しかも日本産の絹糸が使われている、という豆知識。
■HM卿より先に真相をつかんだ(と思われる)マスターズ警部へ読者を誘導する展開はうまい展開だが、
そこにミスディレクションがある。『白い僧院の殺人』『赤後家の殺人』の「手ごたえ」(?)を敷衍して、
『三つの棺』で展開させた、というのはあながち間違いじゃないと思うね。
★『緑のカプセルの謎』でもフェル博士が講義してましたよね。
■こっちはミスディレクションというより、〇〇の〇なんだよ。
★は?
■作中の心理試験で、被害者が持っていたものは?
★〇〇の〇です。
■「観察力の無さと先入観で、それとは気づかぬもの」被害者は、被験者たちに心理試験を仕掛けたのだけど、
じつは著者カーは同じように「観察力の無さと先入観で、犯人とは気づかぬ登場人物」という心理試験を読者へ仕掛けた、といえる。
その自信は「心理学的推理小説」という副題に表れているね。つまり入れ子状態なった二重の心理試験が仕掛けられているんだ。
★へえ~
■「毒殺者とはー」の章は、男性であって、とある性格の犯人ばかりを集めてフェル博士に紹介させている。
読者に対して、こんな人間が犯人だぞ、とフェル博士に言わせているわけ。
毒殺者には女性も、自信のない犯人もいるのにね。つまりカーによって恣意的に選ばれた毒殺者たちなんだ。
★でも残念な点は、犯人があまり意外じゃない、というところですよね。
■そこなんだ。仕掛けは立派なんだが、プロットにヒネリがないというか。
★大多数の読者は犯人より、最後の一番いいところで披露される『フェル博士の歌』のほうが印象深いのではないですか。
■そうなんだよね。
※「虫の好かないフェル博士……」
‘I do not like you, Doctor Fell,
The reason why I cannot tell;
But this I know and know full well,
I do not like you, Doctor Fell.’
例の有名な詩は、
Carolyn Wells著『The Luminous Face』(1921 George Doran Company)の第1章「Doctor Fell」に書かれています。
たぶんカーもこの本を読んでいたはず。















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます