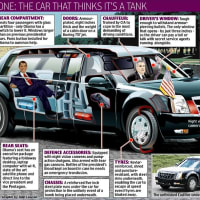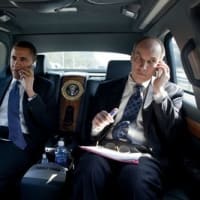第一章 途方もない時空 -類人猿から人へ
ダーウィンの進化論をモチーフにすれば、現代に於ける人ゲノムを遡って行くと
猿の一部が 途方もない歳月を経て二足歩行になったといわれている。それを
証明するような原初人類の化石が発掘されている。外見的に二足歩行を始めた人類だが
頭長部の骨格から推測されるのは 猿の要素が残ったものでありおいおい進化を遂げる訳
だが、容易に推測できるのは動物としての脳であり、意思の疎通方法に言語が登場する迄
再び気の遠くなるような歳月を要したに違いない。
その経緯を考慮すれば 意思疎通に絵を用いていた頃には、所謂「死」の概念が
無かったものだと推察できる。つまり その頃に息絶えた者がいたとしてもそれは
私達が考えるような「死ではなく動物としての死」に過ぎなかったはずである。
「動物としての死」という意味について私論を述べれば、今の時代に野生の世界で
起こりうる死とほぼ同義であり 動かなくなった=死んでしまったものに対して
あくまでも、もう動かないだけであって特別な行動に出ることはないということである。
あえて解釈を加えるならば、永遠に寝ている程度のことでしかない。
現在も形態は全く異なるが 死を理解している民族が死したものを特別な場所に
運んで自然の摂理に再び返すという鳥葬や河に或いは川辺に運びということが
行われているのである。
3千字 /5万字
FOCUSという雑誌の創刊号にサントリーが藤原新也が「犬人を喰らう」という
前述した方法でガンジスの川邉で撮影した写真を掲載した処大きな非難をうけた
事がある。企業の広告としていかがなものか?と思うものの、自然のサイクルは
本来人とて例外ではなかったはずであり、自然に還すという意味においては
理にかなった方法であるともいえる。しかし、ある程度成熟したと自負する
文化圏で生きている人にとっては、野蛮な行為に見えるのだろう。
現代の様な「火葬」という方法が確立されたのは(一部の地域に於いてだが)
人の長い成形過程を考慮するならば、何ミクロン以下の事である。
話を戻すと 原初の人類は動物的野性的要素が強くゆえに死というもの自体の
概念がなかったはずである。然しながら 果てし無い時を経ていく過程で
物に何かを描くことや 象形文字、そして発音から言語へと変遷していき、
それと同系列に、心的な発達があり感情というものが生まれたのだろう
そして 群れで暮らすことや狩猟などを共同で行うようになったことは
自明の理である。言語の発達によって感情を表現する手段となった時に
初めて理性や知性が生まれて、と同時に初めて人間が動かなくなる事は
動物的なものではなく「死」の概念が生まれたものだと思うのだ。
さらに長い時空 を経ていく過程で「死」に対する畏怖や概念が深化し
特別なものだと考え始めたのだろう。