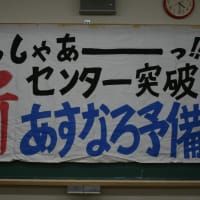収穫の秋となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。夏の間に英数国をがっちりと固め、この時期、センターに向けて地歴公民・理科の学習時間を確保している方も多いと存じますが、そうでない方もおられるかもしれません。センター日本史Bに自信がある方、やや自信がある方、不安な方全ての方に有効な学習方法をご紹介したく存じます。
【センター対策としての学習のスタンス】
教材等
センター日本史Bで高得点獲得する上で必要となる知識及び理解(解釈)は、山川出版社の教科書にあります。結論から言えば、上述の教科書をベースに学習することが全てと言っても過言ではありません(あくまでセンター受験対策としてでございます)。加えて、山川出版社の日本史用語集、出版社は問いませんが、図版(写真・年表・地図などが記載しているもの)も必ず用意して下さい。歴史用語の意味が分からないとき、あやふやな時は必ず、その場で、用語集や図版で調べて下さい。これは習慣付ける必要があります。
理解の手助けとしてのスタンス
日本史の情報量は膨大です。とりあえず、教科書の中の黒字を中心に学習して頂きたいのですが、それでもなかなか明確に理解するのは難しいです。そこで、理解力、知識の定着力を向上する、考え方をご紹介します。
・歴史を敬すること→これは基本ですね。
・ごっちゃにしない→センターではいれかえ問題が頻出します、正確に明確に、何時代に何があったのが、誰がやったのか、どこで等、にたような事柄と明確に区別しておいて下さい。センターで一番やってはならないのが、あやふやな知識で満足することです。時代区分のいれかえ、用語の意味内容のいれかえ、土地のいれかえ、法律のいれかえ、人物のいれかえ、様々ないれかえ問題(後述の過去問の学習方法参照)が登場します。学習する際、きちんと区別しようと頭にいいきかせてください。理解するもととなるデータ-ベースがあやふやだと、理解もあやふやになります。
・歴史の流れ→歴史は時間と空間をあつかう学問ですので、頭をフル活動しなければなりません。ただでさえ、会った事もない人物、聞いた事もない法律、住んだ事のない時代などを扱うわけですから、その取り扱いは慎重にお願いします。そこで重要なのは、我々は現代に生きておりますので、歴史上の出来事の結果を知っているという事です。ある出来事・政策・戦争などの結果を頭に入れた上で、そこに行き着くまでの過程を逆算し、さらにその逆算を頭に入れた上で、今度を時間軸通リ進んでみると、その流れが頭に残りやすくなります。
・時代の雰囲気→どうしても時代の雰囲気、当時の社会の空間が想像できない方は、服装から入って下さい。当時の服装を見るだけでよいのです。衣冠束帯とか大鎧とが軍服とかです。資料集や古語辞典などにありますので参照して下さい。
【政治史】
政治史で重要になるのが系図です。出来事・歴史の流れ・用語チェックをともないつつ、学習して下さい。最低限、飛鳥白鳳時代の天皇家・奈良平安期の藤原摂関家・院政全盛期の天皇家・鎌倉前期の源氏将軍家・鎌倉期執権北条氏・南北朝期天皇家・室町期足利将軍家・江戸期徳川将軍家・歴代内閣総理大臣はおさえて下さい。上述のスタンスを使えば知識は残ります。また、その時代を特徴付ける、テーマがございます(例えば、律令制度の導入・武家政権の確立・不平等条約の撤廃など)。そのテーマ、あえて言うなら大局から入って欲しく存じます。大局から個別の出来事へ、個別の出来事から大局へ視点を変えることで、点と線が結びつきます。
【制度史・文化史・経済史・土地制度史・外交史・沖縄の歴史・北海道の歴史など】
これらのカテゴリーは重要です・政治史を主軸に学習する中で、一応頭には入っているとは思いますが、改めて、このカテゴリーごとに学習する事をお勧めします。当然、正確な時代区分、正確な用語の定義、及び内容を心がけてください。制度史・土地制度史・経済史の用語のいれかえ問題、定義を問う問題は頻出しております。例えば、鎌倉期の守護と室町期の守護の職務内容や、戦国期の被官(武士身分で、一般には家来や家臣の意味で使用される)と江戸期の被官(隷属農民を表す言葉)の相違点などです。
外交史は、国別に学習してください。貿易関係の事項は、他の分野とのからみが多いので、時代ごとに明確に頭に入れて頂きたい。
文化史は特に要注意です。図版で写真を確認するのはもちろんのこと、思想・教育・建築・美術・文学などの基本的理解と時代区分は正確に行なって下さい。また歴史地理・歴史史料については、教科書ベースに学習してください。歴史史料はきちんとその内容を把握してください。
また時代ごとの習俗、生活スタイルの区別も重要です。例えば、鎌倉武士の生活スタイルや室町後期の祇園祭と京都の町衆の関係などです。
【センター過去問】
山川出版社の『センター試験への道』および赤本での5年分の過去問が王道でしょう。過去問学習の力量配分は、解答4割、解説6割です。自分が何を勘違いし、どの知識が定着してないのが、センターがどのような聞き方をしてくるの、何をいれかえてくるのかなど、自分の力量および問題を分析しつつ学習してください。私の過去問演習ではよく言うのですが、訓練中に根拠のない解答や、勘に頼った解答はするなと指導しております。なぜだかお分かりですね、自分の現時点での力量が分からないからであります。まず、汝自身を知ることです。
【歴史学を志す方のために】
参考文献をご紹介しますので、試験がひと通り終わったら、また大学に入学したらぜひお読み下さい
・『歴史とは何か』E・H・カー著 清水幾太郎訳 岩波書店
・『歴史とはなにか』岡田英弘著 文芸春秋
・『宮城谷昌光名言集 歴史のしずく』宮城谷昌光著 中央公論新社
【歴史を学ぶ際に聞くと、感じが出る曲】
・千住明「Next Door」←TBS系「夢の扉」オープニングテーマ
【センター対策としての学習のスタンス】
教材等
センター日本史Bで高得点獲得する上で必要となる知識及び理解(解釈)は、山川出版社の教科書にあります。結論から言えば、上述の教科書をベースに学習することが全てと言っても過言ではありません(あくまでセンター受験対策としてでございます)。加えて、山川出版社の日本史用語集、出版社は問いませんが、図版(写真・年表・地図などが記載しているもの)も必ず用意して下さい。歴史用語の意味が分からないとき、あやふやな時は必ず、その場で、用語集や図版で調べて下さい。これは習慣付ける必要があります。
理解の手助けとしてのスタンス
日本史の情報量は膨大です。とりあえず、教科書の中の黒字を中心に学習して頂きたいのですが、それでもなかなか明確に理解するのは難しいです。そこで、理解力、知識の定着力を向上する、考え方をご紹介します。
・歴史を敬すること→これは基本ですね。
・ごっちゃにしない→センターではいれかえ問題が頻出します、正確に明確に、何時代に何があったのが、誰がやったのか、どこで等、にたような事柄と明確に区別しておいて下さい。センターで一番やってはならないのが、あやふやな知識で満足することです。時代区分のいれかえ、用語の意味内容のいれかえ、土地のいれかえ、法律のいれかえ、人物のいれかえ、様々ないれかえ問題(後述の過去問の学習方法参照)が登場します。学習する際、きちんと区別しようと頭にいいきかせてください。理解するもととなるデータ-ベースがあやふやだと、理解もあやふやになります。
・歴史の流れ→歴史は時間と空間をあつかう学問ですので、頭をフル活動しなければなりません。ただでさえ、会った事もない人物、聞いた事もない法律、住んだ事のない時代などを扱うわけですから、その取り扱いは慎重にお願いします。そこで重要なのは、我々は現代に生きておりますので、歴史上の出来事の結果を知っているという事です。ある出来事・政策・戦争などの結果を頭に入れた上で、そこに行き着くまでの過程を逆算し、さらにその逆算を頭に入れた上で、今度を時間軸通リ進んでみると、その流れが頭に残りやすくなります。
・時代の雰囲気→どうしても時代の雰囲気、当時の社会の空間が想像できない方は、服装から入って下さい。当時の服装を見るだけでよいのです。衣冠束帯とか大鎧とが軍服とかです。資料集や古語辞典などにありますので参照して下さい。
【政治史】
政治史で重要になるのが系図です。出来事・歴史の流れ・用語チェックをともないつつ、学習して下さい。最低限、飛鳥白鳳時代の天皇家・奈良平安期の藤原摂関家・院政全盛期の天皇家・鎌倉前期の源氏将軍家・鎌倉期執権北条氏・南北朝期天皇家・室町期足利将軍家・江戸期徳川将軍家・歴代内閣総理大臣はおさえて下さい。上述のスタンスを使えば知識は残ります。また、その時代を特徴付ける、テーマがございます(例えば、律令制度の導入・武家政権の確立・不平等条約の撤廃など)。そのテーマ、あえて言うなら大局から入って欲しく存じます。大局から個別の出来事へ、個別の出来事から大局へ視点を変えることで、点と線が結びつきます。
【制度史・文化史・経済史・土地制度史・外交史・沖縄の歴史・北海道の歴史など】
これらのカテゴリーは重要です・政治史を主軸に学習する中で、一応頭には入っているとは思いますが、改めて、このカテゴリーごとに学習する事をお勧めします。当然、正確な時代区分、正確な用語の定義、及び内容を心がけてください。制度史・土地制度史・経済史の用語のいれかえ問題、定義を問う問題は頻出しております。例えば、鎌倉期の守護と室町期の守護の職務内容や、戦国期の被官(武士身分で、一般には家来や家臣の意味で使用される)と江戸期の被官(隷属農民を表す言葉)の相違点などです。
外交史は、国別に学習してください。貿易関係の事項は、他の分野とのからみが多いので、時代ごとに明確に頭に入れて頂きたい。
文化史は特に要注意です。図版で写真を確認するのはもちろんのこと、思想・教育・建築・美術・文学などの基本的理解と時代区分は正確に行なって下さい。また歴史地理・歴史史料については、教科書ベースに学習してください。歴史史料はきちんとその内容を把握してください。
また時代ごとの習俗、生活スタイルの区別も重要です。例えば、鎌倉武士の生活スタイルや室町後期の祇園祭と京都の町衆の関係などです。
【センター過去問】
山川出版社の『センター試験への道』および赤本での5年分の過去問が王道でしょう。過去問学習の力量配分は、解答4割、解説6割です。自分が何を勘違いし、どの知識が定着してないのが、センターがどのような聞き方をしてくるの、何をいれかえてくるのかなど、自分の力量および問題を分析しつつ学習してください。私の過去問演習ではよく言うのですが、訓練中に根拠のない解答や、勘に頼った解答はするなと指導しております。なぜだかお分かりですね、自分の現時点での力量が分からないからであります。まず、汝自身を知ることです。
【歴史学を志す方のために】
参考文献をご紹介しますので、試験がひと通り終わったら、また大学に入学したらぜひお読み下さい
・『歴史とは何か』E・H・カー著 清水幾太郎訳 岩波書店
・『歴史とはなにか』岡田英弘著 文芸春秋
・『宮城谷昌光名言集 歴史のしずく』宮城谷昌光著 中央公論新社
【歴史を学ぶ際に聞くと、感じが出る曲】
・千住明「Next Door」←TBS系「夢の扉」オープニングテーマ