 著者の松井今朝子は『吉原手引草』で、第137回直木賞を受賞しているが、本作『非道、行ずべからず』は、その5年前の第127回直木賞にノミネートされながら、残念ながら受賞を逃していた。
著者の松井今朝子は『吉原手引草』で、第137回直木賞を受賞しているが、本作『非道、行ずべからず』は、その5年前の第127回直木賞にノミネートされながら、残念ながら受賞を逃していた。
彼女は大学院終了後松竹に入社。歌舞伎の企画・制作に携わった経歴を持つ。それだけに歌舞伎の世界を題材に取った作品が多々ある。『仲蔵狂乱』では時代小説大賞を受賞。私が読んだ『家、家にあらず』では歌舞伎役者が重要な役割を演じる。『壺中の回廊』はまさに歌舞伎小屋を舞台とするミステリーである。本作も歌舞伎小屋から遺体が発見されるところから物語が始まる。
物語の時系列上、『家、家にあらず』から『非道、行ずべからず』を経て『道たえずば、また』へと続く三作品は『風姿花伝』の中の一文を表題に選んだ三部作。本作の表題”非道、行ずべからず”は芸事の道を極めようと志すものは、他のものに手を出すしてはならない、との戒めである。ストーリー展開そのものは独立しているが、すべてに登場するのが荻野沢之丞で、三部作は微妙にリンクしている。
元旦の未明に出火した江戸の大火は歌舞伎小屋「中村座」をも餌食とした。一部焼け残った二階桟敷を見回った、十一代目中村勘三郎らは、衣装行李の中から男の死体を発見する。北町同心笹岡平左衛門と同心見習園部理市郎の努力により、遺体は小間物屋の忠七と分かる。彼の遺した文から”四君子”が犯人と悟る同心ふたり。
”四君子”とは中村座の中心人物の四人、すなわち、太夫元勘三郎か立女形荻野沢之丞か金主大久保庄助か、はたまた立作者喜多村松栄かと、その周辺の探索が続くなか、内部事情のスパイを依頼していた桟敷番が第二の死体となって発見されるに至り、連続殺人事件の様相を帯びてくる。
更なる捜索により、事件の深淵には荻野家の名跡争いが絡むことを突き止める同心たち。既に60歳を超える沢之丞には腹の違う二人の息子市之介と宇源次がいた。どちらに沢之丞の名跡を継がせるかを巡っての中村座内部の権力争い。真相は一向に見えてこない。
作者は”四君子”というヒントを出して、読者への挑戦を仕掛けていた。その意味を調べれば犯人に到達できたかも知れないが、私はお手上げだった。
歌舞伎に興味を持ち始め、ミステリー好きの私にとって、松井ワールドは兎も角面白い。三部作のすべてに登場する荻野沢之丞なる立女役の内面の葛藤を見事に描いた本作品で直木賞受賞も可笑しくないと思える出来栄え。文庫版で600ページ、単行本にして430ページの大作でもある。
2月16日(日)の今朝、富士神社のラジオ体操はお休み。そこで、2日前のブログに書いた、赤羽は宝憧院(ほうどういん)付近にあるという”左板橋街道と右岩槻街道の道標”を発見したくて、朝6時10分自宅を出発した。南北線「本駒込」⇒「赤羽岩淵」→(徒歩)→(宝憧院)→(赤羽本町通り)→(徒歩)→JR「赤羽」⇒「駒込」と一筆書き周遊をして来た。
「赤羽岩淵」で下車し、宝憧院へと向かう道にはまだ多くの雪が残っていたが、寺前にある下写真の道標を簡単に発見。その上には”宝憧院前の道標”の掲示板があった。
下写真は不鮮明でもあり、提示版の説明文の概略を綴ると、
『道標は江戸時代の元文年間に僧侶了運によって建立されました。宝憧院前は板橋道が日光・岩槻道と合流する位置でしたので、銘文には「東 川口善光寺道 日光岩付(ソノママ)道」・「西 西国富士道 板橋道」・「南 江戸道」と刻まれています』とあり、日光・岩槻道が岩淵から川口へと船で渡り、鳩ヶ谷・大門・岩槻の宿場を経て幸手宿で日光街道に合流する道筋とも書かれている。

この碑を発見した喜びもあったが、3日前にこの寺前を通り、見逃してしまった自らの迂闊さに忸怩たるものもあり、喜びも半ば。 帰りは「南 江戸道」方向にある本庁町通りを歩きながら、新幹線の向こう側に建つビルを望んで、岩槻街道がこちらまで一直線に繋がっていたことを直観した。大正初期に造られた鉄道(多分京浜東北線)によって岩槻道が分断されたことを確信した。帰宅後地図で調べた。それを右の図で示すことにする、。
帰りは「南 江戸道」方向にある本庁町通りを歩きながら、新幹線の向こう側に建つビルを望んで、岩槻街道がこちらまで一直線に繋がっていたことを直観した。大正初期に造られた鉄道(多分京浜東北線)によって岩槻道が分断されたことを確信した。帰宅後地図で調べた。それを右の図で示すことにする、。
A⇔B と C⇔D(本町通り)はともに岩槻街道。Eは宝憧院。岩槻街道は日本橋側からA→B→C→D→Eと進み、Eの宝憧院前で板橋道と合流し、右折していたのだ。鉄道で分断された様子が読み取れる。
何処で右折しようと、どうでも良いことだが、物好きの詮索事である。
桐ヶ丘高校の I さんから”依頼品完成”の連絡を受けて、2月13日(木)11時30分に訪ね、昼食も一緒に摂る約束をした。それでは、会う前に赤羽から荒川まで岩槻街道を歩こうと、昨日2回目の街道散策に出掛けて来た。
岩槻街道に宿は6つあり、江戸から幸手へ、岩淵宿⇒川口宿⇒鳩ヶ谷宿⇒大門宿⇒岩槻宿⇒幸手宿 と続く51Kmの道程。その最初の宿岩淵に至り、新河岸川・荒川を越えようと計画した。
特に確かめたいことは2つ。
(a)赤羽を過ぎでから、どこで右折したか?
(b)荒川をどのように越えたか?
今回は自宅を8時半出発。赤羽まではJRを利用した。赤羽で下車し、西口改札を出る。
ネット等で調べると(a)については3つの説があるようだ。結論を先に書いてしまえば、下に掲示した写真の多分②が正しいと思う。①はネット上で書かれている。③は駅付近の”石の地図”に書かれていたルート。②もネットで紹介されていた。私は往きに①を、帰路に②を通った。
②と考える最大の理由は、このルート上の「宝憧院付近に左板橋街道と右岩槻街道の道標があること」(②説記述にある。私は撮影は出来ていない。後日の撮影を考えている)と、道の流れがスムースである点にある。
往きは、新幹線に沿って300mほど進むと445号線と交差し、ここを右折後ガードを潜り445号線沿いに進んだ。地下鉄南北線「赤羽岩淵」駅の辺りで445号線は終点となり、ここからは、右折して来る国道112号線を進む。この道路、現在は北本通りと呼ばれる道路で、当然のことながら、江戸時代の街道より道幅が広く、街道の面影を留めるものは少ない。
10分ほど行くと、新河岸川にぶつかる。架かる橋の名前は”新荒川大橋”。渡ると直ぐに荒川のゆったりとした流れが目に入る。こちらの橋の名前も”新荒川大橋”。どうやら2つの橋は一つの橋とみなされているようだ。橋上から暫し風景を楽しむ。遠くに霞むは秩父の山塊か。エルザタワー55がひときは高く聳える。下流には岩淵水門の赤門と青門も見え、東京スカイツリーも遥か彼方に。 渡り切るとそこは埼玉県川口市。今回はここで引き返すことにするが、この道路がかっての岩槻街道であることを示す縁を探すと、漸く右のような道標を見つけ一安心。
渡り切るとそこは埼玉県川口市。今回はここで引き返すことにするが、この道路がかっての岩槻街道であることを示す縁を探すと、漸く右のような道標を見つけ一安心。
帰路、新河岸川傍の「小山酒造」に寄る。”丸眞正宗”の醸造所。20数年前に、酒蔵見学に訪れたことがあった。入口には湧水があったが今は無い。高いビルが建ち、醸造場所も奥へ引き込んだようだ。I さんへのお土産に吟醸酒を買いながら、そんな昔話を女将と話し込み、ここでの渡しに付いて聞いてみた。
荒川を、将軍様たちはどのように越えたのかに興味・関心があった。その当時、多分橋は架けられていない。船で渡ったであろう。その痕跡はないか探したが何も見当たらず、その手掛かりを小山酒造の女将に聞いたのだ。すると”私の家より数件先の小田切さんの家にはその昔、舟が吊るしてあった”とのこと。
帰宅して再度ネットを調べると次の解説文を見出した。
『岩淵宿は岩槻道の初宿であって『遊暦雑記』には日本橋から三里八町、宿の長さは四町二十一間、道幅四間とある。旅篭屋は若松屋大黒屋が有名で本陣は小田切氏が代々勤める。川口と合い宿として月の前半後半で宿場の役目を交代した。実際にはほとんどが日光街道の千住宿を利用したのであまり活気はなかったようだ。と新修北区史にある。』
偶然にも、小山酒造付近で見つけた「史跡 岩槻街道岩淵宿問屋場址之碑」。この近辺が岩淵宿で、本陣が張られ、渡しをも管理していたのではないかと推理した。
帰路②の赤羽本町通りはそこが街道筋だったような商店街。
(b)は具体的には何もわからなかった。今後は文献を探すことにしよう。
今回のブログは写真が多いので、この下にまとめて11枚掲示
(①説:青線 ②説:赤線 ③説:黒線)

(宝憧院謂れの掲示板) (宝憧院の碑)

(新河岸川) (エルザタワー55)
(地下鉄南北線「赤羽岩淵」駅付近) 

(岩淵水門) (岩槻街道岩淵宿問屋場址之碑))
(
(荒川の流れ:新荒川大橋から下流を眺める)

(小山酒店の販売所) (ここの銘柄は丸眞正宗)
 2月7日(金)、千葉市立美術館に出かけ”江戸の面影”と題する実に多くの浮世絵を観てきた。その数272点。その殆どが千葉美所蔵作品だから、この美術館の浮世絵蒐集は凄い。
2月7日(金)、千葉市立美術館に出かけ”江戸の面影”と題する実に多くの浮世絵を観てきた。その数272点。その殆どが千葉美所蔵作品だから、この美術館の浮世絵蒐集は凄い。
章立てを見るとどんな浮世絵が展示されていたのか一目瞭然である。
プロローグ 江戸の繁栄
第一章 吉原の粋
第二章 江戸の盛り場
第三章 江戸娘の闊達さ
第四章 歌舞伎への熱狂と団十郎贔屓
第五章 江戸っ子の好奇心
第六章 愛しき日常と子どものパラダイス
第七章 花を愛でる人々
第八章 富士の絶景
エピローグ 江戸の面影
一概に江戸時代といても265年の長期にわたる。浮世絵は、その長い江戸時代のその時々に流行したものを描いて、時の人々の関心を引き、高度な木版画技法=錦絵によって安価に広く普及してきた。多くの大衆を享受者に巻き込んだ、世界でも珍しいこの芸術を、今回の企画では、面白い形式で私たちに伝えてくれる。
すなわち、幕末~明治初期に来日した外国人達の旅行記や、江戸時代の狂歌や随筆を手掛かりにして、浮世絵が表現してきた事柄を解き明かしてくれる。例えば吉原に象徴される”性をひさぐ”女性たちが、蔑みを持って描かれてはいないことは外国人から見て驚きであったらしい。又、時計(だったか?)を持った外国人をみて、混浴の銭湯から全裸で飛び出してきた男女を見たときの驚きも語られているが、そこから日本人の持つおおらかさを感じた様子が書かれている旅行記もある。
私的感想だが、私の知っている多くの世界が、目の前に登場することが、浮世絵を見る大きな喜びだ。飛鳥山の花見が、隅田川の花火が、七福神が、両国の風景が、山王祭が、芝居小屋が、市川団十郎が、あの景清が、富士山等々が登場する。江戸時代の人々がエネルギッシュに快楽を求めてあちらこちらを彷徨う様子が伝わってくる。江戸市民の日常が窺える。 特に面白かったのは鳥文斉栄之『三福神吉原通い図絵巻』だ。七福人のうち、福禄寿・恵比寿・大黒天の“三人“が、舟に乗るところから始まり、最後は花魁たちに囲まれての饗宴に至るまでの絵巻。楽しげに、浮かれる神様たち。彼らも吉原に憧れたという設定がユニークだ。
特に面白かったのは鳥文斉栄之『三福神吉原通い図絵巻』だ。七福人のうち、福禄寿・恵比寿・大黒天の“三人“が、舟に乗るところから始まり、最後は花魁たちに囲まれての饗宴に至るまでの絵巻。楽しげに、浮かれる神様たち。彼らも吉原に憧れたという設定がユニークだ。
私が好きな鍬形斉(前名 北尾政美)の作品も数点展示され、特に登場人物数千人とも見える『東都繁昌図巻』と『江戸名所図会』を興味津々と眺めた。2時間近くの鑑賞。歩くより疲れることを実感。(写真:三福神吉原通い図絵巻より)
有難いことに、今回もチケットを家人の友人Fさんから頂いた。
往きは都営新宿線を利用し、帰りはJRを錦糸町で途中下車。「魚寅」で、お安いマグロぶつとタコぶつを買って帰ってきた。
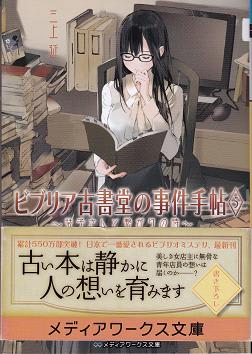 北鎌倉駅の駅脇にあるビブリア古書堂。その店主栞子さんは、初対面の人とは満足に口もきけないほどの人見知りで、接客商売には向いていない人柄ですが、古書の知識は並大抵ではなく、本には人一倍情熱を燃やす、若き女性です。もう一人の主人公で、物語の語り手の俺・五浦大輔は、その店のアルバイト店員。実は、大輔は栞子さんへの、静かにあたためてきた想い告白していました。彼女の答えは「今は待ってほしい」。第5巻では、その答えを待つ大輔のいじらしいほどの苦悩が語られます。読者の私も大輔に感情移入して、はらはらどきどきしながら、一刻も早く返事の内容を知りたくて、先を急ぎ読むことになるのです。
北鎌倉駅の駅脇にあるビブリア古書堂。その店主栞子さんは、初対面の人とは満足に口もきけないほどの人見知りで、接客商売には向いていない人柄ですが、古書の知識は並大抵ではなく、本には人一倍情熱を燃やす、若き女性です。もう一人の主人公で、物語の語り手の俺・五浦大輔は、その店のアルバイト店員。実は、大輔は栞子さんへの、静かにあたためてきた想い告白していました。彼女の答えは「今は待ってほしい」。第5巻では、その答えを待つ大輔のいじらしいほどの苦悩が語られます。読者の私も大輔に感情移入して、はらはらどきどきしながら、一刻も早く返事の内容を知りたくて、先を急ぎ読むことになるのです。
これを横糸として、ビブリア堂に持ち込まれる、古書にまつわるミステリーを縦糸として物語は進みます。プローローグとエピローグに登場する本は『愛のゆくえ』(新潮社文庫)。第一話から第三話には登場する古書は、雑誌『彷書月刊』(弘隆社・彷徨舎)、手塚治虫『ブラック・ジャック』(秋田書店)、寺山修司『われに五月を』(作品社)です。例によって栞子さんの豊富な知識と鋭い推理によって謎は解かれていくのですが・・・。
実は、『われに五月を』に関する謎の提出者は、栞子さんの母親の篠川智恵子です。母智恵子は10年前、夫と娘二人を置き去りにして家を出ていってしまいました。本の知識は栞子さんよりも上。古書をめぐってはライバルともいえる緊張関係にあります。その母からの挑戦。何としてもその謎を解き明かし、母親に会い、是が非でも聞き出したいことが栞子さんにはあったのです。母の思いを聞かなければ、大輔への返事が出来ないと思いつめた栞子さんは、遂に、謎を解き、母に会い、母の思いを聞き出すのでした。
物語は最終局面で大団円のうちに終わるかに見えます。しかし、二人の顔が急接し始めた丁度その時、突然書店のガラス戸がびしりと鋭い音を立てて震えました。かって栞子さんに深い傷を負わせ人物からの石礫です。物語はまだ終わらないのです。そして二人の恋の行方もまだ不透明な余韻を残しての幕。
古書とそれに関する謎は楽しく読めるので、物語が今後も続くのは嬉しいことですが・・・。
550万部も売れているという超人気のこのシリーズ、第5巻も荒川5中の先生から貸して頂きました。
(付記 本文では、栞子さんにだけ”さん”が付けられ、他は全て”さん”・”君”なしです。ブログもそれに倣っています)
、









