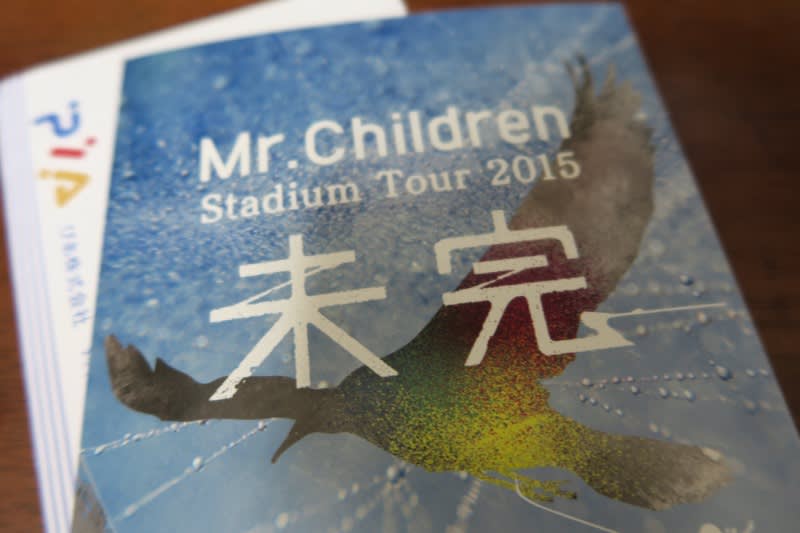「歳をとってきた」というと怒られるかもしれないが、ここ数年は季節ごとの行事や祭りにことのほか惹かれるものがある。
季節の移ろいに敏感になってきたのかもしれない。
とりわけ夏はお祭りや盆行事などイベントが多い。
小中学生の頃といえば、町内会の夏祭りで、食べ物も盆踊りも興味はなく、気になる異性の浴衣などを目当てに駆け回るごく普通の楽しみ方をしていたような気がする。
いざ、東京に出てみると、電車の中づり広告であったりとか、車窓であるとか、あるいは口コミなど祭行事のあることを知ったりもする。
聞いた情報、見た情報に誘われて、知らない場所に訪れる機会も増えた。
花火大会、盆行事、そして夏祭り。
以前から気になっていたねぶた祭りには一昨年と今年の2度見学に赴いた。
夏季の眠気を取り払う「ねむり流し」を起源とするねぶた祭りは、市中にねぶたと呼ばれる大燈籠が練り歩く。
闇夜に灯るねぶたがまた美しいのである。
昼間にスタンバイしているねぶたを見つけて、こんなにも違うものかと思うほど闇夜に映える。
秋田県の竿灯まつりにしかり、夏には明りのお祭りが多いのである。
そんな中、祭りではないものの、灯籠流しも明りにまつわる行事である。
この行事は盆に迎えた祖霊を、灯籠という船(形代)に乗せて送り出すもので、日本各地で行われていた。
仏教の盆と祖霊信仰が中心となって行われていた灯籠流しであるが、近年では意義が曖昧になりイベント化しているものも多い。
死者供養や鎮魂を目的とするものや、平和への祈りを込めたものもある。
さすが多様化の時代である。
私の住む地域にはたいした川もなく、新興住宅街なので灯籠流しの行事はない。
観客として傍から見学するだけにはなってしまうけれど、それでも灯籠の淡い光に誘われて、灯籠流しを見に行ったのであった。
東京下町の浅草では、8月15日に「浅草夜のまつり とうろう流し」が行われている。
どうやら、結構昔から行われていたようである。
浅草といえば、隅田川。
日の沈んだ宵の隅田川に人々が灯籠を流すのである。
宗教的な雰囲気は無く、浅草観光連盟に事前予約をすれば誰でも自分の灯篭を流すことができる。
友人の話によると、当日でも並べば灯籠を購入することができるそうだ。(無くなり次第終了)
灯籠が流されるのは水上バス発着所に程近い隅田公園だ。
18時半を過ぎて、あたりが暗くなってくる頃には、公園には灯籠流しの長い列ができている。
水上バス発着所のあたりから、東武鉄道の鉄橋の近くまで列をなしている。
老若男女、国籍を問わず、多くの人が並んでいる姿が見受けられる。
この灯籠は一基1500円で購入できるそうで、簡易組み立て式なので、紙面に願いを書き込むこともできる。
灯籠を購入した人は、そうめん流しのレーンのような場所で自分の灯篭を流して、川へと流れていくのを見守る。
私は灯籠は購入せずに、デッキで水面に移る淡い灯を見物しようと待っていた。
川と言えども、隅田川。
もう河口に近く、流れの少ない場所なので、吾妻橋付近(灯籠の流される場所より少し河口)で待っていたが、岸辺に滞留してしまった灯籠はなかなか流れてこない。
じっと待っていると、ゆっくり、ゆらりゆらりと時間をかけて灯籠が少しづつ流れてくる。
時間の流れがゆるやかで、都会の喧騒をしばし忘れてしまいそうである。
気付けば、自分のすぐ下を灯籠が通り過ぎてゆく。
遠景の東武線や近景の吾妻橋と相まって、非常に美しいのであるが、灯籠流し見物の屋形船がすべてをぶち壊してしまっているのが残念だ。
紙でつくられた、非常に繊細な灯籠が流れているというのに、近くを通るため、幾度も岸に追いやられ、仕舞には横転して無残な残骸が流れてくる。
しかしこれが、盛り場の宿命というものであろう。
良くも悪くもここは浅草なのである。
ところ変わって、2014年の相模川 小倉橋灯ろう流しである。
相模原市緑区、圏央道相模原ICの付近にある小倉橋下河原で行われている。
開催されるのは毎年8月16日だ。
のどかな自然と、近代的な架橋の対比が美しい場所だ。
津久井湖と城山ダムも近いこの土地は、切り込んだ谷になっていているが交通の要所でもあり旧来は小倉の渡しがあった。。
その後、1938年には小倉橋が架けられたが、交通量の増加から休日を中心に渋滞が多発したため、2004年に片側2車線を有する新小倉橋がつくられた。
新小倉橋は相模原台地から突き出したように架けられているため、相当な高さがあり橋脚部には景色が眺められるスペースが設けられていたりもする。
さて、そんな交通の変化もあり相模原中心部からもずいぶんと訪れやすい土地になった小倉橋で行われる灯ろう流しは橋のライトアップと共に、明かりが美しいイベントだ。
新小倉橋まで自転車を走らせ、急斜面を下っていけば下河原だ。
土手には夜店が立って、会場には篠笛のBGMが流れている。
非常に混んでいるという様子でもなく、地元の人々が集っているような、そんな雰囲気である。
家族連れが多く、お盆の終わりに家族で灯籠を流しに来たのだろう。
場所柄もあり、暗いので灯籠の明りがいとおしい。
橋も会場もライトアップされているが、これがなかったら本当の闇夜になってしまうくらいに、自然が濃い。
石が転がる河原を進んでいくと、相模川が流れがあって、灯籠も思った以上の速さで流れていく。
灯籠のかたちもなんだかおしゃれ。

河原に座って、ぼんやりと流れていく灯籠を眺める。
人々のいる明るい場所から、暗い場所へと、ゆらゆら流れていく灯籠を見つめて、夏の終わりを感じてしまうのは私だけではないだろう。
流れていった灯籠はやがて見えなくなる。
祖霊を迎えた盆も終わり、祖霊は帰っていく。
それぞれが祈り、去っていく灯に虚無感のようなものを味わう。
これは非日常から日常への回帰でもある。
盆行事の延長として行われているからこそ、その寂しさがいっそう感じられたのであった。
川のほとりに一人の老人がいて、流れに乗ることができずに岸に戻って来てしまった灯籠を、木の枝で「トン」とつついていた。
私はその老人が、この世とあの世の中間にいる存在のように思えてならなかった。