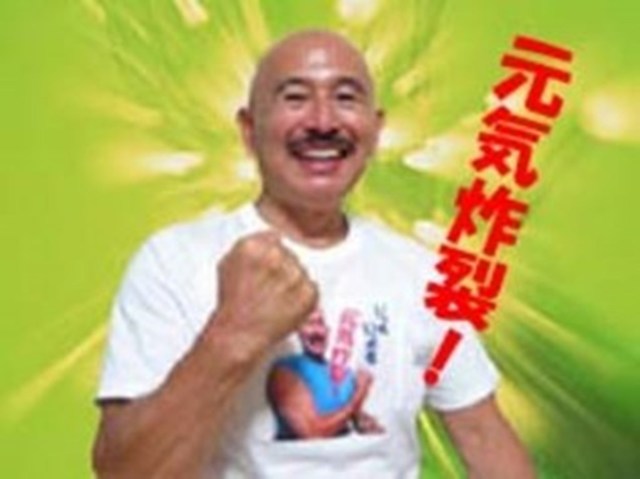1週間ほど前、ブログ友で読書家のすずさんが梨木香歩さんの著書
「冬虫夏草」について説明されていた。
私は以前に何かで世にも不思議な「ゾンビキノコ」といわれる
「冬虫夏草」のことを知り、その成長のメカニズムなどを調べたことを
思い出し、虫(特に幼虫)が嫌いな私は一瞬背筋が寒くなるような
感情と同時に何故タイトルが「冬虫夏草」なのだろうという思いで
すずさんへのコメントを書いたのだが・・・
すずさんから「冬虫夏草」の本についての説明や同じ作家の他の著書に
ついても解説や解りやすく丁寧な説明があり、さらにこんな一文が
あった。
『ちなみに、この作家さんで最も分かりやすいのは、「西の魔女が死んだ」
です。最初はこちらがお勧めかな、と思いましたので。 』・・と。
スピリチュアルとは・・・ということもよくわからない私だが、大きな
意味では大自然について、誰もが思ったり、考えたりすることや一人一人の
持つ精神的なものと捉えれば、「霊的」「心霊的」なものや「宗教的」な
ものと言うより広義では大自然を相手にしたいろんなことにも繋がる
ものなのかな?と信仰心の薄い私にも何となくわかるような気がして、
梨木香歩さんの書に触れてみることにした。
私の行く図書館には生憎「西の魔女が死んだ」や『沼地のある森を抜けて』が
なかったので、他のタイトルの3冊を借りてきた。
そのうちの1冊「家守奇譚」を読み始めたのだが、な、なんと・・
過日のすずさんの記事で紹介された「冬虫夏草」はこの「家守奇譚」の
続編であるという。
「冬虫夏草」についてのすずさんの説明の一部に
『何処か懐かしい、とても美しい日本語で綴られています。』とあったが
読み始めたばかりでもそれは随所に感じられた。
さらに言葉やその表現にも・・・
例えば言葉としてわかっていても普段あまり使われない「疎水」「洋燈」
「釣果」や文字として書く場合も本来の漢字よりもひらがなで書きがちな
「迂闊」「狼狽える」「蔓延る」「益体もない」「掠める」「上がり框」
「漆喰」「魚籠」「此方」「縋る」など・・・
そして話し言葉ではあまり使われない「興がる」や「癇性」「却を経る」
などという言葉も自然に無理なく目に入ってくるのでやはり日本語は
いいなあ~という思いが強くなってくるのだ。
主人公と周りの人たちとの微笑ましい関係、掛け軸から抜け出てくる
友人(故人)家の周りの動植物の不思議な行動、妖怪、あるいは幽霊を
思わせる事柄にも恐怖心や嫌悪感などは起きず、物語りの進行とともに
植物が登場し、最初に登場する擬人化されたサルスベリも次のヒツジグサも
意思を持ったものとして描かれているが違和感なく読める。
28章中のまだサルスベリ、都わすれ、ヒツジグサ、ダァリヤ(ダリア)
ドクダミの4章までしか進んでいないがその間も季節(四季)の様子が
見事に描かれている。
ヒツジグサ=睡蓮だということを初めて知った。
僅か(?)155ページなのですずさんならあっという間に読破・・・
というところだと思うが私は速読もできないので登場する人物や動物、
植物、妖怪などの相関関係をしっかりと把握しながら…ということに
なるので少し時間がかかりそう・・・
読み終えるころは私にも少し優しい気持ちが芽生えてくるだろうか・・・・
あと2冊はもう少し先になりそうだ。