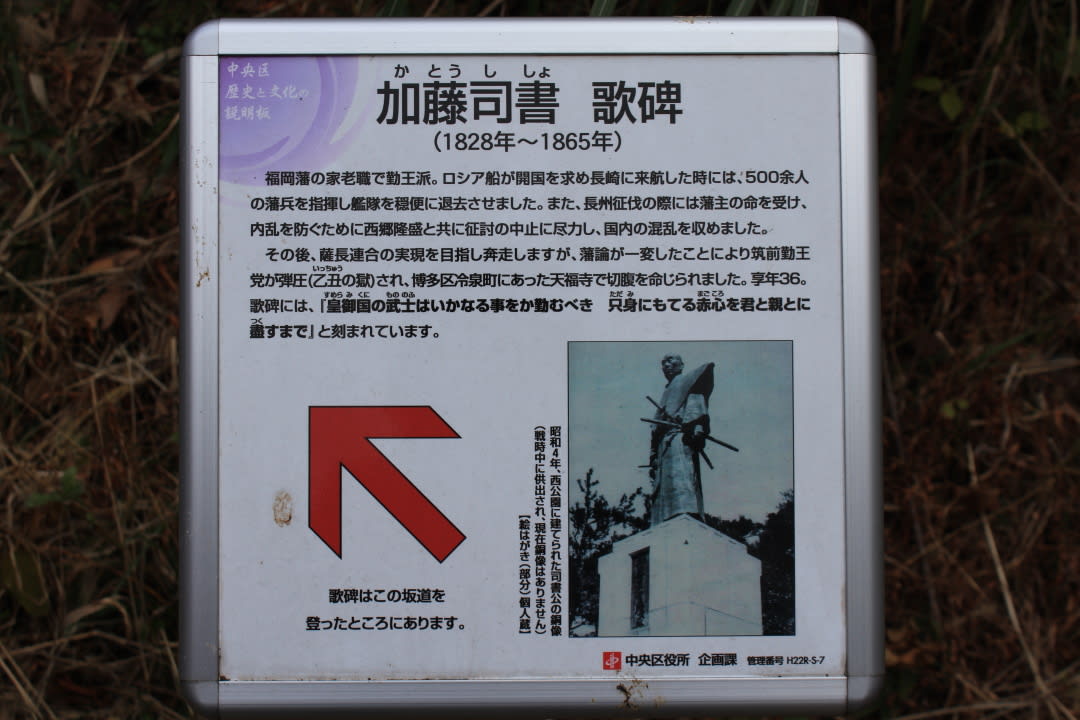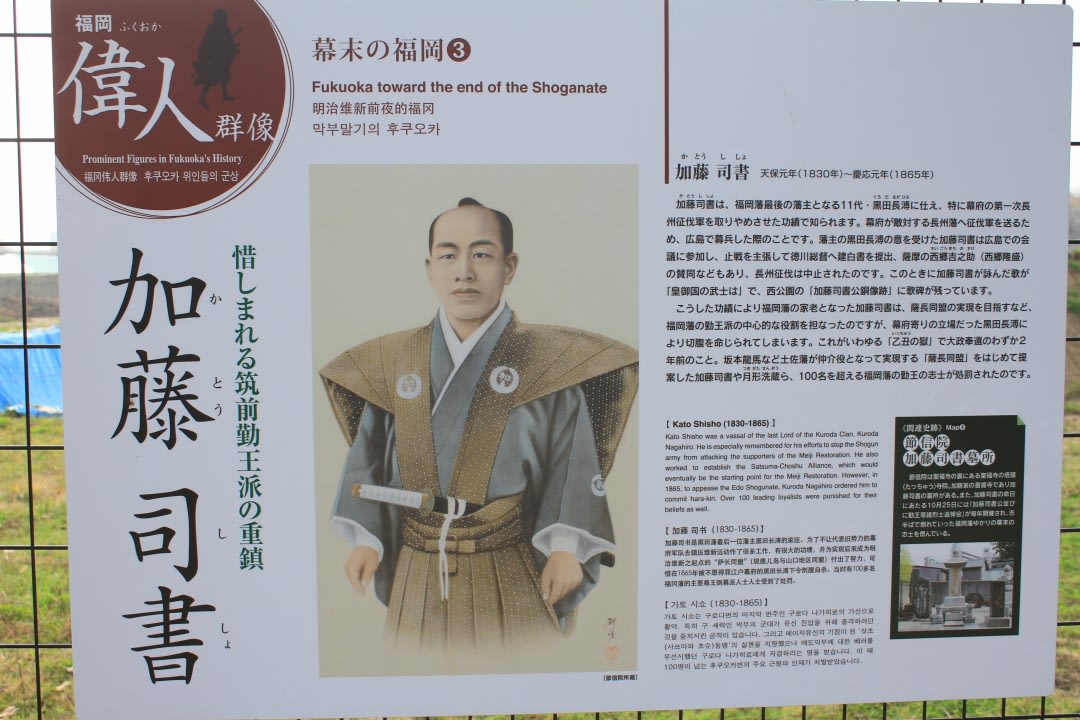黒田長溥の兄弟は薩摩藩主の他、中津藩主、盛岡藩主を継ぎ、姉妹は桑名藩主、大垣藩主、郡山藩主、新庄藩主などに嫁していました。

徳川時代の260余年の間、全国の各大名は姻戚を結び合い、黒田家も1万石以上の大名100家以上と姻戚を結び、親族は400家に及んだそうです。
 この熱い血で結ばれた武家の時代をたやすく変革することはできませんでした。そのためか、明治維新では全国で2万から3万人の尊い血が流されたと言われています。
この熱い血で結ばれた武家の時代をたやすく変革することはできませんでした。そのためか、明治維新では全国で2万から3万人の尊い血が流されたと言われています。

徳川時代の260余年の間、全国の各大名は姻戚を結び合い、黒田家も1万石以上の大名100家以上と姻戚を結び、親族は400家に及んだそうです。