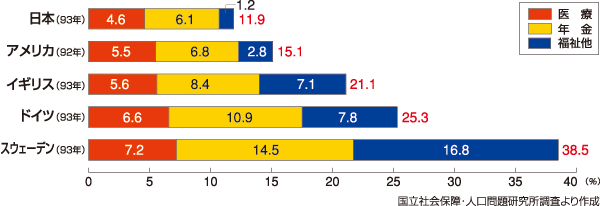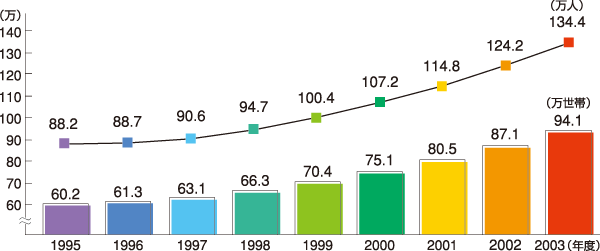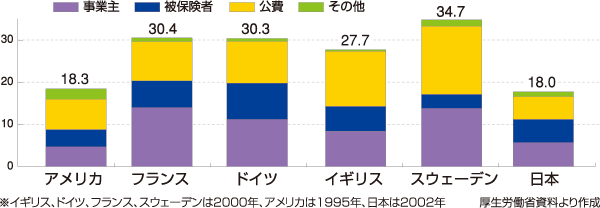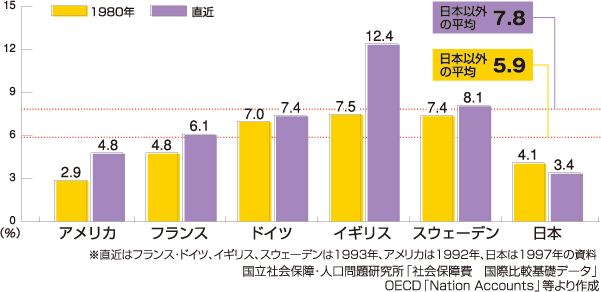第2章 なぜ少子化が進行しているのか
第2章 なぜ少子化が進行しているのか
第1節 少子化の原因
第1章では、少子社会の現状について解説してきたが、こうした出生率の低下という少子化の現象はどのような原因で生じてきたのであろうか。
前述した晩婚化の進展や夫婦出生力の低下などが、少子化の直接の原因として指摘されている。
そこで、本章では、少子化の原因やその背景にある要因としてこれまで取り上げられてきた主な事項について、最近のデータを基にあらためて分析する。
本章で少子化の原因やその背景にあるものとして取り上げる項目は、次のとおりである。
なお、本章全体の分析を整理すると次のフローチャートのとおりである。

1 晩婚化・未婚化の進展
(未婚率の上昇)
わが国では、子どもは男女が結婚してから生まれる場合が大半であるので、結婚しない人たちの割合が増加すれば、子どもの出生数に影響を与えることになる。
総務省「国勢調査」によると、2000(平成12)年の全国における20~39歳の未婚者数は、約1,833万人であり、男性が約1,040万人、女性が約793万人である。

また、国勢調査によれば、20~34歳の未婚率は、1950(昭和25)年から80(昭和55)年頃までは、男性が約50%、女性は約33%と、さほど変化がなく推移をしてきた。

5歳年齢階級別の未婚率をみると、1980(昭和55)年と2000(平成12)年を比較して、男性の場合、25~29歳では55.1%から69.3%へ、30~34歳では21.5%から42.9%へと倍増し、女性の場合、25~29歳では24.0%から54.0%へと倍増し、30~34歳では9.1%から26.6%へと3倍になっている。
女性の25~29歳では、1970年代では「5人に1人が独身」であったが、30年間に「2人に1人が独身」という状態に変化している。

(晩婚化の進展)
1980年代後半から合計特殊出生率の低下が社会的に知られ始めたが、当時は、晩婚化の進展による「出産の先送り現象」のために、一時的に出生率が低下したものであり、いずれ晩婚化傾向が一段落をすれば、出生率は回復するであろうと認識されていた。
20~30歳代の未婚率の上昇等により、生涯未婚率(50歳時点で結婚していない人の割合)も近年上昇している。
国民の全てが結婚をするという「皆婚社会」が、いまや崩れつつある状況に至っている。

(独身者の結婚意思)
未婚者の生涯の結婚意思について5年ごとに調査している「出生動向基本調査」(国立社会保障・人口問題研究所)によると、

結婚する意思は高いにもかかわらず、未婚の人が多い理由は何だろうか。
25~34歳では、「適当な相手にめぐり合わない」をあげる人が最も多いが、以前よりは割合が低下している。

(婚外子割合の国際比較)
これを欧米諸国と比較をすると、スペイン、イタリアといった南ヨーロッパでは低いものの、いずれの国も日本よりもはるかに高い水準にある。
たとえば、スウェーデンでは、サムボと呼ばれる事実婚カップルが、サムボ法という法律により、法律婚カップルとほぼ同様に保護されている。また親子法により、サムボカップルの子どもに対する法的差別も全くない。内閣府経済社会総合研究所編「スウェーデン家庭生活調査」によれば、このように制度が整備されていることもあり、法律婚カップルの9割以上がサムボを経験しており、法律婚への移行過程として機能していると考えられる。サムボはライフスタイルのひとつとして社会に受け入れられ、現在では生まれてくる子どもの半数以上が婚外子である。ただし、出生順位別にみると、第一子の婚外子率は65%に達するものの、第二子では44%、第三子では29%に減少しており(1990年代)、サムボが法律婚に移行する前の段階として定着していることを示している。
| (%) | ||
| 年 | 嫡出でない子の割合 | |
|---|---|---|
| 日本 | 2003 | 1.93 |
| 1980 | 0.80 | |
| アメリカ | 2002 | 33.96 |
| アイスランド | 2003 | 63.60p |
| スウェーデン | 2003 | 56.00 |
| ノルウェー | 2003 | 50.00 |
| デンマーク | 2003 | 44.90 |
| フランス | 2002 | 44.30 |
| イギリス | 2003 | 43.10p |
| フィンランド | 2003 | 40.00 |
| オランダ | 2003 | 31.30p |
| ドイツ | 2003 | 26.20p |
| スペイン | 2003 | 23.20e |
| イタリア | 2002 | 10.80e |
| 資料: | 日本は厚生労働省「人口動態統計」、米国は疾病管制局(CDC)資料、その他の国はEuro-Statによる。 |
| 注: | eは推計値、pは速報値 |
(妊娠・出産と結婚との関係)
厚生労働省「人口動態特殊報告‐出生に関する統計‐」(2001(平成13)年)によれば、結婚期間が妊娠期間より短い出生数は増加傾向にあり、2000(平成12)年では、嫡出第1子出生数の約4分の1を占めている。これは20年前と比較をすると、約2倍の増加となっている。母の年齢階級別にみると、10代後半では8割、20代前半では6割、20代後半では2割となっており、年齢層が若くなるほど多くなっている。
同棲の状況についてみると、毎日新聞社の「第1回人口・家族・世代世論調査」(2004(平成16)年)1によると、15%の女性が「同棲をしている。または過去に同棲の経験がある」と答えている。30代前半では21%に上っている。こうした状況からみると、わが国でも結婚前に、あるいは同棲中に妊娠するという事態が少なくないものと想像できるが、出産となると、いわゆる「できちゃった婚」のように法律上の結婚という行為と密接に結びついている。
なお、10代後半など若い世代の「できちゃった婚」の中には、親としての準備などが整っていないため、若い夫婦のそれぞれの親やきょうだい、地域、行政における支援が必要な場合が多いものと考えられる。
2 夫婦の出生力の低下
国立社会保障・人口問題研究所「第12回出生動向基本調査」(2002(平成14)年)によれば、夫婦に対して、理想的な子どもの数(理想子ども数)と、実際に持つつもりの子どもの数(予定子ども数)を尋ねたところ、結婚期間が短い夫婦ほど、理想、予定子ども数とも少なくなっている。全体の平均では、理想子ども数は2.56人、予定子ども数は2.13人であるが、結婚持続期間が5~9年の夫婦では、理想子ども数2.48人、予定子ども数2.07人、同じく0~4年の夫婦では、理想子ども数2.31人、予定子ども数1.99人となっている。結婚持続期間が0~4年という結婚後5年未満の夫婦の場合、以前の調査では現在よりも高い数値を示していた。たとえば、1987(昭和62)年調査では、理想子ども数2.51人、予定子ども数2.28人であった。90年代以降、理想、予定子ども数ともに比較的急に低下しつつある。
このように最近における結婚持続期間が短い夫婦では出生力の低下傾向がうかがえるが、その原因は後述する様々な要因に加えて、バブル経済崩壊の心理的影響が夫婦の出生力の低下に影響を与えているのではないか、晩婚化による出生力の低下が夫婦の出生力の低下にも影響を与えているのではないか、自分の子どもに自分以上の高学歴を求める傾向があり教育費等の負担を考慮して、出生抑制を行うなどの影響を与えているのではないか、都市部において継続就業する女性の存在、一方では仕事と子育てを両立できる環境の不十分なことなどが、夫婦の出生力に影響を与えているのではないかなどの指摘がなされている。2