私は、薬は悪であるとは思っていません。
かつて、私自身、内海聡や船瀬俊介氏のファンであったときは、「西洋医学の薬は100害あって一利なし」と考えていました。
しかし、いざ急性症状の時に、薬を使わないと、病気が長引いたりするという経験を嫌と言うほど体験しました。
ひどかったのが、ヘルペスウイルス発症時でした。
ヘルペスとは、過去に罹患したウィルスが神経に眠っていて、体調不良時に「熱の吹き出し」として出てくるものです。
「体調管理できてなかったな」と思って反省しても、ヘルペスはどんどん出てきます。
ですから、体調管理をし直す、しっかり休息をとる+抗ウィルス薬を内服することで、リセットできることが経験的に理解できました。
創薬の歴史を見ていくと、そのほとんどが、生物から抽出された麻薬成分や覚醒剤成分です。
脳、つまり中枢神経に働きかけて、今ある症状を緩和しながら、自己治癒能力を待つのが現代社会の治療法だと思います。
つまり、発症してしまってから、「自然治癒力に頼っていても、もう遅い」のです。
ある意味、それは仕方ないと受け止め、急性症状は薬を使うべきなのです。
ただし、その内服が慢性化しているならば要注意であるため、その部分は生活を見直していく、自分の生活の乱れ、心の乱れを修正していく必要があると思います。
心、考え方が乱れるため、実際の行動、生活が乱れていく。その蓄積が体調不良になり、病気として発現すると考えれば、薬というものは非常に便利なものでもあるし、時として薬頼みになってしまう怖いものでもあります。
市販薬依存症というものが存在し、それは、一般の風邪薬であったりします。
つらい感冒症状に対して内服するのでなく、沈んだ気持ちを癒すために内服しているそうです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(薬物依存、市販薬でも「1日60錠…ラムネ菓子を食べるように」 合法の影で実態見えず 2/23(日) 19:00配信京都新聞)
薬物依存、市販薬でも「1日60錠…ラムネ菓子を食べるように」 合法の影で実態見えず
芸能人の違法薬物問題が注目を集める。
市販薬や処方薬への依存は増加傾向にあるが、その実態は知られていない。
薬物依存症という病と向き合い、回復の道を歩む人たちにとって欠かせないのは、自助グループや家族会などで仲間と出会い、思いや体験を分かち合うことだ。京都府内や滋賀県内に市販薬や処方薬の依存症の自助グループはまだない。市販薬依存とは、回復を支える人とのつながりとは何か、当事者や家族の声を聞きに現場を訪ねた。
■10代で4割、2014年から大幅増
ドラッグストアやインターネットで手軽に買える咳(せき)止め薬などを、高揚感などを求めて大量に摂取する市販薬依存。厚生労働省研究班の2018年全国調査によると、薬物関連治療を受けた患者2609人のうち、風邪薬や頭痛薬といった市販薬の依存症は5・9%。特に10代では市販薬依存の割合が4割を占め、14年調査のゼロから大幅に増えている。
京都府精神保健福祉総合センターと滋賀県立精神保健福祉センターによると、それぞれ府内や県内で市販薬や処方薬に特化した自助グループや家族会は把握していないという。
昨年秋、京都市伏見区の龍谷大であった依存症予防教育についてのフォーラム会場。質疑応答で、一人の女性が声を上げた。「関西に来てから夫が薬を大量に飲み、手に負えないとき、行政や医療の助けを求めても『市販薬でそんなことになるはずがない』とたらい回しにされた。東京では支援や理解があった」
■「風邪薬や鎮痛剤、一日中飲んでいる」
後日、女性に取材した。東京から関西に引っ越してきたアヤコさん(46)=仮名、大阪市東成区。夫が市販薬の依存症という。「1日60錠くらいかな、とにかく何十錠も飲むの。一日中飲んでいる。胃腸薬や下剤やサプリなんかも含めて12種類くらい、ラムネ菓子を食べるように」。夫は2年前から、沖縄の回復施設に入所している。
市販薬で興奮状態になった夫は「養ってやっているのをありがたく思え」「お前のせいだ」と言葉の暴力をふるい続けた。数時間、激高し、薬の効果が切れてくると、罪悪感で落ち込む。摂取する市販薬で夫の症状は違っていた。
禁断症状で、眠る夫の体がバッタのように飛び跳ねる。うわ言のように「止めてくれ」とつぶやいた。多量摂取の副作用で夫は腸閉塞を発症し、入院した。
アヤコさんの心は疲弊していったが、夫婦だからと耐えた。当時の自分の姿を、アヤコさんは少しうつむき、言葉を探しながら、ゆっくり語った。「ずっと怒っていた。怒っている自分のことも責めていた」
■止めても、隠しても、買えてしまう 家族の苦悩
寝る前に風邪薬の黄色い錠剤を大量に摂取する夫。
翌朝、布団には汗で黄色い人型ができていた。アヤコさん(46)=仮名=が「何でこんなことになるまで飲むの」と声を荒らげると、夫は「どうせ俺が悪い。いつもあなたは正しいことを言う」と何かを諦めたように言った。
市販薬依存という病。アヤコさんは言い返せず、「彼も病気なんだ」と、何度も自分に言い聞かせた。
飲むなと止めても、隠しても、すぐに市販薬は買えてしまう。
財布を渡さず、ネットで購入できないようにしてもだめだった。
市販薬依存症の夫との生活を、「悲しさや苦しさ、『夫は変わってくれるかもしれない』という期待が、ごちゃ混ぜになっていた」と振り返る。
アヤコさんは現在、自助グループや家族会に参加、自分と向き合い人生を生き直している。夫とは別々の道を歩むことを選び、離婚協議を進めている。
「同じ境遇の人に、パートナーはパートナー、あなたはあなたでいい。抱え込まず、誰かに話す勇気をもってと伝えたい。誰かに手を差し伸べることが私自身の回復にもつながるから」
■市販薬・処方薬依存症の自助グループ
大阪にある市販薬・処方薬依存症の自助グループを取材した。MDAA(メディカル ドラッグ アディクション アノニマス)は東京で始まり、大阪は2018年にできた。
昨年11月に高槻市内で開かれたミーティングには14人が参加。参加者はニックネームで呼び合い、自分のペースで思いや経験を語っていた。話し手以外は聞くことに徹し、質問や意見はしないのがルールだ。
代表のヒロシさん(仮名)も処方薬依存の経験者。
医療機関で処方された睡眠薬や抗うつ剤を手放せなかった。
なくなれば、医師に処方箋をもらうために通院を繰り返した。
大阪でMDAAが立ち上げられたのは「違法薬物依存のミーティングに、市販薬や処方薬の依存に悩む人たちは入りづらさを感じるとの声があったから」という。
■共感するものがあるからこそ
共感するものがあるからこそ、語ることも聞くこともできる。
「違法薬物と依存症として多くは重なるものの、違法かどうかという点で『自分はこの人たちとは違う』と感じる人もいる。
誰になら語れるか、どこなら通い続けられるかを考え、場所を選ぶのは大事なこと。その選択肢は一つでも多い方がいい」とヒロシさんは語る。
市販薬や処方薬の依存が病だとの認識は、社会や当事者自身も、まだ浅い。処方薬依存では、大量に処方する医師や病院にも責任があると指摘する人もいる。
さらに、合法薬物としてひとくくりにされがちだが、市販薬と処方薬でも問題の捉え方が異なる部分がある。
ヒロシさんは「苦しんでいる人に、あなたは一人ではないということを伝えたい。
同じような経験をしてきた人たちが、自分以外にもたくさんいること。その人たちと回復できるということを知ってほしい。安心して語ることができる分かち合いの場が広がっていくことが目標」と話している。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(転載ここまで)
市販薬例えば、咳止めを多量服薬すると、気持ちが落ち着く、飲まないとやってられないということは、もともと薬というものは、「麻薬の成分を薄めたもの」だということなのですね。
つまり、使い方が大切になってくるわけですが、使い方は当事者が選択できてしまうのが現状です。
実は薬理学ではこのように教えられていません。
作用機序というものを小難しく教えられます。
まさか、市販薬や処方薬が、麻薬からできているとは思いもよらないでしょう。
その理由に、飲み合わせルールというものが存在します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(処方薬と市販薬、注意すべき同時服用 抗うつ剤&鎮痛剤は危険 2020年1月8日 16時0分 NEWSポストセブン 抗うつ剤と鎮痛剤ののみ合わせに注意を)
風邪や便秘、花粉症などのための市販薬を気軽に服用している人も多いだろう。しかし、そんな身近な薬でも、処方薬を服用中は細心の注意が必要。命にかかわる副作用を起こすこともあるのだ。
「よかれと思って、似たような効能のものを重ねのみしたり、相反する作用がある成分を組み合わせて効き目を無効化したりすることで起こりうる副作用は予見しきれません。その大前提は、ぜひ頭の片隅に置いてほしい」(銀座薬局代表、薬剤師・長澤育弘さん)
そこで、知らずにのみ合わせると、重篤な相互作用を起こす可能性もある、処方薬と市販薬との「危険なのみ合わせ」を紹介する。
※監修/長澤育弘さん(薬剤師、銀座薬局代表。薬同士ののみ合わせや副作用に詳しい)
以下、処方薬×市販薬の順番に表記。
◆降圧剤心不全治療薬(カルベジロールなど)、糖尿病治療薬(スルフォニル尿素薬など)×鼻炎薬(プソイドエフェドリン配合)
交感神経を刺激して鼻づまりを改善するプソイドエフェドリンは血圧にも作用するため、高血圧や不整脈の原因となりうる。
◆抗不安剤(ベンゾジアゼピン)×アレルギー性鼻炎薬(抗ヒスタミン薬)
アレルギー性鼻炎薬の抗ヒスタミン剤と抗不安薬のベンゾジアゼピンには共に強い喉の渇きの副作用があり、併用は危険。
◆胃潰瘍の薬(オメプラゾールなど)×便秘薬(ビサコジル配合)
ビサコジル配合の便秘薬と胃酸を抑える薬を服用すると、便秘薬が腸に届かず胃の中で溶け出し、腹痛や吐き気のリスクが。
◆抗血栓剤(ワルファリンカリウム)×解熱鎮静剤(アスピリン、イブプロフェン、ロキソプロフェン配合)
解熱鎮痛剤には血液を固まりにくくする作用があるため、抗血栓剤との相乗効果で出血時に血が止まりにくくなる危険が。
◆抗うつ剤(炭酸リチウム)×解熱鎮静剤(ロキソプロフェンNa水和物配合)
一部の解熱鎮痛薬と抗うつ剤を併用すると腎臓に負担がかかり、吐き気や下痢、耳鳴りなどリチウム中毒症状が出ることも。
※女性セブン2020年1月16・23日号
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(転載ここまで)
要するに、薬という薬は、実際の病気に効果があるのではなく、麻薬か覚醒剤のどちらかの成分を弱毒化して、美味しい効果だけを使っていこうというものだといえます。
ですから、同じような系列の麻薬同士、覚醒剤同士を飲み合わせると、強い効果が出てしまうというだけの話です。
例えば、マリファナ(大麻)は食欲亢進の作用があります。
しかし、長期間マリファナをし続ければ、幻覚や被害妄想が出てきて、気が狂ってしまいます。
マリファナの成分を弱毒化して、上手く投与すれば、食欲亢進だけが効果が出てくるというお話なのです。
やはり市販薬や処方薬が麻薬や覚醒剤と同じ成分だと警鐘を鳴らすサイトはあります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(厚労省の資料「濫用等のおそれのある医薬品の成分・品目及び数量について」)
【症例1】20代女性
風邪を引いて近所の薬局に。咳が強いため咳によく効くという薬(ブロン錠)を購入。使用説明書に眠気が起こるかもしれないと書いてあったので寝る前のみ飲むことにした。薬はよく効き、前日まで咳でほとんど眠れなかったのが昨日は嘘のようによく効きぐっすり眠れた。安眠できたことからその後も寝る前だけこの薬を飲むようになった。気づけば3か月が経過し、なぜか寝る前以外にも飲みたいという衝動がでてきた......。
【症例2】30代女性
以前から頭痛がある。市販のものをいろいろと試したが結局「ナロンエース」が一番"合っている"ことが分かった。最初は週に2~3回しか飲んでいなかったが、最近は1日も欠かせなくなってきている。錠数がどんどん増えてきて1日に10錠以上飲むこともある。頭痛はますますひどくなり薬も増える一方となっている......。
解説していきましょう。【症例1】はエフェドリン(正確には塩酸メチルエフェドリン)とコデイン(リン酸ジヒドロコデイン)の依存症になってしまっているのはほぼ間違いありません。
エフェドリンとは覚醒剤の一種、コデインは麻薬(オピオイド)です。
覚醒剤には気管支拡張作用があり、麻薬には脳の咳中枢を抑制する効果がありますから双方とも咳に効果があるのは事実です(ただし最近はこれらの咳止めには有効性を示したエビデンスがなく使用すべきでないという意見が増えてきています。参照:太融寺町谷口医院ウェブサイト「はやりの病気」第178回(2018年6月)「「咳止めが効かない」ならどうすればいいのか」)。
エフェドリンとコデインを双方摂取するとどうなるか。
現在40代後半以上の人はエスエス製薬の咳止めシロップ「ブロン」が社会問題になったことを覚えているのではないでしょうか。
ちょうど私がひとつめの大学(関西学院大学)の学生だった1980年代後半、この「ブロン」が大流行し、社会復帰できなくなり退学した奴がいる、という噂も何度か聞きました。
真偽は定かではありませんが、当時「ブロン中毒専門の矯正施設がある」と(私の周囲では)言われていました。
それだけ問題になったのですから、製薬会社は当然製品を販売中止するなり成分変更したりすべきです。
そして、たしかにこのシロップは成分が変わりエフェドリンが含まれなくなりましたが、コデインはそのままです。
そして、(私は、これは問題だと思うのですが)「ブロン錠」という錠剤が登場し、こちらはシロップと同様エフェドリンとコデインの双方が含まれているのです。
【症例1】はそのブロン錠を飲み始めて知らぬまに依存症になってしまった例ですが、なかには初めから"トリップ"することを目的としてブロン錠を大量に(なかには一晩で数百錠も!)飲む人もいます。
では販売元のエスエス製薬だけが問題なのかと言えば、そういうわけではなく、メジャーな風邪薬のいくらかはエフェドリンとコデインの双方が含まれています。
例えば、パブロンゴールドA、新ルルA、カイゲン感冒錠、ベンザブロックS、エスタックイブなどです。
私自身は、少なくとも医学部に入学してからは市販の感冒薬や咳止めを一度も飲んでいませんし、こういった薬を飲んでいる医師を見たことがありません。
はっきり言えば、こういった感冒薬は一生飲むべきでないのです。
【症例2】は2つの問題があります。ひとつはイブプロフェン中毒、もうひとつはブロムワレリル尿素(ブロムバレリル尿素とも呼ばれる)中毒です。
前者は「薬物乱用頭痛」と呼ばれるやっかいな頭痛を引き起こすことがよくあり、そもそもすべての痛み止めには依存性・中毒性があると考えなければなりません。
ですが、その何倍も問題なのが後者の「ブロムワレリル尿素」であり、これがどれくらい問題かというと、90年代に社会問題となった『完全自殺マニュアル』でも紹介されている危険な薬物なのです。そもそもこのような薬剤が薬局で買えること自体が問題です。
ブロムワレリル尿素の致死量は15gと言われています。ナロンエース1錠に100mgのブロムワレリル尿素が含まれていますから150錠飲めば(体重にもよりますが)死んでしまうわけです。
しかも『完全自殺マニュアル』には、他に「首吊り」「飛び降り」「ガス中毒」などの自殺方法が紹介されていますが、ブロムワレリル尿素を用いた「クスリ」による自殺は「安らかな眠りの延長上にある死、これが最も理想的な自殺手段だ」と書かれているのです。
こんなもの、販売してもいいのでしょうか。ウルグアイやカナダに負けまいと、多くの州で娯楽用大麻が合法化されている米国でさえ、ブロムワレリル尿素を薬局で販売することは禁じられています。
いったん、ブロムワレリル尿素依存症になってしまうと、これがないと眠れなくなり、切れると頭痛がひどくなってきます。
服薬量がどんどん増えていき、こうなると自分自身の力ではもはや離脱することができません。
尚、ナロンエース以外にブロムワレリル尿素を含む薬剤にウット、奥田脳神経薬があります。
私が院長を務める太融寺町谷口医院では、過去12年間の間に100人以上の「風邪薬・鎮痛薬依存症」になった(知らない間になってしまった)人たちに、危険性を伝え、止めることができるよう支援してきました。
幸いなことに無事離脱できた人もいますが、止めるように言っても理解が得られず受診しなくなった人も少なくないのが実情です......。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(転載ここまで)
医者は普通に知っているのです。
しかし、平然と処方する医者の方が多い。
また私たちも、「何も薬を処方してくれない医者はヤブ医者だ」とマスコミに洗脳されています。
しかしながら、麻薬や覚醒剤成分をいかにも小難しく、エビデンスがあるようにみせかけていることは許しがたいと思います。
アルコールを飲むと、トイレが近くなります。
それは、飲酒によって実際に膀胱に尿がたまっているからでもありながら、バソプレシンという抗利尿ホルモンを阻害するため「おしっこに行きたい」と感じるからだそうです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(お酒を飲むと頻繁にトイレに行きたくなる3つの理由とは? 食事・栄養|2017年10月24日)
ある男が、友人と一緒にバーにいます。そこで彼は、ビールを数杯飲んで談話を楽しんだ後、ふとトイレに行きたくなりました。
すると、友人が「行ってはダメよ。一度トイレに行くと、おしっこの封が切られてしまう」と一言。
英語では、これを「break the seal」といい、お酒を飲んで一度トイレに行くと、そこからは封を切ったように、たて続けにトイレに行きたくなるという都市伝説によるものですが、これは、実際に起こり得る現象なのでしょうか?
ここでは、お酒を飲んで一度トイレにいくと、その後のトイレが近くなるという現象について、その原因を中心に科学的な視点で分かりやすく紹介します。
英語でbreak(壊す)と表現されるように、お酒が体の何かを実際に「壊す」わけではありませんが、どうやらお酒は、膀胱に直接影響を与えているようです。
飲酒量が与える影響
人にはそれぞれ、排尿システムにおける基本的な尿の保有量がありますが、お酒を飲む場合、飲酒量が多いほど新しい尿がたくさん作られていきます。
お酒を飲み始めて、まず最初に出されるのは古い尿ですが、飲むペースが速いほど、新しい尿は、つぎつぎと作られていきます。新しい尿は、老廃物が少ないクリーンな尿なので、尿道を滑るようにして速く通過し、膀胱を短時間で満たしていきます。
一般的に、膀胱の水分保有量の平均は、2カップくらいで、膀胱がどれだけ速く満タンになるかは、その人がどれだけお酒を飲んだかによります。
たとえば、ウィスキーをショートグラスで飲むよりも、ビールをグラス1杯飲む方が膀胱は早く満たされるというわけです。
アルコールの利尿作用による影響
アルコールに利尿作用があるのは事実です。
利尿作用とは、通常よりも、体の水分をより多く失わせる働きを意味します。アルコールの利尿作用は、人が脱水状態になるときに、体内に水分を吸収するように腎臓に指令を送る「バソプレシン」と呼ばれるホルモンの分泌をブロックすることによって引き起こされます。
そうなると、体が、実際よりも体内水分量が多いと勘違いしてしまい、通常よりももっと水分を排出しようとします。
最初のトイレタイム後から、おしっこを我慢できなくなる理由
一般的に、水分を摂取するとトイレに行きたくなるのは生理的現象のひとつです。
しかし、研究によって下記のことが新たに分かってきました。
お酒を飲んだ場合、最初のトイレタイムで排尿したときに、脳が爽快感を覚え、その後は、脳から5分や20分おきなど立て続けに排尿を促すような催促が起こることも分かってきました。
そうなると、人は「トイレに行かなければならない」と頻繁に感じるようになるというわけです。
トイレへ行くのを我慢してもいい?
お酒を飲むことはやめられない人が、もしトイレを我慢すると、尿路感染症(にょうろかんせんしょう)のリスクを高めます。
同時に、尿漏れを防いでいる括約筋を損傷してしまう可能性もあります。
まとめ
お酒を飲むと、アルコールによる利尿作用と、短時間に行われる大量の水分摂取がともに組み合わさって膀胱を刺激し、排尿に直接的な影響を与えていきます。
それによって、尿の回数が増えるかもしれませんが、実際にお酒の水分で膀胱が満タンになるのも速くなっているので、トイレは決して我慢しないでください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(転載ここまで)
「お酒を飲み始めて、まず最初に出されるのは古い尿ですが、飲むペースが速いほど、新しい尿は、つぎつぎと作られていきます。新しい尿は、老廃物が少ないクリーンな尿なので、尿道を滑るようにして速く通過し、膀胱を短時間で満たしていきます。」とあります。
実際、心不全患者で強い利尿剤をかけられているハルンバッグの尿の正常は、薄い尿が多いです。
つまり、利尿剤は麻薬成分=麻酔成分だということです。
それをループ利尿薬、ACE阻害剤、A-II受容体拮抗剤など小難しく説明しているだけかもしれません。
麻酔成分が強いもの、弱いものと成分を変えているだけなのでしょう。
利尿剤「フロセミド」の薬剤説明のサイトには、以下の通り禁忌、注意事項が書かれています。
「脱水」です。
アルコールも脱水から不整脈になってしまいます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(宮崎薬剤師会 アルコールのお話)
■質問■
例えば、どのような影響でしょうか。
体内に入ったアルコールは胃や腸から吸収され、血液中に入り全身を回り麻酔作用により酔いを起こします。酔いの状態は血中アルコール濃度により異なりますが、急激に高くなると死亡することもあります。怖いですよね。
また、アルコールには水分を奪う(脱水作用)・水分を出す(利尿作用)などがあります。
■回答■
■質問■
だから、喉が渇くのですね。
そして、体内に入ったアルコールは主に肝臓の酵素の働きで最終的には水と炭酸ガスに分解され体外に出ていきます。この分解する酵素の働きの強弱により個人差が出てきます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(転載ここまで)
アルコールは食べ物ではなく、薬物です。
利尿剤は、エチルアルコールを薄めているだけでしょう。
実際に、利尿剤には「肝機能障害」が副作用でありますから、冷静に考えれば、利尿剤は麻酔薬でありアルコールであると考えても自然なのです。
このように、私たちは、アルコールや覚醒剤などを上手く弱毒化して、メリットのある部分だけを利用して、生活しています。
このこと自体は悪い事ではありません。
しかしながら、薬を飲み続けなくてはならないといった慢性化してしまうのは、医療の責任だと言わざるを得ません。
長期薬物の内服を必要とされる慢性疾患はもはや慢性疾患でも何でもなく、「治療失敗による薬物依存」と言い換えるべきなのではないでしょうか?










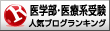

















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます