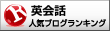『秋』
6. 鍋の季節だ。
⇒ 『鍋』、『鍋料理』というのは日本特有のもののようで、これまたなかなか通じにくいものの部類に入る。日本に来て初めて見たという外国人も多い。英語を話すというのは、単に単語を置き換えるのではなく、やはり異文化コミュニケーションであるから、相手がわからないという前提で話すということが大切である。相手も知っている、という甘えは禁物である。もちろん人間なので同じもの、普遍性というものもある。英語で話す際、我々は、相手と共通する所と、異なる所が両方あるという前提で話すことが異文化コミュニケーションをスムーズにこなす鍵であろう。
一応、『鍋』には、a hot pot なる英訳が充てられているようである。しかし日本通を除けば、これですぐわかるとは言い難い。相手に通じなければ、通じるまで、あの手この手で通じさせる気概が必要である。
鍋を知らない外国人に、どう説明するか。
まず、関係ありそうな英単語を考えてみる。
材料は、野菜で vegetables. 具体的に言ってもいい。他に肉ならmeat。具体的には 豚肉(pork) や牛肉(beef) 、鶏肉(chicken)も入れるだろうし、魚(fish)も入れるか。動作でいうと、料理するはcook、煮込むので、ボイル(boil)。野菜を刻むので、簡単にカット (cut)辺り。鍋のだし汁は、簡単にスープ(soup)にしよう。
こちらも語彙が限られているので、知っている英語を片っ端からぶつける感じになるだろう。異文化コミュニケーションの場合、双方に同じものが無い場合、似たものを出して、相手にイメージを与えるのが得策である。
鍋に似た西洋の料理? 冬に食べるし、シチュー(stew)か? 似てないが、とりあえず、It's something like a stew. と言っておいて説明していくといい。
ちなみに stew を英英辞典(oxford)で調べると、
stew: a dish of meat and vegetables cooked slowly in liquid in a container that has a lid. とある。肉と野菜を使った料理で、蓋(lid)のある入れ物(container)に入った液体(liquid)で、ゆっくりと調理(cooked)したもの、とのこと。
説明だけ見ると、鍋っぽい。使える。
・It's like a stew. You use vegetables and meat. You boil them in water or soup. We often eat them in a cold winter. We put a big pot on a table, cook them and eat together with a family or friends.
鍋の特徴は、調理しながら同時進行で食べられることである。具材だけの説明では物足りない。なぜ鍋がこよなく愛されるか。一緒に(一人鍋もあるが)仲間、家族と談笑しながら、常に暖かいものを食べられるということだろう。そのあたりも伝えたい。
・It's like a barbecue. You can cook and eat at the same time. (同時に作って食べられる)
・It's like a barbecue. You can cook and always eat hot things in a cold winter. (寒い冬なのに、暖かいものが食べられる)
上記の訳、説明は非常に稚拙だろうし、まとまりもない。くだらない訳である。何を言いたいのかというと、特に日本的な事象でもそうだが、訳に決まったものはないということ。分からないから辞書を引く。それでは解決しないものなのだ。
決まったものがない、模範解答がないということは困ったものだが、逆に言うとそれは自由だということ。本人の裁量でいくらでも表現できるということ。
英語は、本来考えられているより、もっと自由なもので、学習者が自分の感性や、これまでの経験、イメージをもっと組み込めるものだと思う。英語?わからない!ネイティブに聞こう、ネット翻訳にかけよう。そうではない。自分なりの英語、自分なりの答を出す。間違ってもいいから、堂々と自分で考えて英語を話す。それが大事だと思う。
日本人の『完成』に対する美意識。中途半端なものを出すことへの抵抗。高度で洗練された伝統と文化をもつ日本であるが、『完成』という意識が時に、英語学習を邪魔しているということに気付く必要がある。
未完成でよい。中途半端でいい。くちゃくちゃでもよい。、日本を代表して英語を話そう。中途半端で行く。それは勇気である。
『鍋の季節だ』。季節はseason である。使っても使わなくてもいい。要は『寒い』ので鍋がいい、ということ。
・It's really cold now. It's good to have "nabe". It's a Japanese dish, ~ .
・Now is the best time to eat "nabe" in Japan. Nabe is something you eat in winter. It's ~ .
など。
最後に、古代ギリシャの将軍ペリクレスの言葉を紹介する。
『幸福は自由より生じ、自由は勇気より生ず』
『英語は自由である。自由は考えることから生ず』
これは私。
以上。
6. 鍋の季節だ。
⇒ 『鍋』、『鍋料理』というのは日本特有のもののようで、これまたなかなか通じにくいものの部類に入る。日本に来て初めて見たという外国人も多い。英語を話すというのは、単に単語を置き換えるのではなく、やはり異文化コミュニケーションであるから、相手がわからないという前提で話すということが大切である。相手も知っている、という甘えは禁物である。もちろん人間なので同じもの、普遍性というものもある。英語で話す際、我々は、相手と共通する所と、異なる所が両方あるという前提で話すことが異文化コミュニケーションをスムーズにこなす鍵であろう。
一応、『鍋』には、a hot pot なる英訳が充てられているようである。しかし日本通を除けば、これですぐわかるとは言い難い。相手に通じなければ、通じるまで、あの手この手で通じさせる気概が必要である。
鍋を知らない外国人に、どう説明するか。
まず、関係ありそうな英単語を考えてみる。
材料は、野菜で vegetables. 具体的に言ってもいい。他に肉ならmeat。具体的には 豚肉(pork) や牛肉(beef) 、鶏肉(chicken)も入れるだろうし、魚(fish)も入れるか。動作でいうと、料理するはcook、煮込むので、ボイル(boil)。野菜を刻むので、簡単にカット (cut)辺り。鍋のだし汁は、簡単にスープ(soup)にしよう。
こちらも語彙が限られているので、知っている英語を片っ端からぶつける感じになるだろう。異文化コミュニケーションの場合、双方に同じものが無い場合、似たものを出して、相手にイメージを与えるのが得策である。
鍋に似た西洋の料理? 冬に食べるし、シチュー(stew)か? 似てないが、とりあえず、It's something like a stew. と言っておいて説明していくといい。
ちなみに stew を英英辞典(oxford)で調べると、
stew: a dish of meat and vegetables cooked slowly in liquid in a container that has a lid. とある。肉と野菜を使った料理で、蓋(lid)のある入れ物(container)に入った液体(liquid)で、ゆっくりと調理(cooked)したもの、とのこと。
説明だけ見ると、鍋っぽい。使える。
・It's like a stew. You use vegetables and meat. You boil them in water or soup. We often eat them in a cold winter. We put a big pot on a table, cook them and eat together with a family or friends.
鍋の特徴は、調理しながら同時進行で食べられることである。具材だけの説明では物足りない。なぜ鍋がこよなく愛されるか。一緒に(一人鍋もあるが)仲間、家族と談笑しながら、常に暖かいものを食べられるということだろう。そのあたりも伝えたい。
・It's like a barbecue. You can cook and eat at the same time. (同時に作って食べられる)
・It's like a barbecue. You can cook and always eat hot things in a cold winter. (寒い冬なのに、暖かいものが食べられる)
上記の訳、説明は非常に稚拙だろうし、まとまりもない。くだらない訳である。何を言いたいのかというと、特に日本的な事象でもそうだが、訳に決まったものはないということ。分からないから辞書を引く。それでは解決しないものなのだ。
決まったものがない、模範解答がないということは困ったものだが、逆に言うとそれは自由だということ。本人の裁量でいくらでも表現できるということ。
英語は、本来考えられているより、もっと自由なもので、学習者が自分の感性や、これまでの経験、イメージをもっと組み込めるものだと思う。英語?わからない!ネイティブに聞こう、ネット翻訳にかけよう。そうではない。自分なりの英語、自分なりの答を出す。間違ってもいいから、堂々と自分で考えて英語を話す。それが大事だと思う。
日本人の『完成』に対する美意識。中途半端なものを出すことへの抵抗。高度で洗練された伝統と文化をもつ日本であるが、『完成』という意識が時に、英語学習を邪魔しているということに気付く必要がある。
未完成でよい。中途半端でいい。くちゃくちゃでもよい。、日本を代表して英語を話そう。中途半端で行く。それは勇気である。
『鍋の季節だ』。季節はseason である。使っても使わなくてもいい。要は『寒い』ので鍋がいい、ということ。
・It's really cold now. It's good to have "nabe". It's a Japanese dish, ~ .
・Now is the best time to eat "nabe" in Japan. Nabe is something you eat in winter. It's ~ .
など。
最後に、古代ギリシャの将軍ペリクレスの言葉を紹介する。
『幸福は自由より生じ、自由は勇気より生ず』
『英語は自由である。自由は考えることから生ず』
これは私。
以上。