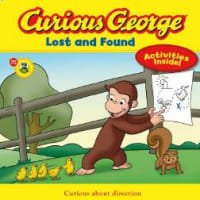「その男は禅僧にもかかわらず、詩と酒と女をこよなく愛した。
破戒に手を染めながらも、命を投げ打ち修行に身を投じた。
尊き血を持ちながら権門に目を背け、腐敗する禅を痛烈に指弾した。
名を、一休宗純という。 」
巻頭はこの文から始まる。一休禅師についての伝記風小説。史実をもとにして著者が考究した一休宗純像がフィクションとして見事に紡ぎだされている。
奥書を読むと、本作は「小説すばる」(2023年4月号~11月号)に連載された後、大幅な加筆修正を経て、2024年6月に単行本が刊行された。
巻頭の1ページの末尾は「人々は、一休についてこう評した。 その狂気、量るべからず----と。」
7月の朝日新聞に「愚かでもいい 一休さんからの応援歌」という見出し、「木下昌輝さん新刊 長編『愚道一休』」という副題で、著者がインタビューに応じた記事が掲載されていた。切り抜いた記事に日付をメモするのを失念。河合真美江さんの署名入り記事。この中に著者の言葉が引用されている。著者はいう。「愚かな人だと思った。でも、生き方が芸術品なんです」と。そして、本書のタイトル「愚道一休」の「愚道」は「求道」をかけた言葉として、自然に思いついたという。冒頭の二行がまさに、愚道と求道を一休宗純の生きざまの両面として言い表わしているように思う。
純粋に真の禅を極めようと志し、求道に邁進した一休が、愚道をも駆け抜ける生きざまを取るようになった。求道と愚道が、一休というコインの裏表として一体である生きざま。そこに徹した一休の存在そのものを描きだそうとしていると感じた。
堺の町に行きそこで布教を実践する一休らが布教に苦闘している時に、養叟からの書状が届く。そこに”風狂子一休”とだけ書かれていた(p241)。この一行が一休の生きざまを変える契機となったと著者は描いていく。
さて、このストーリーは、十刹の一つ、臨済宗の安国寺で稚児として仕える幼名・千菊丸、12歳の心境叙述から始まる。千菊丸は、「千菊丸や、たくさん勉学するのですよ。そして、えらいお坊さんになるのですよ」という母の言葉に送られて数え年6歳で安国寺に入った。母の願いはこの俗世にあり力のある寺で息子が栄達することである。だが、千菊丸がこれまでに眺めてきたのは、僧侶の風紀が乱れた実情である。学ぶことで満たされている日々に中で、僧侶の日常の負の側面を見ている。つまり、僧侶としての出発地点に立つ以前から、臨済宗の寺内の矛盾の中に投げ込まれている。宗派を問わず、当時の禅宗の寺々の実情が如何なる状態だったかについて、端々で触れていく。
千菊丸(一休)は、長じるまで己の出自を知らなかったようだ。母は教えようとはしなかった。千菊丸の出自はいずこか高貴な血筋という噂だけは寺内に伝わっていた。そんな、状況からこのストーリーが始まっていく。そして、薪村にある酬恩庵の一室で森と称する女性に看取られながら一休宗純が没するまでの生き様が描き出されていく。
この伝記風長編小説を大きな流れで捉えると次の諸点が織り込まれ、相互に絡み合いながら、一休の生きざまが変転していく様を描き出す。
1.時代背景は、足利幕府の室町時代後半。南北朝が形として統合されていたとはいえ、北朝優位であった。奈良吉野の方には南朝の後裔が盤踞したままである。さらに応仁の乱へと時代は推移していく。
2.千菊丸(一休)が、己の出自を究明しようとする行動が要所要所に織り込まれていく。一休の出自について、関りを深めていく人物が現れる。赤松越後守。彼は野望を抱いていた。一休にとっては、赤松越後守を避けて遠ざかることができない縁があきらかになっていく。
3.千菊丸は五山三位、建仁寺の知足院の慕哲禅師のもとで、得度し周建という法諱を与えられ、僧侶となる。建仁寺では詩偈の分野で頭角を現していく。だが、破門の身となり、妙心寺で修行し洛外の西金寺で修行に明け暮れる謙翁の会下に参じる。謙翁から宗純の法諱を得る。たまたま赤松越後守を介在する形で、托鉢修行中の禅僧養叟と再会する。
謙翁の没後、養叟が師と仰ぐ堅田・祥瑞庵の華叟宗曇に一休は師事する。一休と養叟の縁がこの後生涯にわたって深まっていく。つまり、一休の生き様に養叟との関わり方が大きく影響を及ぼす。そのプロセスが本作の後半でもある。
4.赤松越後守を介して、一休は山名小次郎との縁が始まっていく。山名小次郎とは後に山名宗全と名乗る人物。一休は禅と公案を介して小次郎との関係が深まっていく。
山名宗全は後に、応仁の乱の首魁の一人になっていく。
5.禅にとり公案は悟道修行の手段である。本書では主に2つの公案がストーリーの底流として息づいていく。一つは「趙州無字」。もう一つは「南泉斬猫」。もちろん、その他にもいくつかの公案が登場してくる。公案とはどういうものか、その一端を感じることができる。
著者はインタビュー記事で、「はからいをなくす」という意識に触れている。
本作には現成公案、かな文字の公案という問題にも触れていて、興味深い。
6.人生の後半において、一休は一面では愚道を突き進む。そこに登場するのが地獄大夫と自称した女性と、地獄大夫の道を継承する森という女性である。
例えば、著者は地獄太夫に、一休への言葉として、こう語らせる。「私は、時にあなた方、お坊さんたちのいうことが馬鹿らしく思えることがあります。悪業を身につければ修羅道や地獄道に堕ちる、と。噴飯ものだと思いませんか。どうして、今の世がましなものだと思っているのか。こここそが、地獄道なのではと、なぜ疑わないのか」(p324)と。実におもしろい。修行とは何かに跳ね返っていく。
桜木陣内が一休に「陣内殿、お主、変わったな」とからかうと、陣内から返される。
「風狂は以前からでしたが、どこか型にはまっているというか・・・使命ゆえにという風がありました。ですが、今はちがいます。心の底から風狂を楽しんでおられる。吹く風に身を楽しげに委ねておられまするぞ」(p404) と。
そして、その後に、こんな一文がつづく。「何かのはからいが解けたから、民たちが一休の風狂の列に加わるようになったのではないか」(p404-405)
風狂に徹したその先に、一休宗純の求める真の禅が生き様と一体化して存在したのではないか。
あの時代におおいて、一休宗純という禅者は生き方において妥協しない稀有な人だったと感じる。
あの時代を感じ、一休さんを感じるために、一読を勧めたい。
ご一読ありがとうございます。
補遺
一休宗純 狂雲集 :「松岡正剛の千夜千冊」
一休宗純『狂雲集』は読んではいけません 太田哲二 :「医薬経済ONLINE」
こころを読む「漢詩に見る日本人の心」 宇野直人(共立女子大教授):「おっさんの残された日」
一休さん、狂った雲を見る 鈴木創士 :「現代思潮新社」
一休骸骨 :ウィキペディア
一休骸骨 :「国書データベース」
一休骸骨 図叛と訳注 :「禅文化研究所」
ネットに情報を掲載された皆様に感謝!
(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません
その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。
その点、ご寛恕ください。)
破戒に手を染めながらも、命を投げ打ち修行に身を投じた。
尊き血を持ちながら権門に目を背け、腐敗する禅を痛烈に指弾した。
名を、一休宗純という。 」
巻頭はこの文から始まる。一休禅師についての伝記風小説。史実をもとにして著者が考究した一休宗純像がフィクションとして見事に紡ぎだされている。
奥書を読むと、本作は「小説すばる」(2023年4月号~11月号)に連載された後、大幅な加筆修正を経て、2024年6月に単行本が刊行された。
巻頭の1ページの末尾は「人々は、一休についてこう評した。 その狂気、量るべからず----と。」
7月の朝日新聞に「愚かでもいい 一休さんからの応援歌」という見出し、「木下昌輝さん新刊 長編『愚道一休』」という副題で、著者がインタビューに応じた記事が掲載されていた。切り抜いた記事に日付をメモするのを失念。河合真美江さんの署名入り記事。この中に著者の言葉が引用されている。著者はいう。「愚かな人だと思った。でも、生き方が芸術品なんです」と。そして、本書のタイトル「愚道一休」の「愚道」は「求道」をかけた言葉として、自然に思いついたという。冒頭の二行がまさに、愚道と求道を一休宗純の生きざまの両面として言い表わしているように思う。
純粋に真の禅を極めようと志し、求道に邁進した一休が、愚道をも駆け抜ける生きざまを取るようになった。求道と愚道が、一休というコインの裏表として一体である生きざま。そこに徹した一休の存在そのものを描きだそうとしていると感じた。
堺の町に行きそこで布教を実践する一休らが布教に苦闘している時に、養叟からの書状が届く。そこに”風狂子一休”とだけ書かれていた(p241)。この一行が一休の生きざまを変える契機となったと著者は描いていく。
さて、このストーリーは、十刹の一つ、臨済宗の安国寺で稚児として仕える幼名・千菊丸、12歳の心境叙述から始まる。千菊丸は、「千菊丸や、たくさん勉学するのですよ。そして、えらいお坊さんになるのですよ」という母の言葉に送られて数え年6歳で安国寺に入った。母の願いはこの俗世にあり力のある寺で息子が栄達することである。だが、千菊丸がこれまでに眺めてきたのは、僧侶の風紀が乱れた実情である。学ぶことで満たされている日々に中で、僧侶の日常の負の側面を見ている。つまり、僧侶としての出発地点に立つ以前から、臨済宗の寺内の矛盾の中に投げ込まれている。宗派を問わず、当時の禅宗の寺々の実情が如何なる状態だったかについて、端々で触れていく。
千菊丸(一休)は、長じるまで己の出自を知らなかったようだ。母は教えようとはしなかった。千菊丸の出自はいずこか高貴な血筋という噂だけは寺内に伝わっていた。そんな、状況からこのストーリーが始まっていく。そして、薪村にある酬恩庵の一室で森と称する女性に看取られながら一休宗純が没するまでの生き様が描き出されていく。
この伝記風長編小説を大きな流れで捉えると次の諸点が織り込まれ、相互に絡み合いながら、一休の生きざまが変転していく様を描き出す。
1.時代背景は、足利幕府の室町時代後半。南北朝が形として統合されていたとはいえ、北朝優位であった。奈良吉野の方には南朝の後裔が盤踞したままである。さらに応仁の乱へと時代は推移していく。
2.千菊丸(一休)が、己の出自を究明しようとする行動が要所要所に織り込まれていく。一休の出自について、関りを深めていく人物が現れる。赤松越後守。彼は野望を抱いていた。一休にとっては、赤松越後守を避けて遠ざかることができない縁があきらかになっていく。
3.千菊丸は五山三位、建仁寺の知足院の慕哲禅師のもとで、得度し周建という法諱を与えられ、僧侶となる。建仁寺では詩偈の分野で頭角を現していく。だが、破門の身となり、妙心寺で修行し洛外の西金寺で修行に明け暮れる謙翁の会下に参じる。謙翁から宗純の法諱を得る。たまたま赤松越後守を介在する形で、托鉢修行中の禅僧養叟と再会する。
謙翁の没後、養叟が師と仰ぐ堅田・祥瑞庵の華叟宗曇に一休は師事する。一休と養叟の縁がこの後生涯にわたって深まっていく。つまり、一休の生き様に養叟との関わり方が大きく影響を及ぼす。そのプロセスが本作の後半でもある。
4.赤松越後守を介して、一休は山名小次郎との縁が始まっていく。山名小次郎とは後に山名宗全と名乗る人物。一休は禅と公案を介して小次郎との関係が深まっていく。
山名宗全は後に、応仁の乱の首魁の一人になっていく。
5.禅にとり公案は悟道修行の手段である。本書では主に2つの公案がストーリーの底流として息づいていく。一つは「趙州無字」。もう一つは「南泉斬猫」。もちろん、その他にもいくつかの公案が登場してくる。公案とはどういうものか、その一端を感じることができる。
著者はインタビュー記事で、「はからいをなくす」という意識に触れている。
本作には現成公案、かな文字の公案という問題にも触れていて、興味深い。
6.人生の後半において、一休は一面では愚道を突き進む。そこに登場するのが地獄大夫と自称した女性と、地獄大夫の道を継承する森という女性である。
例えば、著者は地獄太夫に、一休への言葉として、こう語らせる。「私は、時にあなた方、お坊さんたちのいうことが馬鹿らしく思えることがあります。悪業を身につければ修羅道や地獄道に堕ちる、と。噴飯ものだと思いませんか。どうして、今の世がましなものだと思っているのか。こここそが、地獄道なのではと、なぜ疑わないのか」(p324)と。実におもしろい。修行とは何かに跳ね返っていく。
桜木陣内が一休に「陣内殿、お主、変わったな」とからかうと、陣内から返される。
「風狂は以前からでしたが、どこか型にはまっているというか・・・使命ゆえにという風がありました。ですが、今はちがいます。心の底から風狂を楽しんでおられる。吹く風に身を楽しげに委ねておられまするぞ」(p404) と。
そして、その後に、こんな一文がつづく。「何かのはからいが解けたから、民たちが一休の風狂の列に加わるようになったのではないか」(p404-405)
風狂に徹したその先に、一休宗純の求める真の禅が生き様と一体化して存在したのではないか。
あの時代におおいて、一休宗純という禅者は生き方において妥協しない稀有な人だったと感じる。
あの時代を感じ、一休さんを感じるために、一読を勧めたい。
ご一読ありがとうございます。
補遺
一休宗純 狂雲集 :「松岡正剛の千夜千冊」
一休宗純『狂雲集』は読んではいけません 太田哲二 :「医薬経済ONLINE」
こころを読む「漢詩に見る日本人の心」 宇野直人(共立女子大教授):「おっさんの残された日」
一休さん、狂った雲を見る 鈴木創士 :「現代思潮新社」
一休骸骨 :ウィキペディア
一休骸骨 :「国書データベース」
一休骸骨 図叛と訳注 :「禅文化研究所」
ネットに情報を掲載された皆様に感謝!
(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません
その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。
その点、ご寛恕ください。)