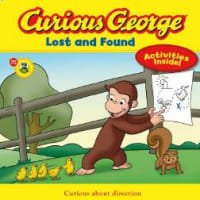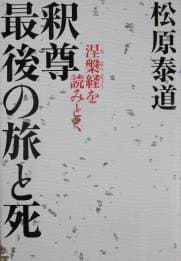
著者は「序章 私の老病死」と題して、”九死に一生”をくり返してきた人生を簡略に語り、自らの老いと死に思いを寄せる。その上で「齢九十五にして、釈尊の老いと死を見つめる」という立ち位置で釈尊の最後の旅と死を主題にした涅槃経を取り上げて、読者に語りかけていく。平成15年(2003)4月に単行本が刊行された。
調べてみると、著者は2009年、肺炎により101歳で死去されていた。合掌。
本書が出版された95歳時点以降も、数々の著作を残されているようである。
著者は第一章で、釈尊の臨終(死)の場面をまず取り上げる。つまり、「釈尊の涅槃」の状況を語る。我々が「涅槃図」として目にする場面である。
著者は釈尊の死を主題にして、上座部仏教と大乗仏教の両方で4世紀の頃に「涅槃経」が作られたと言う。それぞれに複数の訳経があるため、様々な「涅槃経」が存在することをまず明らかにしている。上座部の涅槃経では釈尊入滅の前後、つまり釈尊の最後の旅と入滅の前後が主たる内容に取り上げられている。一方、大乗の涅槃経では釈尊の入滅という厳粛な時機において、釈尊が入滅前に説かれた教義の内容を取り上げている。両者には釈尊の涅槃の取り上げ方に観点の相違がある点を指摘している。この点が本書での最初の学びであった。
著者は、上座部の説く「涅槃経」をベースにして、第二章・第三章で、釈尊晩年の三大悲劇と80歳で故郷を目指した釈尊の最後の旅の経緯について、それらの要点を読者に分かりやすく語っている。大きめのフォントを使い、語り口調の平易な文は読みやすく、理解しやすい。
三大悲劇とは何か? 1)釈尊の生国カピラヴァスツと釈迦族の滅亡。2)同年代の幼ななじみである提婆達多(だいばだった)の叛逆。3)釈迦が後継者と目していた愛弟子、舎利弗(しゃりほつ)と目連(もくれん)の死。これらがまず、語られていく。
第1の悲劇では、コーサラ国の大軍がカピラヴァスツに向けて進軍する街道の沙羅の枯木の下で、釈尊が坐禅するという行動を三度くり返したと言う。三度は釈迦族殲滅作戦が挫折したとか。そもそもの原因は釈迦族の背信行為にあるそうで、結局釈迦族は殲滅する。このことを本書で初めて私は知った。
第2の悲劇は、提婆達多にそそのかされ、阿闍世王が起こす父殺しと提婆達多が新教団を誕生させ釈尊から離反することである。阿闍世王のことは『観無量寿経』の教えとの関連で多少知識はあった。しかし、『法華経』の第十二品「提婆達多品」に、提婆達多に対する釈尊自身の思い、慈悲心が寓話で示唆しているということを本書で知った。著者は釈尊の心を、友松圓諦訳『発句経』五を例示して説いている。
まこと恨み心は/いかなる術(すべ)を持つとも/恨みを懐くその日まで
ひとの世にはやみがたし/うらみなさによりてのみ/うらみはついに消ゆるべし
こは易(かわ)らざる真理(まこと)なり
第3の悲劇は、釈尊の入滅を間近にして、舎利弗と目連が死ぬという悲劇である。例えば、漢訳の『仏説阿弥陀経』は仏が舎利弗に語る形で描かれている。これだけでも舎利弗が高弟だったとわかる。舎利弗と目連が釈尊の弟子となった経緯が本書に書かれている。また、舎利弗が病死し、目連が伝道の途中で殺され非業の死を遂げたことを本書で学ぶ機会になった。
この時の釈尊の思いは、やはり詩に託されたという。有名な章句だ。
自らを洲(しま)とし、自らを依りどころとして、他を依りどころとしてはならぬ
法を洲とし、法を依りどころとして、他を依りどころとしてはならぬ
第二章で三大悲劇を語り、第三章はいよいよ80歳で故郷を目指す釈尊の最後の旅、死出の旅路の要所要点が語られていく。この最後の旅について、多少の予備知識はあったが、本書でその経緯を整理して理解できた次第。
最後の旅において、釈尊は最後まで己の思いを説きつづけたことが語られていく。ここでは、『発句経』からの引用と説明、此岸から彼岸へ渡る六つの方法(六波羅密:布施・持戒・忍辱・精進・禅定・智慧)、「自灯明・法灯明」、「天上天下、唯我独尊」の本当の意味、「上求菩提 下化衆生」、「生きる縁を大切にせよ」の内容がわかりやすく説かれていく。
釈尊が最後まで説かれたのは、「自灯明・法灯明」の教えであった。そして最後の説法を次のように締めくくられたそうである。これも初めて学んだこと。
「汝ら且(しば)らく止みね(靜にせよ)、また語(もの)いうことなかれ、時(とき)まさに過ぎなんとす。われ滅度せんと欲す。『この世はすべて壊法(えほう:無常・移り変わりゆく)なり。放逸(怠けて修行に専心できないこと)することなく精進(自己完成に励むこと)すべし』これが我最後の教誨(きょうげ:教えさとす)するところなり」
実に耳の痛い言葉と感じる・・・。
ここに上座部仏教の特徴が表れているようである。人間釈尊の死を素朴に語っていき、釈尊の法を説くという立場が貫かれている。
本書の特徴は、この後の第四章を大乗仏教の立場から釈尊の涅槃を説明することに転じていることだ。釈尊が説かれた仏法は、いつ・どこにでも開示されている。この法の常住を中心に釈尊の思想を大乗仏教の経典『大般涅槃経』は説いていると言う。私にとっては、白紙の経典であり、本書でその要点をいくつか学ぶ機会になった。その要点を箇条書きで覚書を兼ねてご紹介したい。詳しくは本書を開いてみてほしい。
*法の象徴としての釈尊は「如来常住」。人間釈尊の死は法を伝える上では方便。
*涅槃のさとりの面を中心に「常楽我浄」(常徳・楽德・我德・浄徳)の四德目を説く。
⇒德:そのものに本来具わっているすぐれた資質という意味
「常楽我浄」を備えるのは法身の釈迦である。
注意点:涅槃経のいう常は、常と無常の相反する二つの見方を止揚統合して創られた
常であるということ。それは創造された常観である。
楽・我・浄もまた同様の思考プロセスを経て創造された楽観・我観・浄観
*「一切衆生 悉有仏性」(命あるものは、すべて仏となる性質(可能性)を内に持つ
⇒「仏性」は大乗経典では涅槃経で初めて登場する言葉だという
*涅槃経は「一闡提(いつせんだい)」ですら成仏できると説く。
⇒一闡提は梵語イッチャンテイカの音写語で<欲望ある人・欲望を持つ人>から
目の前の欲楽を追求して、自分の人間的成長を願ったり、心身のやすらぎな どを思ってもみない人のこと。
⇒異論も多く、長い間論争されてきたが、大勢としては「闡提成仏」の思想は
大乗仏教思想の根幹となっていると言う。
上座部仏教と大乗仏教の双方が伝える「涅槃経」理解への奥は深いのだろう。本書は、その入口を一歩入って学び始める入門書として、分かりやすくて読みやすい一書だと思う。長らく書棚に眠らせていた本書をやっと通読して「涅槃経」群に少し踏み込む動機づけにすることができた。
最後に、本書で印象深い文をいくつか引用してご紹介しておこう。
*釈尊の言葉をそのまま記憶するよりも、釈尊の教えの精神を象徴的に表現するねらいが、大乗仏教徒にあったようです。・・・・(「仏」を釈尊に限定せず、「法を知りしもの、道をさとりひもの」の説を「仏説」と解するように、必ずしも釈尊の説でなくともよし、とするのが大乗仏教者の通説です) p196
*「大乗仏教経典を理解するには、象徴文学を理解するように読まないと、その底に秘められた教えを正しく納得できない」ーー--と喝破したのは・・・・岡本かな子さんです。p196
*人間が(本当の)人間になるために必要なのは、「自分に秘められている仏性を自覚する」こと、つまり「真実の人間性にめざめる」ことです。それはまた自分が済(すく)われることでもあります。自分を済う大きな機能は、自分の中に潜在しているとするのが、大乗仏教の人間観です。 p230-231
*人間が度(すく)われるということは、個々に具わる自己の仏性を自覚して、「人間はどうあるべきか」と自らうなずきとることでなければなりますまい。仏性とか仏心とかいう仏教用語を平たくいうなら、”自分の身に生まれながらに具わっている自分を自分であらしめる根元的な心”となるでしょう。この根元的な心は、また「命」とも、「もう一人の自分」と言い換えてもいいでしょう。 p259
*人間をリードする大いなる力や権威を、多くの宗教は天など人間の外界に設定します。しかし大乗仏教は、人間を人間たらしむる超人間的な機能を、人間の外界ではなく人間の内部に凝視するところに、その特徴があります。それだけ人間性を高次に考え、人間を尊重いたします。こうした思想を完全にまとめたのが、涅槃経です。 p233
*如来(仏に同じ)の名称は、「釈尊が得たさとりの内容」、菩薩の名称は、「釈尊が積まれた数々の修行の内容」です。たとえば、釈尊が積まれた忍耐の修行を、人に踏まれ汚物にまみれる土になぞらえ、その徳の豊かさを人格化して「地蔵」菩薩として崇めます。そのため、忍耐する柔軟な心を象徴して、彫刻でも絵画でも柔和な容姿に表すのです。 p256
ご一読ありがとうございます。
補遺
大般涅槃経 :ウィキペディア
涅槃経 :「コトバンク」
大般涅槃経 : 現代意訳 :「国立国会図書館デジタルコレクション」
松原泰道 :ウィキペディア
松原泰道 宗教家 :「NHKアーカイブス」
松原泰道先生の思い出 2022.08.03 今日の言葉 :「臨済宗円覚寺派大本山 円覚寺」
Vol.06 松原泰道「私が彼土でする説法の第一日です」(最終回) 禅僧のことば
細川晋輔 臨済宗妙心寺派 龍雲寺 住職 :「わたしと仏教」
岡本かの子 :ウィキペディア
インターネットに有益な情報を掲載してくださった皆様に感謝します。
(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。
その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。
その点、ご寛恕ください。)
調べてみると、著者は2009年、肺炎により101歳で死去されていた。合掌。
本書が出版された95歳時点以降も、数々の著作を残されているようである。
著者は第一章で、釈尊の臨終(死)の場面をまず取り上げる。つまり、「釈尊の涅槃」の状況を語る。我々が「涅槃図」として目にする場面である。
著者は釈尊の死を主題にして、上座部仏教と大乗仏教の両方で4世紀の頃に「涅槃経」が作られたと言う。それぞれに複数の訳経があるため、様々な「涅槃経」が存在することをまず明らかにしている。上座部の涅槃経では釈尊入滅の前後、つまり釈尊の最後の旅と入滅の前後が主たる内容に取り上げられている。一方、大乗の涅槃経では釈尊の入滅という厳粛な時機において、釈尊が入滅前に説かれた教義の内容を取り上げている。両者には釈尊の涅槃の取り上げ方に観点の相違がある点を指摘している。この点が本書での最初の学びであった。
著者は、上座部の説く「涅槃経」をベースにして、第二章・第三章で、釈尊晩年の三大悲劇と80歳で故郷を目指した釈尊の最後の旅の経緯について、それらの要点を読者に分かりやすく語っている。大きめのフォントを使い、語り口調の平易な文は読みやすく、理解しやすい。
三大悲劇とは何か? 1)釈尊の生国カピラヴァスツと釈迦族の滅亡。2)同年代の幼ななじみである提婆達多(だいばだった)の叛逆。3)釈迦が後継者と目していた愛弟子、舎利弗(しゃりほつ)と目連(もくれん)の死。これらがまず、語られていく。
第1の悲劇では、コーサラ国の大軍がカピラヴァスツに向けて進軍する街道の沙羅の枯木の下で、釈尊が坐禅するという行動を三度くり返したと言う。三度は釈迦族殲滅作戦が挫折したとか。そもそもの原因は釈迦族の背信行為にあるそうで、結局釈迦族は殲滅する。このことを本書で初めて私は知った。
第2の悲劇は、提婆達多にそそのかされ、阿闍世王が起こす父殺しと提婆達多が新教団を誕生させ釈尊から離反することである。阿闍世王のことは『観無量寿経』の教えとの関連で多少知識はあった。しかし、『法華経』の第十二品「提婆達多品」に、提婆達多に対する釈尊自身の思い、慈悲心が寓話で示唆しているということを本書で知った。著者は釈尊の心を、友松圓諦訳『発句経』五を例示して説いている。
まこと恨み心は/いかなる術(すべ)を持つとも/恨みを懐くその日まで
ひとの世にはやみがたし/うらみなさによりてのみ/うらみはついに消ゆるべし
こは易(かわ)らざる真理(まこと)なり
第3の悲劇は、釈尊の入滅を間近にして、舎利弗と目連が死ぬという悲劇である。例えば、漢訳の『仏説阿弥陀経』は仏が舎利弗に語る形で描かれている。これだけでも舎利弗が高弟だったとわかる。舎利弗と目連が釈尊の弟子となった経緯が本書に書かれている。また、舎利弗が病死し、目連が伝道の途中で殺され非業の死を遂げたことを本書で学ぶ機会になった。
この時の釈尊の思いは、やはり詩に託されたという。有名な章句だ。
自らを洲(しま)とし、自らを依りどころとして、他を依りどころとしてはならぬ
法を洲とし、法を依りどころとして、他を依りどころとしてはならぬ
第二章で三大悲劇を語り、第三章はいよいよ80歳で故郷を目指す釈尊の最後の旅、死出の旅路の要所要点が語られていく。この最後の旅について、多少の予備知識はあったが、本書でその経緯を整理して理解できた次第。
最後の旅において、釈尊は最後まで己の思いを説きつづけたことが語られていく。ここでは、『発句経』からの引用と説明、此岸から彼岸へ渡る六つの方法(六波羅密:布施・持戒・忍辱・精進・禅定・智慧)、「自灯明・法灯明」、「天上天下、唯我独尊」の本当の意味、「上求菩提 下化衆生」、「生きる縁を大切にせよ」の内容がわかりやすく説かれていく。
釈尊が最後まで説かれたのは、「自灯明・法灯明」の教えであった。そして最後の説法を次のように締めくくられたそうである。これも初めて学んだこと。
「汝ら且(しば)らく止みね(靜にせよ)、また語(もの)いうことなかれ、時(とき)まさに過ぎなんとす。われ滅度せんと欲す。『この世はすべて壊法(えほう:無常・移り変わりゆく)なり。放逸(怠けて修行に専心できないこと)することなく精進(自己完成に励むこと)すべし』これが我最後の教誨(きょうげ:教えさとす)するところなり」
実に耳の痛い言葉と感じる・・・。
ここに上座部仏教の特徴が表れているようである。人間釈尊の死を素朴に語っていき、釈尊の法を説くという立場が貫かれている。
本書の特徴は、この後の第四章を大乗仏教の立場から釈尊の涅槃を説明することに転じていることだ。釈尊が説かれた仏法は、いつ・どこにでも開示されている。この法の常住を中心に釈尊の思想を大乗仏教の経典『大般涅槃経』は説いていると言う。私にとっては、白紙の経典であり、本書でその要点をいくつか学ぶ機会になった。その要点を箇条書きで覚書を兼ねてご紹介したい。詳しくは本書を開いてみてほしい。
*法の象徴としての釈尊は「如来常住」。人間釈尊の死は法を伝える上では方便。
*涅槃のさとりの面を中心に「常楽我浄」(常徳・楽德・我德・浄徳)の四德目を説く。
⇒德:そのものに本来具わっているすぐれた資質という意味
「常楽我浄」を備えるのは法身の釈迦である。
注意点:涅槃経のいう常は、常と無常の相反する二つの見方を止揚統合して創られた
常であるということ。それは創造された常観である。
楽・我・浄もまた同様の思考プロセスを経て創造された楽観・我観・浄観
*「一切衆生 悉有仏性」(命あるものは、すべて仏となる性質(可能性)を内に持つ
⇒「仏性」は大乗経典では涅槃経で初めて登場する言葉だという
*涅槃経は「一闡提(いつせんだい)」ですら成仏できると説く。
⇒一闡提は梵語イッチャンテイカの音写語で<欲望ある人・欲望を持つ人>から
目の前の欲楽を追求して、自分の人間的成長を願ったり、心身のやすらぎな どを思ってもみない人のこと。
⇒異論も多く、長い間論争されてきたが、大勢としては「闡提成仏」の思想は
大乗仏教思想の根幹となっていると言う。
上座部仏教と大乗仏教の双方が伝える「涅槃経」理解への奥は深いのだろう。本書は、その入口を一歩入って学び始める入門書として、分かりやすくて読みやすい一書だと思う。長らく書棚に眠らせていた本書をやっと通読して「涅槃経」群に少し踏み込む動機づけにすることができた。
最後に、本書で印象深い文をいくつか引用してご紹介しておこう。
*釈尊の言葉をそのまま記憶するよりも、釈尊の教えの精神を象徴的に表現するねらいが、大乗仏教徒にあったようです。・・・・(「仏」を釈尊に限定せず、「法を知りしもの、道をさとりひもの」の説を「仏説」と解するように、必ずしも釈尊の説でなくともよし、とするのが大乗仏教者の通説です) p196
*「大乗仏教経典を理解するには、象徴文学を理解するように読まないと、その底に秘められた教えを正しく納得できない」ーー--と喝破したのは・・・・岡本かな子さんです。p196
*人間が(本当の)人間になるために必要なのは、「自分に秘められている仏性を自覚する」こと、つまり「真実の人間性にめざめる」ことです。それはまた自分が済(すく)われることでもあります。自分を済う大きな機能は、自分の中に潜在しているとするのが、大乗仏教の人間観です。 p230-231
*人間が度(すく)われるということは、個々に具わる自己の仏性を自覚して、「人間はどうあるべきか」と自らうなずきとることでなければなりますまい。仏性とか仏心とかいう仏教用語を平たくいうなら、”自分の身に生まれながらに具わっている自分を自分であらしめる根元的な心”となるでしょう。この根元的な心は、また「命」とも、「もう一人の自分」と言い換えてもいいでしょう。 p259
*人間をリードする大いなる力や権威を、多くの宗教は天など人間の外界に設定します。しかし大乗仏教は、人間を人間たらしむる超人間的な機能を、人間の外界ではなく人間の内部に凝視するところに、その特徴があります。それだけ人間性を高次に考え、人間を尊重いたします。こうした思想を完全にまとめたのが、涅槃経です。 p233
*如来(仏に同じ)の名称は、「釈尊が得たさとりの内容」、菩薩の名称は、「釈尊が積まれた数々の修行の内容」です。たとえば、釈尊が積まれた忍耐の修行を、人に踏まれ汚物にまみれる土になぞらえ、その徳の豊かさを人格化して「地蔵」菩薩として崇めます。そのため、忍耐する柔軟な心を象徴して、彫刻でも絵画でも柔和な容姿に表すのです。 p256
ご一読ありがとうございます。
補遺
大般涅槃経 :ウィキペディア
涅槃経 :「コトバンク」
大般涅槃経 : 現代意訳 :「国立国会図書館デジタルコレクション」
松原泰道 :ウィキペディア
松原泰道 宗教家 :「NHKアーカイブス」
松原泰道先生の思い出 2022.08.03 今日の言葉 :「臨済宗円覚寺派大本山 円覚寺」
Vol.06 松原泰道「私が彼土でする説法の第一日です」(最終回) 禅僧のことば
細川晋輔 臨済宗妙心寺派 龍雲寺 住職 :「わたしと仏教」
岡本かの子 :ウィキペディア
インターネットに有益な情報を掲載してくださった皆様に感謝します。
(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。
その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。
その点、ご寛恕ください。)