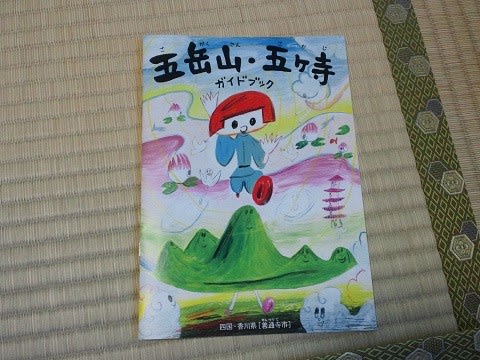1736
今朝の気温77.5度 !?
トイレに置いている時計に表示されている温度が『77.5度』。
10年ほど前に新聞のクイズに当選してもらった時計です。
長年使っているのでとうとう故障したのかな ? それもと電池がなくなって誤動作しているのかな ?
よく見ると温度表示の右上に小さく「F」とあります。セ氏とカ氏が切り替わったようです。
ところが元に戻す方法が分かりません。裏面にSETとか MODEのボタンがあるのですが、日時の設定やアラームの設定はできるものの、温度表示は切り替わりません。取説を探した方が早いかなと思いながらあれこれやってみているとやっと分かりました。単に「V」(下げる)ボタンを押せばよいようです。なにかの拍子に触って切り替わってしまったようです。

それにしても、近頃カ氏という言葉を全く聞きません。「セ氏とカ氏」、昔の温度計には左にセ氏、右にカ氏の目盛りがあって、中学校で換算式も習った覚えがあります。全く忘れていました。少しでも頭にあれば、ああカ氏に切り替わったのだとすぐに分かったと思います。
77.5°(カ氏) は計算してみると 25.3°(セ氏)でした。
今日も暑くなりそうです。
今朝の気温77.5度 !?
トイレに置いている時計に表示されている温度が『77.5度』。
10年ほど前に新聞のクイズに当選してもらった時計です。
長年使っているのでとうとう故障したのかな ? それもと電池がなくなって誤動作しているのかな ?
よく見ると温度表示の右上に小さく「F」とあります。セ氏とカ氏が切り替わったようです。
ところが元に戻す方法が分かりません。裏面にSETとか MODEのボタンがあるのですが、日時の設定やアラームの設定はできるものの、温度表示は切り替わりません。取説を探した方が早いかなと思いながらあれこれやってみているとやっと分かりました。単に「V」(下げる)ボタンを押せばよいようです。なにかの拍子に触って切り替わってしまったようです。

77.5°(カ氏) は計算してみると 25.3°(セ氏)でした。
今日も暑くなりそうです。